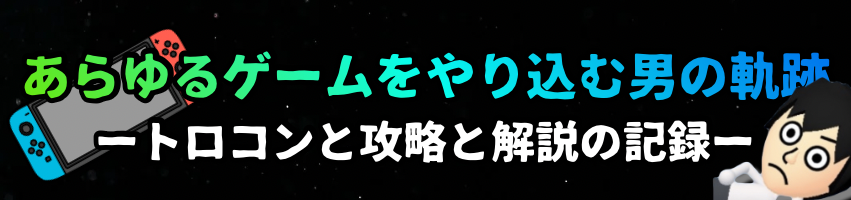- 発売日:1998年1月29日🇯🇵
- ジャンル:サバイバルホラー
- プラットフォーム:PlayStation/ドリームキャスト/NINTENDO 64/ニンテンドーゲームキューブ/PlayStation 3/PlayStation 4/PlayStation 5
- 開発・発売:カプコン
- シリーズ:バイオハザードシリーズ
1998年にプレイステーションで発売された『バイオハザード2』(海外名:Resident Evil 2)は、シリーズファンの心に強く刻まれた不朽の名作。前作『バイオハザード』の大ヒットを受けて制作された本作は、レオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドという2人の主人公による物語が展開する。
ゾンビであふれたラクーンシティからの決死の脱出劇と、G-ウィルスを巡る陰謀を描いたストーリーは、当時として破格のボリュームとスリルでプレイヤーを虜にした。
また、ザッピングシステムと呼ばれる独自のシナリオ構成により、2人の視点から物語を楽しむことができる点も大きな特徴である。
本記事では、レトロゲーム愛好家にも親しみやすい語り口で、『バイオハザード2』のストーリーやゲームシステム、開発秘話、当時の評価、そして後年発売されたリメイク版との比較までを徹底解説する。当時を知るファンも、初めて触れる方も、ラクーンシティ警察署発の悪夢をもう一度体験してみよう。

ちなみに筆者は、ほぼ全てのプラットフォームでプレイ済みなくらいに本作の狂いファンである。最近もPS5で遊びました…。
第1章:ストーリー解説 – レオン編とクレア編の悪夢
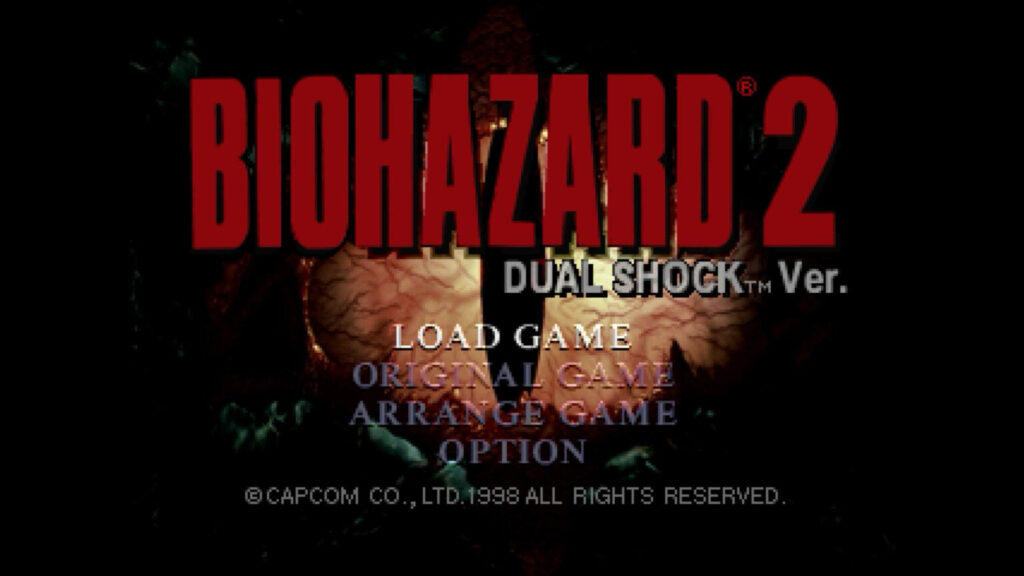
『バイオハザード2』の物語は、1998年9月下旬のラクーンシティを舞台に、新人警官レオンとクリス・レッドフィールドの妹クレアがそれぞれの目的で街を訪れるところから始まる。
偶然出会った二人だったが、街はすでにT-ウィルスによるバイオハザード(生物災害)に見舞われゾンビが徘徊する地獄と化していた。
序盤、レオンとクレアは警察署へ向かう途中で事故に遭い離ればなれになるが、「警察署で落ち合おう」と約束し、それぞれ別ルートでラクーン市警(R.P.D.)を目指す。
ここから先は二人のシナリオが並行して進行し、お互いの行動が物語に影響を与えていく(この仕組みについては後述するゾッピングシステムで詳しく触れます)。
ストーリーについては『バイオハザード2(1998)ストーリー完全解剖|ラクーンシティ崩壊の全貌とG-ウィルスの真実』でより詳しく解説中!

レオン編:初出勤の日に遭遇した地獄

レオン・S・ケネディは配属初日にラクーンシティへ赴任してきた新人警官。市内へ入るや否や無数のゾンビに囲まれ、彼にとって悪夢のような初勤務が幕を開ける。
何とか警察署(R.P.D)へたどり着いたレオンは、署内で生存者の警官マービン・ブラナーと遭遇。瀕死のマービンから街で起きた生物災害の概要を知らされる。レオンはマービンから渡された警察署の鍵を使い館内を探索し、行方不明の署長や生存者を捜索していく。
やがて警察署内で謎の女性エイダ・ウォンに出会い、共に行動することになる。
こうしてレオンの脱出劇が幕を開ける。
クレア編:兄を捜す妹と少女の絆

クレア・レッドフィールドは前作主人公の一人クリス・レッドフィールドの妹で、兄を捜すためラクーンシティを訪れる。
クレアは奮闘しつつ警察署内で幼い少女シェリー・バーキンと出会う。シェリーはアンブレラ社の科学者夫妻(ウィリアム・バーキン博士と妻のアネット)の娘で、混乱する街で両親とはぐれて怯えていた。
クレアはシェリーを守りながら行動を共にするが、警察署長のブライアン・アイアンズにも遭遇。アイアンズ署長は精神に異常を来しており、署内で市長の娘の遺体をコレクションするという狂気的な姿を見せた。
本作では表裏の2つのシナリオを組み合わせることで真の結末が描かれるが、公式には「どの組み合わせが正史」と明言はされていない。

ただ、シリーズ後の展開を見ると、クレア表→レオン裏でのみ描写される「シェリーがG-ウィルスに感染し治療されるエピソード」が後の作品に影響しているため、この組み合わせが事実上の正史と考えられている。
第2章:ゲームシステムと特徴|ザッピングシステム、サバイバル要素、謎解き
本作が当時画期的だったのは、そのゲームシステムと多彩な特徴にある。前作の基本を踏襲しつつも、新たな試みが随所に盛り込まれ、プレイヤーを飽きさせない工夫が施された。
本作ならではの二人の主人公によるデュアルシナリオとザッピングシステム、限られたリソースで生き延びるサバイバル要素、そして頭を悩ませる謎解きや隠しモードについて、それぞれ詳しく見ていこう。
2人の主人公と「ザッピングシステム」

本作の最大の特徴が、レオンとクレア2人の主人公によるダブルシナリオである。ゲーム開始時にレオン編かクレア編かを選び、一方の「表」シナリオをクリアすると、もう一人の「裏」シナリオがプレイ可能になる構成だった(表レオン、裏クレア、または表クレア、裏レオンの全4シナリオが存在) 。
この表裏シナリオは内容が独立しているわけではなく、ザッピングシステムと呼ばれる仕掛けによって密接に絡み合っている。
例えば、表シナリオでサブマシンガンやサイドパックといった貴重なアイテムを取るかどうかで、裏シナリオ側にそれが残っているかが変わる。
また、表で特定の行動(例えばシャッターを下ろして廊下の窓を封鎖する等)を取ると、裏でゾンビの出現状況が変化するなど 、合計9箇所の連動ポイントが用意されていた。
このようにプレイヤーの行動がもう一人の主人公に影響を与える仕組みにより、一度クリアした後も新鮮な気持ちでもう一方のシナリオを楽しめた。
ザッピングシステムのおかげで、ストーリーも様々な角度から深掘りされる。表では語られなかった裏側の出来事が裏シナリオで明かされたり、表ではすれ違っただけのレオンとクレアが裏では無線で会話するシーンが追加されるなど、二周目で初めて判明する情報も多く用意されていた。
「2人の物語が同期して進行している」というコンセプトは、当時としては斬新で、プレイヤーに強い没入感を与えた。
このシナリオ連携の着想は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』で前作の出来事を別視点から見る演出にヒントを得たものだという。映画的なアイデアをゲームプレイに落とし込んだザッピングシステムは、『バイオ2』を語る上で欠かせない革命的な特徴であった。
限られた弾薬、インベントリ管理と緊張感

前作同様、本作もサバイバルホラーとして限られた資源を管理しながら進む緊張感が醍醐味。プレイヤーはキャラクターごとに限られたインベントリ(持てるアイテム枠)の中で、武器・弾薬・回復薬・鍵アイテムなどをやりくりしなければならない。
不要なアイテムは各所にあるアイテムボックスへ預けることができるが、ボックスの中身は全てのボックスで共有されるため、一つに預ければ離れた場所のボックスからも取り出せる仕組みだった。
これを活用して必要物資をやり繰りする戦略性が要求される。また、弾薬は序盤こそハンドガンの弾がある程度手に入るが、強力なショットガンやグレネードランチャーの弾は数が限られる。
全ての敵を倒そうとするとすぐ弾切れになるため、「戦うべきか逃げるべきか」を常に考える必要があった。特にレオン編ではマグナムやショットガン、クレア編ではグレネード弾など強力な火器をいつ使うかが生死を分ける。

それでも本作の弾薬数は前作よりも緩和されていて、そこまで弾切れを起こす場面は少ない。

セーブ(保存)にもリソース管理の要素があった。タイプライターで進行をセーブするにはインクリボンというアイテムが必要で、これも有限。
何度もセーブしすぎると後半でインクリボン不足に陥る可能性があるため、ここぞというタイミングでのみセーブを行う緊張感も味わえた。
もっとも、ゲームに慣れてくれば少ないセーブ回数でのクリアに挑戦したり、クリア後のランク評価向上のために節約プレイを楽しむユーザーも多く、生存戦略の幅が広がる要素でもあった。
さらに本作では、主人公の負傷状態が見た目と動作に反映される演出も秀逸だった。体力が残り少ない「Danger」状態になると、キャラクターが腹部を押さえて足を引きずるように歩くため移動速度が大幅に低下する。
これによって「重傷を負っている」という緊張感がプレイヤーにも直感的に伝わり、ただでさえ恐ろしいクリーチャーとの遭遇がさらにスリリングになる効果を生んでいた。
例えば、廊下でゾンビ犬に大怪我を負わされた後、その足で何とかセーフルームまでたどり着こうとノロノロ逃げる――そんな映画さながらの緊迫感を自分で体験できる。
こうした細かな演出が積み重なり、プレイヤーはラクーンシティの地獄を文字通り身を引き裂かれる思いでサバイバルすることになった。
謎解きと探索要素|美術館の名残りを巡る鍵

『バイオハザード』シリーズといえば謎解き要素も欠かせない。本作の舞台となるラクーン警察署は前述の通り元は美術館として使用されていた建物であり、そのため館内には不思議な仕掛けやパズルが数多く存在する。
警察署の各階へ通じる扉にはスペード・ハート・ダイヤ・クラブのトランプの絵柄が刻まれており、それぞれ対応するカードキーを見つけなければ開錠できない。プレイヤーはゾンビの脅威にさらされつつも館内をくまなく探索し、机やロッカーの中から鍵やアイテムを見つけ出す必要がある。
代表的な謎解きとして、メインホールにある女神像の仕掛けがある。像の持つ皿に宝石をはめ込むと隠された通路が開くといった具合に、美術館らしい芸術品を絡めたパズルが点在していた。
また、図書館の本棚を動かして地下へのハシゴを出現させたり、下水処理場では巨大な将棋の駒型プラグを集めて電力を復旧させたりと、バリエーションも豊富。
こうした謎解きを解決しながら少しずつ行動範囲を広げ、新たなエリアへの扉を開けていく探索の流れは前作から踏襲されたシリーズ伝統のゲームデザインである。
プレイヤーはマップやファイル(書類に書かれたヒント)を頼りに「あの鍵はどの扉だろう?」「このアイテムはどこで使うのか?」と頭をひねりながら館内を行き来することになる。
謎解き要素は怖さを和らげる「一服の清涼剤」であると同時に、物語の背景を伝える役割も果たしていた。例えば、署長室で見つかるファイルからは署長アイアンズの狂気とアンブレラ社との繋がりが読み取れたり、研究所で発見する報告書からはG-ウィルス計画の断片が明かされたりする。
パズルの合間に読み解くファイル類もファンにはたまらない要素で、隅々まで探索することでラクーンシティで何が起きていたのかを深く知ることができた。
隠しモードとやり込み要素 – 豆腐も登場!?
本編の表裏シナリオだけでも十分なボリュームを誇る『バイオハザード2』だが、さらにファンを喜ばせたのがクリア後に遊べる隠しモードの存在。
その筆頭が、シリーズでも語り草になっている「The 4th Survivor」(第四の生存者)モード。これは本編を特定条件でクリアすると出現するおまけシナリオで、アンブレラ特殊工作員ハンクを操作してラクーンシティ警察署屋上のヘリポートを目指すタイムアタック形式のゲーム。
限られた装備で次々襲い来る敵をかいくぐりゴールを目指す内容で、ハンクの冷徹なキャラクター性も相まって本編とはひと味違う硬派なミニゲームとして人気を博した。

さらに極めつけが、「The 豆腐 Survivor」(ザ・豆腐サバイバー)という超ユニークな隠しシナリオである。こちらは4th Survivorをクリアした猛者へのご褒美モードで、なんと巨大な豆腐(!)を操作キャラクターとしてプレイする前代未聞の内容であった。
豆腐は関西弁で「いてっ!」「なにすんねん!」などとしゃべりながらナイフ一本でゾンビだらけの下水道を突き進む。見た目のインパクトとコミカルな演出に、多くのプレイヤーが驚きつつも大笑いしたことだろう。

筆者は大笑いよりも沈黙だった(笑)とにかく驚きました(笑)
開発スタッフの遊び心が炸裂したこのモードは、『バイオ2』の伝説的おまけ要素として今なお語り草になっている。豆腐モード誕生の裏には、デバッグ用ポリゴンモデル(当たり判定テスト用の白い豆腐状オブジェクト)を流用して主人公に仕立てたという経緯があり、開発陣のユーモアとサービス精神が感じられる。

豆腐の難易度は異様に高く、筆者が子供の頃はいっっっっっさいクリアできませんでした。
その他にも、後に発売されたデュアルショック版では追加要素として、本編とは別軸の戦闘シミュレーションゲーム「Extreme Battle」が収録された。レオンやクレア、さらには当時はまだ名前程度しか登場しなかったクリス・レッドフィールドまで操作可能なキャラクターに据え、アンブレラ施設からの脱出を目指すミニゲーム。
本編クリア後も長く遊べるやり込み要素が満載だったことも、『バイオハザード2』が名作と呼ばれる所以だろう。
第3章:開発秘話|“没になったバイオ2”と再出発のドラマ
本作の開発舞台裏には、波乱万丈のドラマがあります。実は本作、最初に作られていたバージョン(通称「バイオハザード1.5」)がほぼ完成間近にも関わらず一度開発中止となり、ゼロから作り直されている。
そこには三上真司プロデューサーや神谷英樹ディレクターらスタッフの葛藤と決断があった。この章では幻の「バイオ2(1.5)」が葬られた経緯と、新生『バイオハザード2』誕生の秘密に迫る。
当時のゲーム雑誌やインタビューから明らかになった逸話の数々をひも解き、ファンの知的好奇心をくすぐる開発秘話を紹介しよう。

調べ尽くすまでにリアルに10日間くらい掛かってます笑
幻の『バイオハザード1.5』 – 一度完成しかけた続編

初代『バイオハザード』の世界的大ヒットを受け、続編の開発は早々にスタートした。開発チームは約40~50名の若手スタッフ中心で編成され 、ディレクターには前作でプログラムやゲームデザインに関わった神谷英樹氏が抜擢された。
三上真司氏はプロデューサーとして現場を見守る立場だったが、当初から神谷との間でゲーム内容に対する意見の相違があったという。三上はあえて細かい口出しを避け、月に一度のペースで進捗をチェックする形で開発を進めさせていた。
しかし、制作が佳境に入るにつれ不安が募る。個々の要素の出来は決して悪くないものの、それらを組み合わせても前作以上の満足感が得られる作品になっていない――三上はそう直感した。
当初予定していた発売日は1997年5月とされるが、その直前になってもなお完成度に納得がいかなかったという。
ついに三上は「このままでは面白くならない」と判断し、自ら辞表を用意した上で上層部に開発中止とスケジュール延期を直訴するという決断に踏み切った。この勇気ある進言により、完成度60~80%に達していた最初の『バイオハザード2』は白紙撤回されることになった。

ファンが後に「バイオハザード1.5」と呼ぶことになるこの没バージョンでは、現在の製品版とは大きく異なる設定やシナリオが展開されていた。
主人公はレオンこそ共通だが、もう一人の女性主人公はエルザ・ウォーカーという名前の新キャラクターで、ラクーンシティ出身の大学生&バイクレーサーという設定だった(製品版でクレアに置き換わった人物)。
舞台となる警察署も美術館ではなく近代的な建物で、内装もより現実的なオフィスに近い雰囲気だった。警察署内で出会う生存者も異なり、例えば製品版でレオンが出会うエイダ・ウォンの立ち位置にはリンダという女性研究員が登場し、クレアの代わりにエルザが出会う少女シェリーを助ける相棒としてジョンという男性が登場する予定であった (ジョンは製品版では銃砲店主ケンドに相当)。
また、敵クリーチャーの配置や種類も一部異なり、探索するエリアも現在とは違った構成だったようだ。
では、なぜせっかく作り上げた1.5が没になったのか。その理由は前述の通り「ゲームとしてつまらない」というシンプルかつ深刻なものだった。加えて、岡本吉起製作総指揮からの指摘も決定打となった。岡本は当時の1.5について「ストーリーが綺麗にまとまりすぎていて、これ以上続編を作る余地がない」と感じたと言う。
つまり物語が完結しすぎて世界が広がらないという。そこで岡本は「このシリーズをガンダムや007のような長寿シリーズに育てるため、もっと世界観を広げよう」と提案する。1.5の物語ではラクーンシティで起きた事件がそこで完結してしまい、続編につなげにくい閉じたストーリーだったことが問題視されたのである。
再スタート – 新ストーリーとキャラクターの誕生

開発リセット後、新生『バイオハザード2』の制作が改めて始動する。しかし当初、開発チーム内で満足いくシナリオを書き直すことができず行き詰まってしまう。
そこで岡本氏が白羽の矢を立てたのが、当時シナリオライターとして活躍していた杉村升氏であった。杉村氏は特撮ヒーロー番組などを手掛けていた脚本家で、偶然にも『バイオハザード1』のストーリーに感銘を受けていた人物であった。
杉村氏は試用という形で開発に参加すると、その手腕でシナリオ上の問題点を次々と解決して行く。彼の貢献により、岡本から全幅の信頼を得て本格的にストーリー改稿を任されることになった。

杉村氏がまず着手したのが、前述のエルザ・ウォーカーをクリスの妹クレアに置き換えるというアイデアだった。シリーズの継続性を高めるため、全くの新キャラだったエルザを既存キャラの肉親に変更することで、ファンの共感と物語の広がりを両立させようとした。
この判断は結果的に功を奏し、クレア・レッドフィールドというキャラクターはシリーズ屈指の人気を誇るヒロインとなった。また、警察署を美術館跡に設定し直したのも杉村氏の発案とされている。これにより「警察署に妙な仕掛けが多すぎる」という不自然さに説得力を持たせ、独特の雰囲気づくりにも成功した。
ストーリー面では、岡本の方針通り物語のスケールを広げシリーズ化に耐えうる世界観が構築された。ラクーンシティという街全体が事件の舞台となり、アンブレラ社の闇やウィルス兵器の脅威がより広範囲に描かれるよう修正されたのである。
さらに神谷ディレクターはカプコンから提示された「販売目標200万本」を達成すべく、「新規ファンを獲得するためストーリーをハリウッド映画のように大げさなものにしてはどうか」と提案した。結果、生まれたのがレオンとエイダの淡いロマンスや、クレアとシェリーの擬似親子的なドラマなど、人間模様を前作以上にドラマチックに描いた演出だった。

事実、当時の海外ゲーム誌GameProのレビューでも「ドラマチックで面白いストーリーと魅力的な会話」を高く評価する声がある。
こうした刷新に伴い、一時中断していた開発は再び軌道に乗り始める。ゲームデザインも根本から練り直され、不要になったリソースは他プロジェクトへ転用された。

たとえば、プログラマー等の一部スタッフは『バイオハザード1 ディレクターズカット版』の制作に回り、このディレクターズカットにはお詫びも兼ねて1.5の映像や『2』の体験版が収録されることになった。発売延期となったファンへのサービスとして、雑誌や体験版ディスクで新生『2』の情報が少しずつ公開され、期待が高まって行った。
興味深い裏話として、没になった1.5のゲームエンジンは廃棄されずに後の別タイトル開発に役立てられている。プロモーションプロデューサーだった稲船敬二氏が「せっかく作ったものを捨てるのはもったいない」と1.5のエンジンを引き取り、和風アクション『鬼武者』の開発に流用したというエピソードである。
ゲーム業界では試作エンジンの使い回しは珍しくないが、有効活用の極端な例としてファンの間でも語られる逸話となっている(稲船氏本人がテレビ番組『ゲームセンターCX』の中で語っている)。
プロモーションと演出 – 映画さながらのCMと熱意

再構築された本作には、開発陣の演出面でのこだわりも多く盛り込まれた。ゲーム内ムービーは当時最高水準のCG映像で描かれ、ゾンビが群れで押し寄せるシーンや爆発する研究所からの脱出など、ハリウッド映画さながらの迫力だった。
キャラクターの台詞は今回も全編英語音声で収録されたが、日本人スタッフが日本語脚本を英訳しカナダ人俳優に演じさせるという手法だったため、ネイティブから見ると少し不自然で大げさなセリフ回しになってしまったそうだ。
開発スタッフも後年のインタビューで「海外記者から演技が“Cheesy”(古臭い大げささ)だと言われた」と苦笑交じりに振り返っている。しかしこの多少芝居がかったボイスアクトこそ、当時のB級ホラー映画的な味わいを生み、逆にファンから愛される要因にもなった。

プロモーション面でも、カプコンは本作に相当力を入れていました。特筆すべきは、ゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督が手掛けた実写テレビCMだろう。
このCM撮影は1997年9月末にロサンゼルスのセットで行われ、ラクーン市警の館内を忠実に再現した舞台でレオン役の俳優とクレア役の女優が大勢のゾンビに立ち向かうという内容だった。
レオン役には当時若手俳優として注目されていたブラッド・レンフロが起用され、特殊メイクは日本人アーティストのスクリーミング・マッド・ジョージ氏が担当するなど、その豪華さはゲームのCMとして異例だった。
ロメロ監督は『バイオハザード』映画版の監督候補にも挙がっていた経緯があったが、結果的に映画は別人が監督しロメロ版は実現せず…とはいえ、このCMで「幻のロメロ版バイオハザード」を垣間見れたのはファンにとって貴重なサプライズであった。
さらにカプコンは当時、このゲームの宣伝に500万ドルもの予算を投下したと報じられている。発売前からゲーム雑誌で大々的に特集が組まれたのはもちろん、体験版や店頭プロモーションビデオ、果ては実写CMまで投入されたことで、『バイオハザード2』への期待感は発売前夜にはピークに達していた。
第4章:発売当時の反響と社会的影響 – シリーズ人気を決定づけた傑作
1998年1月29日に満を持して発売された本作は、発売後瞬く間に大ヒットを記録した。その勢いは販売本数や各種評価に如実に表れており、シリーズの人気を決定づけた作品としてゲーム史に名を残すことになる。
ここでは発売当時の売上データやメディアの評価、そしてゲーム文化への影響について振り返ってみよう。
圧倒的な販売記録と商業的成功
本作は発売と同時に飛ぶように売れ、発売週末だけで北米では38万本を売り上げ190万ドルの利益を記録。その売れ行きは当時として異例の早さで、北米において発売直後の販売ペースが史上最速とも報じられた。
さらに全世界累計ではシリーズ前作(約280万本)を大きく上回る約496万本という驚異的な数字を叩き出し、当時のカプコンの販売目標200万本を悠々と突破している。この約496万本という販売実績は、長らく「シリーズ史上最高の売上」として語られて来た。(※後年、リメイク版が更新するまでの記録)。
また日本国内に限っても、発売から1か月で190万本のセールスを達成し、1998年に200万本超えを唯一達成したタイトルとなっている。初代がじわじわと口コミで広がったのに対し、『2』は満を持しての続編という期待から初動で爆発的ヒットしたことがうかがえる。
この商業的成功の背景には、前述の大規模な宣伝や映画的な演出強化が功を奏し、より幅広いユーザー層を取り込んだことが挙げられる。
「ハリウッド調の演出が購入者の目を引き、当時トップだった『ファイナルファンタジーVII』や『スーパーマリオ64』の記録を打ち破った」との分析もあり 、ストーリー性とアクション性の両立した本作はコアゲーマーからライト層まで巻き込んだ。
また、この大ヒットによりカプコンはシリーズ展開に一層注力するようになり、後続作品や様々なメディアミックス(小説・漫画・玩具など)展開の基盤が築かれた。いわば『バイオハザード2』は、バイオハザードというIPを世界規模のフランチャイズへ押し上げたエポックメイキングなタイトルだったのである。
メディア評価とゲーム文化への影響

批評家やゲームメディアからの評価も非常に高く、発売当時多くの雑誌で高得点レビューが相次いだ。例えば、日本のゲーム誌『電撃PlayStation』では4人のレビュアーがそれぞれ100点満点中65/75/80/90点をつける高評価となり、総合的にも「期待以上の出来」という論調だった(※点数は当時の雑誌評価システムによるもの)。
海外でもGamePro誌のレビュアーが「ドラマチックで面白いストーリー」と「うまくまとめられた魅力的な会話劇」を絶賛するなど 、ストーリー面の充実が評価されるコメントが目立った。またIGNやGameInformerといった主要メディアの年間ベストにも名前が挙がり、「サバイバルホラーの金字塔」との呼び声も高かった。
プレイヤーからの支持も厚く、発売から年月を経ても高い人気を保ち続けている。イギリスのRetro Gamer誌が行った読者投票では本作が歴代ゲームランキングで97位にランクインし、編集部コメントで「長寿シリーズの中でも最高傑作だと多くの人々が考えている」と紹介された。
また、2000年代に入ってからもファンの間で「もう一度リメイクしてほしいゲーム」の上位に挙げられるなど 、根強い愛着が持たれてきた作品である。

社会的影響という観点では、本作の成功により「サバイバルホラー」というジャンルがゲーム文化に定着したことが挙げられる。『バイオハザード2』のヒットを受けて、他社からも次々とホラーゲームがリリースされるようになった。
有名なところではコナミの『サイレントヒル』(1999年)など、本作に触発された作品も少なくない。また、当時はバイオブームとも言える現象が起き、ゲーム雑誌でホラーゲーム特集が組まれたり、関連グッズが多数発売されたりもした。
1998年には実写映画化の企画も動き出し、後にハリウッドで映画シリーズが展開するきっかけにもつながっている(※実際の映画公開は2002年以降)。

一方で、暴力描写の過激さゆえの論争もあった。例えばイタリアでは市民団体から「残酷すぎる」との抗議を受け、発売前のソフトが財務警察に差し押さえられる事件も起きている。
最終的に発売禁止処分は解除されたものの 、この出来事はゲーム表現のあり方について議論を呼んだ。
もっとも、日本国内ではCERO:C(15才以上対象)という年齢区分の範囲内で発売されており、大きな問題にはならなかった。むしろ「血の色を緑に変更できるオプション」や「自動照準の有無」など海外版との違いが話題になる程度で 、作品そのものの面白さが議論をさらうことはなかったと言える。
総じて『バイオハザード2』は、商業的成功と高い評価によってシリーズの地位を不動のものとしたタイトルであった。
レオン・クレアという新主人公コンビはファンに強く支持され、後のシリーズ作品やスピンオフにも登場する人気キャラクターとなった(レオンは『バイオハザード4』『6』主人公、クレアも『コード:ベロニカ』『リベレーションズ2』主演など)。
発売から四半世紀以上が経過した現在でも、多くのゲーマーにとって『バイオ2』は特別な思い入れのある一作となっている。
最後に
『バイオハザード2』は、ゾンビに制圧されたラクーンシティで繰り広げられる極限のサバイバルドラマと、それを支える革新的なゲームシステムでゲーム史に燦然と輝く作品と言える。
レオンとクレアのダブル主人公によるゾッピングシステムは当時プレイヤーを驚かせ、開発中止からの奇跡の復活という舞台裏も含め、その存在自体がドラマチックであった。
発売当時の熱狂や社会的インパクトは凄まじく、そして20年後に生まれ変わったリメイク版で再び世界を熱狂させた事実は、この作品が時代を超越した魅力を持っている証拠だろう。
もし未プレイであれば、ぜひオリジナル版とリメイク版の両方に触れてみて欲しい。ポリゴンの荒い映像から想像力を刺激される1998年版の恐怖と、精巧なグラフィックで直視する2019年版の恐怖はベクトルこそ違えど、根底に流れる「サバイバルホラーの楽しさ」は共通している。
『バイオハザード2』という名作は、これからも語り継がれ、そしてプレイし継がれていくことだろう。レオンとクレアが駆け抜けたあの悪夢の一夜は、我々ファンの心の中で永遠に生き続ける。