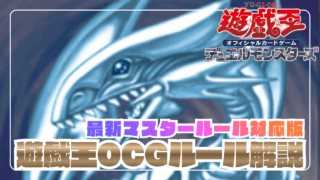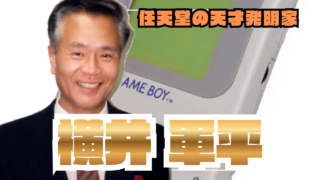「こんなRPG、もう出ない」
そう断言してもいいほど、『ウィッチャー3 ワイルドハント』は筆者にとって特別な作品だ。
2015年の発売から10年近く経った今でも、PS4でここまで没入できるゲームは数えるほどしかない。ゲラルトの一歩ごとに風景が変わり、街の騒がしさ、怪物の息づかい、決断の重み。
その全てが、プレイヤーの選択によって姿を変えていく。ゲラルトの運命までも、、、
RPGというジャンルに慣れている人ほど、ウィッチャー3の世界に踏み込んだ瞬間、「うわ、ここまで作り込むか……」と声が出るはずだ。
しかも、このゲームはただ広いだけじゃない。
寄り道した先には、ちょっとした短編小説レベルのサイドクエストが転がり、ローチ(馬)に跨り旅しているだけで1時間が消える。
気付けばあなたも、世界のどこかで夕陽に見とれて、「今日メインクエスト進んでないな…」とどこか満足げな顔を浮かべていることだろう、、、。
今回はそんな魅力あふれる傑作『ウィッチャー3』について詳しく解説して行こう。
『ウィッチャー3 ワイルドハント』とは?

- 発売日:2015年5月19日
- 開発:CD PROJECT RED
- 発売:CD PROJECT RED(日本ではスパイク・チュンソフト)
- プラットフォーム:PlayStation 4/Play Station 5/Nintendo Switch/Xbox One
- ジャンル:アクションRPG/オープンワールド
第1章:ストーリー・深掘り

物語は、主人公の『リヴィアのゲラルト』と呼ばれるウィッチャー(魔物ハンター的な)が、かつての恋人であり強力な魔女『ヴェンガーバーグのイェネファー』からの手紙を受け取り、旅を再開するところから始まる。
彼女との再会後、帝国 ニルフガード帝国 の皇帝『エムヒル・ヴァル・エムレイス』からの命令で、ゲラルトは養女でありウィッチャーの徒でもある『シリラ・フィオナ・テラ・リアノン(通称・シリ)』を追うことになりる。彼女は“古代の血(Elder Blood)”を引く特殊な能力者であり、謎の軍団・ワイルドハントに狙われているのである。
この「追う者と追われる者」という構図が、物語の大きなエンジンとなる。
深掘り:血と鉄と愛と戦い
物語の核にあるのは、グラルトの“守るべきもの”――それは、かつての恋人であり魔法使いのイェネファーや、運命の子であり、彼の徒となりうるシリとの再会、そして差し迫る「ワイルドハント」の脅威。
ストーリー展開はしっかりと『英雄の旅』の構造を持ちつつ、重厚さ・悲哀・ユーモアをバランスよく含んでいる。レビューでも「選択肢を思い返す」「物語に引き込まれる」という声が数多く。
例えば、あるサイドクエストでは…(ネタバレにならない範囲で)村人を助けるか、見捨てるかでその後の展開が変わるというものがあった。
その結果、「あの時助ければ…」と後悔したり、「助けてよかったな」って思えたりするわけだ。どちらの選択肢も正解ではなく、あなたの物语として刻まれていく。ゲームなのに、まるで人生の縮図を見てるような気分にさせられる。
また、拡張コンテンツも非常に評判が高い。例えば、Hearts of Stone や Blood and Wine、特に後者は「別ゲームと言ってもいいほどのボリューム」と評された。グラルトとしての旅の締めくくりを飾るにふさわしい内容である。
第2章:世界観・イントロダクション:魔物も恋も散る世界

まず、本作の舞台となる世界をざっくり押さえよう。
舞台は「北方諸国」。王国と帝国、野盗と妖魔、そして『魔女狩りの宴』とも言える混沌。グラルトは魔物狩りのウィッチャーとして生きているが、本作では「魔物を狩る」だけでは終わらない。
物語の大きなテーマは、「失われた家族」と「帰るべき場所」、そして「迫りくる大いなる脅威・ワイルドハント(Wild Hunt)」である。
ウィッチャー3はシリーズ第3作であるものの、初心者でも入りやすいよう設計されており、前作までをプレイしていなくても楽しめるようになっている。
例えば、俺が初めて起動した時のことを思い出す。
また、世界の描写は非常に丁寧。広大なマップ、時間・天候の変化、村や町ひとつひとつに人の営みが感じられるNPCたち。レビューでも「探検するだけでワクワクする」など高く評価されている。
ただし、広大な世界には『寄り道地獄への落とし穴(良い意味で)』もある。油断すると「この森の奥に宝箱が…」「あ、この洞窟気になる」→気づいたら5時間経過、現実に戻れないことも。白狼あるあるである。
第3章:ゲームシステム:剣を振り、印を打て、馬に乗れ
本作のゲームシステムは、とにかく「剣」「印」「馬」を軸に構成されている。
戦闘&魔法(印)

グラルトの主な装備は「鋼の剣(人間用)」「銀の剣(モンスター用)」という、典型ウィッチャー装備。この2本を巧みに使い分けて戦っていく。
更に、『5つの印』という呪文めいた技も使えます。例えば「アード」で敵を吹き飛ばし、「イグニ(」で火事を起こすなど。 このシステムが戦闘を単純な「殴って回避して」から一歩上に押し上げている。
戦闘におけるポイントは「準備」である。魔物の弱点を調べ、オイルを塗り、爆弾を用意する。まるで「今日の夜ご飯なににしよう…あ、魔物を焼こうか」的な気分である。
RPGとしての『ハクスラっぽい要素』もきちんとあるが、本作では“目的”=物語“帰結”がしっかりしているので、「装備集めだけして終わり」になりにくい点も好印象である。
ただし注意点も。多数のレビューによると、武器の耐久度システムやロックオン・カメラの不安定さなど、若干の粗さも指摘されている。(筆者はそこまで感じなかったが)
耐久度切れで「うわ、剣使えねぇ」→魔法でごり押し…というのも白狼あるあるだ。
オープンワールド&探索

マップは非常に広く、多くのレビューで「RPGの理想形」の一つとして挙げられている。
村→森→山→島といった多様なロケーションに加え、馬で疾走、船で海を巡る場面も。移動だけで絵になる。
PS4版では解像度やフレームレートなどハードウェア制約もあっが、体験としては十分満足できると評価できる。(当時の最新機種PS4ですらめちゃくちゃ重かった)
「ちょっとお気に入りスポットで写真撮ろう」と思ってスクリーンショットを撮ると、いつの間にか30分経っていて「あ、今メインストーリーの途中だった…」ということに…。
SNS用の旅ログ用素材としても超重宝する。あなたのインスタに『白狼が馬と夕焼けに映る画像』を載せれば、いいねが稼げるかも…。
クエスト・選択と結末

本作のもうひとつの強みは「選択肢による分岐・その結果が物語に影響を与える」という点。Steamのレビューでも「自分の選択を今も思い返す」などというコメントが出ている。(確かに…印象的すぎる文化があまりにも多い)
例えば「この村を助けるか放置するか」「この人間を信じるか騙すか」など、それによりグラルトの立場、世界の状況、イベント後の展開が変わることがある。まさに魔物を狩るだけじゃないRPGの醍醐味がある。
ただし全てが壮大な分、ちょっとしたサイドクエストにはお使い感が感じられるというレビューもあるが、そのストーリーが面白すぎる。「つい寄り道しちゃう」魅力があるのが本作の良さである。
ミニゲーム&コレクション要素

本作には、名物ミニゲームGwent(グウェント)が登場する。カードを集めて対戦し、勝てば報酬もあり、時には物語の核心に関わることも。遊び疲れたら「カードでもやるか」となる中毒性あり。単体のゲームとして出しても問題ないくらいのクオリティを誇っている。
筆者はグウェントにあまりにもハマりすぎて、カードコンプリートはもちろんのこと、プレイ時間は50時間以上、グウェントだけでブログ記事を15も書いたことも、、、、笑
他にも、錬金・クラフト・装備強化・馬の世話・怪物調査など、「やりこみ」要素は盛りだくさん。
PS4版で遊ぶなら知っておきたいこと
- ロード時間とフレームレート
- PS4版では時々ロードが長め、またフレームレートが落ちることもレビューで指摘されている。つまり、「魔物が出た、剣を振るぞ!」と思ったら、一瞬の間に「あれ、馬ローチが止まってる?」「画面カクッ」…なんてことも。忍耐が試される場面も多々ある。
- セーブをこまめに
- オープンワールドRPGあるあるだが、進行中にバグや落ちる可能性も。馬が動かないとか、進行不能になるクエストも話題に上がった。
- お気に入りの馬ローチに乗ったまま壁に挟まって動けなくなったら…それはそれでX用のスクショ素材になるかもだが。。。
- 寄り道の誘惑に勝てるか?
- このゲーム、「つい立ち止まって景色眺める」「この洞窟入ってみる」「馬で丘に登ってみる」…で1時間消える。
- SNSに「旅してます」投稿するために立ち止まるならいいが、実はクリアを目指すなら“ほどほど”が肝。でもそれが良いんだよな、、、。
- 難易度と遊び方の選択
- 戦闘をサクッと楽しみたいなら『ストーリー重視モード』、じっくり準備・装備・錬金も楽しみたいなら『ハードモード』など。白狼として“伝説を目指す”なら後者をおすすめします。
- ハードモードはかなり絶妙な難易度バランスになっており、理不尽な要素がほぼない。(主観)
- 日本語対応も確認
- 日本語吹き替え・字幕版があるので、英語がちょっと苦手でも安心。セリフ量も膨大なので読み疲れないよう、プレイ中は「あ、ローチに乗って休憩ね」的な休憩を挟むのも手。
- 日本語版声優さんも豪華で、ドン引きするくらいに各キャラクターにマッチしているので、普段洋画で吹き替えを毛嫌い筆者でもオススメしたくなるレベル。
- SNS&ブログ旅ログ素材としても◎
- あなたがSNSやブログを活用されているなら、このゲームは撮れ高豊富。
- 「夕焼けの海辺でグラルトが剣を構える」「ローチと二人旅」「怪物退治→トロフィーゲット」など、写真+軽い一言でゲーム旅ログが作れる。投稿タイミング、ハッシュタグ、英語+日本語ミックスで「#Witcher3 #旅するウィッチャー #白狼日記」なんて入れたら、ファン層にも刺さるかもしれない。
第4章:なぜ“名作”と呼ばれるのか:白狼伝説を紐解く

本作が、ただの良いRPGではなく伝説級とされる理由はいくつかある。
- 量と質の両立
- レビューでは「広大な世界」「膨大なサイドクエスト」「自由度の高さ」といった“量”だけでなく、「各クエストのドラマ性」「選択の重み」「キャラクターの魅力」といった質も高いと評価されている。
- 世界構築の巧みさ
- 村・町・人・魔物・伝承――それらが存在感をもって配置されており、「歩くだけで物語が始まる」ような没入感がある。レビューでも「探索するだけでワクワクする」などの声あり。
- 選択と結末の深み
- プレイヤーの選択が意味を持つ。これは最近のゲームでもよく言われるが、本作ではかなりのレベルで実現されている。先述の通り、選んだ道がそのまま物語に影響を与え、かつそれが演出としても成立している。
- 時間を忘れる没入感
- 「もう1クエストだけ…」→気づいたら10 時間経過。レビューで探検するだけでプレイする価値ありと書かれたことも。
- バグや技術的課題があっても魅力が勝る
- 技術的には「時折バグ」「ロード時間」「フレームレート低下」といった指摘も多々ある。しかし、それでも「許せる」「それを補って余りある体験」というユーザーが多数。つまり魅力が技術的欠点を凌駕しているということだ。
このような諸要素が揃って「RPGとは何かを問い直す傑作」として、ゲーム史に名を刻んでいるる。PS4という家庭用ハードでもその体験がしっかり味わえる点も敷居を下げた偉大さと言える。
第5章:制作秘話

衝撃的すぎる制作費
本作は、開発開始から約3年半かけて制作され、制作+マーケティング費用が約8,100万ドル(日本円で125億円)という非常に大規模なプロジェクトだった。
また、開発初期は150名ほどのチームがスタートし、最終的には社内250名以上、外部も含めると1,500名以上が関わっていたと報じられている。
制作だけじゃなく、宣伝にもしっかり予算が割かれていた」ことを示し、単なるゲーム作りではなくグローバル大作として戦略的に作られたことが分かる。
技術・エンジン・世界構築について
本作はスタジオ独自のゲームエンジン『REDengine 3 』を使用している。これはオープンワールド&マルチプラットフォーム(PC・PS4・Xbox One)に対応するために設計されたものである。
エンジンの特徴として、物理ベースシェーディング(PBR)、高ダイナミックレンジ(HDR)、フォワード・ディファードレンダーパイプライン、ボリューメトリック効果(雲・霧・煙など)といった先進的なグラフィック技術が導入されていた。
制作陣の意図として、「ただ広い世界を作る」だけでなく、「その世界に人が暮らしている感じを出す」=つまり歩いていて何か起こる・寄り道して意味があるという体験を重視していたことが、インタビュー記事から窺える。
吹き替えの規模が異次元
シナリオ・テキスト量も膨大で、登場人物の会話・クエスト文・選択肢の数などが映画1本分と言われるほど。
インタビューでは、制作チームが「世界中で遊ばれること」を想定して15言語版対応し、約500人の声優が参加していたと報じられている。英文・多言語ローカライズの壁を超えて作られたゲームである。
原作小説シリーズ(Andrzej Sapkowski)をベースにしつつも、本作は「ゲームオリジナルストーリー」として設計されており、原作未読のプレイヤーにもアクセスしやすい仕様になっていた。
マップ上の小ネタやローカル伝承(東欧・スラヴ神話)を多く取り込んでいたことも、開発者のインタビューから語られている。
例えば、民間伝承をモチーフにしたサイドクエストの数々。開発中、オープンワールドを作る際に「広すぎてやることがない」感が出てしまったため、「目と手を止める場所=興味を引くポイント(洞窟・キャンプ・眺望地点)」を意図的に配置したという話も。
第6章:体験に深みを与える音楽

この作品の音楽は、ゲーム体験の深みを大幅に引き上げており、“なぜこの音楽が印象的なのか”を深掘り。
作曲陣・関わったアーティスト
- 主な作曲家は Marcin Przybyłowicz(ポーランド)で、本作の音楽監督でもある。
- 更に Mikołaj Stroinski が共作・追加作曲を担当。
- また、フォークバンド Percival Schuttenbach(通称「Percival」)が伝統楽器・民謡的な要素で音楽制作に寄与している。
- サウンドトラックは、オリジナルゲーム+拡張(「Hearts of Stone」「Blood and Wine」)を通じて複数枚出ており、35曲・約81分のオリジナル盤がベースである。

ちなみに筆者はサントラを所持しています、、、。Spotifyなどでも配信されているので、本作が好きな方は聴き込んでみてはいかが??
スタイル・特徴・こだわり
制作当初から、開発スタジオは「スラヴ風・東欧伝承風の音楽」を意図していたとのインタビューがある。その地域特有の音楽性のことで、悲しく美しいメロディラインが特徴。
Percival(前述) が持つ古楽器(リュート、ルネサンスヴァイオリンなど)を録音に使い、「中世感・土着感」を演出。(劇中で女歌手がリュートを弾き語りするシーンが印象的)
オーケストラ録音も行われており、例えばドイツ・フランクフルト近郊のブランデンブルク州立オーケストラが演奏に参加している。
音の演出では「馬で荒野を駆ける時」「怪物との戦闘時」「静かな村・森の中」など、シーンによって音楽のテンポ・色彩・楽器編成が変わるため、プレイヤーの没入を強めている。
また、音響・サウンドデザイン面でも「目を閉じても何が起きているかわかるように」という意図を持っており、音楽・効果音が密接に連携している。
代表トラックとその使われ方
以下は音楽を紹介する際に挙げやすいトラックと、その場面・印象。
- “The Trail”(Marcin Przybyłowicz)
- オープニングや旅立ちシーンに相応しい、風を感じさせるメロディ。
- “Silver for Monsters…”(Percival & Marcin Przybyłowicz)
- 怪物討伐時や緊張感ある戦闘前に使われやすい。
- “Ladies of the Woods”(Percival & Marcin Przybyłowicz)
- ダークファンタジーらしい森・妖精/呪いの雰囲気を醸す。
- “Kaer Morhen”
- ウィッチャーの聖地・帰還のテーマとして、感情的な場面での効果が高い。
制作/収録裏話
- Percival のメンバーは多くが正式な音楽教育を受けておらず、録音中は「即興的な演奏」も多かったという。これが偶然にも生の民俗音楽感を生んだと言われている。
- 録音時には「戦場の音」(歩く群衆、鉄の響き、矢の軋み)なども別途収録され、音楽と環境音が密接に設計されているを
- 本作のコンサート「The Witcher in Concert」も世界各地で実施され、ゲームサウンドトラックが「ライブ体験」できるレベルであることも示しています。 (ガチで行ってみたい、、、)
ゲームをプレイする時、ヘッドホン・良音質で一度音楽に耳を傾けてみると、楽しさが倍増するかも、、、?
第7章:売上データから見る人気

発売から約10年経った2025年時点で、全世界で 6,000万本以上を販売したと発表されている。
同時に、収益(売上金額)としてはポーランドのスタジオ CD Projekt RED の報告で 約6億4,200万ドル(USD)=約2.4 十億ズウォティ(ポーランド通貨) を生み出しているとされている。
具体的には「PLN 2.4 billion(ズウォティ)=USD 642.3 million」などの報告がある。
初動データとして、発売から2週間で世界売上が 400万本以上 に達したという報告もある。
ストーリーや世界観が少し暗くて荒廃的であり、グロテスク要素もある中でこの売上は、筆者的に相当すごいと感じる。
- 「時間をかけて売れ続けてきた」作品
- 60 百万本という数字は一発ドカンではなく、長期にわたって積み上げてきた売上です。発売直後の勢いもあるが、ドラマ化・次世代機移植・各種セールなどが後押ししている。
- 価格戦略とプロモーションの影響
- 収益が6億4千万ドル程度という報告がある中で、本数60 million本ならば“一本あたりの平均売価”や“値下げ・セールの影響”がかなり大きかったと推察できる。
- 例えば廉価版・Complete Edition・移植版などが売上を持続させている。
- ブランド力の向上・シリーズ全体の効果
- 本作(第3作)がシリーズの中でも突出しており、売上の核となっている。シリーズ全体で見れば75 million本以上という報告もある。 つまり、ウィッチャーというブランドがゲーム以外(ドラマ・グッズ・スピンオフ等)でも認知を高め、相互に売上を支えている構図が見える。
- 移植・次世代機対応の寄与
- PS4/Xbox One/PC版に加えて、Nintendo Switch/PS5/Xbox Series版(またアップデート版)が出ており、これによって新たなプラットフォームでの販売も加速した。これが累積売上を伸ばす要因の一つである。
- セールや配信メディアの波及効果
- 例えば、ドラマ版がヒットしたことでゲーム売上が大きく跳ね上がったという報道もある。ゲームとメディア展開の相乗効果も大きい。
第8章:面白?エピソード
秘密のイースターエッグ:メッセージ「CDPR Needs You」
プレイヤーが通常のルートを外れ、マップ外や隠し空間へ進入すると、なんと開発会社 CD PROJEKT RED の社名入りメッセージ “CDPR Needs You” が壁に描かれている場所があることを発見したファンがいる。
このメッセージは「バグなどでマップ外に出るテスター向けおふざけメッセージだったのでは?」という憶測もあり、RPGの大作でこういう遊び場を用意していたという点が、開発側のユーモアやファン愛を感じさせる。

映画・物語・文化への豊富な引用・オマージュ
このゲームには映画・文学・神話・伝承など多くのリファレンス・イースターエッグが散りばめられている。
- Game of Thrones の「スカイセル(壁のない監獄)」構造を模した牢屋がある。
- Monty Python and the Holy Grail のウサギ伝説(殺戮ウサギ)がゲーム内に実装されている。
- 「牛を殺し過ぎると“牛の軍隊”が出る」という冗談めいたアップデートがあったという話も(フランス語ウィキソース/ファン検証)
クエスト「血の男爵(The Bloody Baron)」の深み
サイドクエスト「Family Matters」(通称「血の男爵」)は、本作でも特に高く評価されているエピソードである。
- 単なる魔物を倒すではなく、家族・過ち・赦し・結果というテーマを扱っており、プレイヤーが感情移入しやすく、ストーリーとしても強烈。
- デザイン側でも、「テンションの波(物語の起伏)」「戦闘・選択・心理描写」のバランスを綿密に設計した」と語られている。
サイドクエスト1つに対してもここまでこだわって作っていることに脱帽、、、。
未だ発見される秘密と長寿タイトルとしての証
発売からかなり時間が経った今も、プレイヤーが「これまだ見つけてなかった!」という隠し要素を発見し続けているという報告がある。
「十数年経っても発見される…」という事実自体が、ゲームの深さ・こだわりを物語っており、長寿作品としての証明でもある。
最後に
ウィッチャーの旅には終わりがあっても、物語の余韻は消えない。
荒野を駆けた風、焚き火の匂い、戦いの足音、そしてシリを想うゲラルトの静かな横顔。
この世界は、電源を切ったあともあなたの心のどこかで生き続けている。
もしまだ旅をしていないなら、PS4のコントローラーを手に取り、白狼の背中を追ってみて欲しい。(ガチでオススメだから)
そして、すでに旅を終えた人は――また「ローチ!!」と呼んで、あの風の中へ帰ろう!