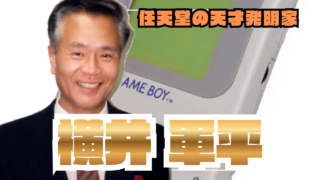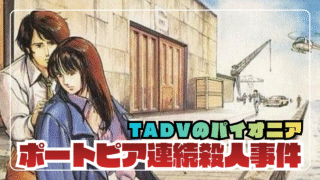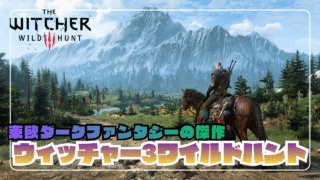1990年代後半。この頃の携帯ゲーム市場は「百数十種類のモンスターが織りなすゲームブーム」の真っ只中だった。
そのキッカケを作ったのが、皆んなもご存知『ポケットモンスター赤・緑』である。151種類のポケモンを集めるという要素が全世代のユーザーに刺さり、空前のブームが巻き起こり、社会現象にもなった。
そんなブームの中、1998年9月、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』(以下「テリワン」)が発売。
ドラクエシリーズに登場するモンスター(魔物)を仲間にし、配合して新たなモンスターを生み出す、、、そんな仲間モンスターシステム×競走馬育成を掛け合わせたような斬新なシステムが大受けした。
スライムとドラキーを配合したらよく分からない生物が生まれ、せっかく愛情込めて育てたモンスターは「親としての役目を終えました」と静かに消えていく…。そんな哀愁を感じながらもワクワクする今作は大ヒットを飛ばすこととなる。
この記事では、そんなドラクエの新たな歴史を作った『テリーのワンダーランド』について徹底的に解説して行こうと思う。
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』とは?

- 発売日:1998年9月25日
- 開発:トーセ(TOSE)
- 発売:エニックス(Enix)
- ジャンル:ロールプレイングゲーム(RPG)
- プラットフォーム:ゲームボーイ/ゲームボーイカラー/Nintendo Switch
- シリーズ:ドラゴンクエストモンスターズシリーズ(DQM)
第1章:ストーリー「テリワン」って何?

主人公はテリー。本作は実は『ドラゴンクエストVI 幻の大地』の登場キャラクターであるテリーと妹ミレーユの子ども時代とされており、作品世界としては「ドラクエ6の少し前・番外編的な物語」とされている。(ゲーム史上屈指の美男美女姉弟だよね、、、🤤)
以降、ジョーカーシリーズを除いてDQMシリーズはメインシリーズのパーティキャラクターや的キャラクターが主人公として採用されている。(これがまた良いんだよな、、、)
ある夜、テリーとミレーユは自宅(あるいは幼少期の部屋)で平穏な時間を過ごしていた。しかしその夜、その平穏は突如として破られる。物語冒頭、ミレーユが何者かのモンスターにさらわれるという事件が起こる。
ミレーユが連れ去られたあと、テリーは混乱し、どうすべきか分からない状況になる。そこで、もう1体の導きのモンスターが現れ、テリーを別世界・異国の地である『タイジュの国』へと誘う。
テリーはこの新たな場所で、王様と出会い、この国にモンスター育成し、大会で競わせる『星降りの大会』の出場を提案される。王様曰く「この国では、モンスター大会で優勝すれば“願いが叶う”」という伝承があるというのだ。
テリーは、ミレーユを救うため、家に戻るため・姉と一緒にいたいという思いを胸に、このモンスター育成・大会挑戦の旅を決意する。
筆者だったら、絶望のあまり、タイジュのすみっこで膝を抱えたべそかいてると思う。
第2章:ゲームシステム「遊びこみと中毒性の根源」

基本のゲーム構成
本作は、冒険・育成RPGというよりは「モンスターを仲間にし育て、配合し、トーナメントで競う」ことを主軸に据えた育成ゲーム型RPGと位置づけられる。
メインシリーズのようにストーリーはそこまで濃くなく、一方でゲームシステムが濃厚に仕上がっている。
プレイヤーは主人公テリーを操作するが、実際の戦闘ではモンスターが戦う形で進行する。(テリーは指示役)
簡潔に言うと、本作の構造は以下のようになる。
- フィールド・ダンジョン探索 → モンスターとの出会い・戦闘 → 仲間化・育成
- 育てたモンスターの「配合」による上位モンスター生成
- トーナメントなどの区切りを通じた達成目標(大会優勝)
- 図鑑コレクション・やり込み(+値・隠しボス等)
この構造が「モンスター育成ゲームとしての遊びのループ」を確立しており、育成好きプレイヤーを惹きつけることに成功している。
「プレイヤーキャラが戦わず、モンスターを育てて戦わせる」という点は、以降のドラゴンクエストモンスターズシリーズ共通した特徴である。
また、ゲームボーイカラーという当時の携帯ゲームハードとしての制約を逆手にとり、「育成と配合という“じっくり遊ぶ”要素」にフォーカスされている点も興味深い。
モンスター仲間化・育成・ステータス・レベルアップ
モンスターを仲間にする
本作では、野生のモンスターをただバトルで倒すだけでなく、「仲間にする」というプロセスが重要。例えば、戦闘中に『肉(しもふりにく等)🍖』を与えてモンスターを懐かせると、戦闘終了時に仲間として申し出てくる場合がある。要するに餌付けして仲間にするのである。
この「肉を与えることで仲間化を促す」システムは、いわゆるポケモン風の「捕まえる」ではなく、「交渉・説得・条件」が絡む点で少し異なり、育成ゲームとしての丁寧さを感じられる。
さらに、全モンスターが確実に仲間になるわけではなく、条件・確率・タイミングなどが絡んでおり、仲間化そのものが育成要素の一部になっている。
レベルアップ・経験値・ステータス
仲間にしたモンスターは戦闘を重ね経験値を獲得、レベルが上がることでステータス(攻撃・防御・素早さ・賢さなど)が上昇する。
ただし、単にレベルを上げれば勝てるわけではない。例えば、モンスターごとに「成長限界レベル」が設定されていたり、ステータスの伸びに差があったりする。
さらに、「+(プラス)値」と呼ばれる隠しステータス補正もあり、高プラス値モンスターは育成の後期において大きな意味を持つ。
このように、レベル上げ=すれば終わり、ではなく、育成の質を問う構造になっており、プレイヤーに「どう育てるか」「どれを育てるか」という戦略を与えてくれる。
図鑑・コレクションの要素
モンスターを仲間にしたり、配合して新モンスターを生み出したりする中で、図書館にあるモンスター図鑑に登録されていくというコレクション性も存在する。
例えば、野生で出現するモンスター、配合専用モンスター、扉ダンジョンでしか出ないモンスターなどが存在し、「全モンスターを集める」という目標が長期的なモチベーションになる。
また、通常エリアとは別に「扉ダンジョン」や「隠しゲート」といった探索ルートも用意されており、そこをクリア・仲間化することで図鑑コンプ・強育成を目指す展開になる。
後述するが、これは「育てたモンスターを使って新たなモンスターを探す探求」に繋がる構造である。
モンスター配合システム

本作で最も特徴的かつ魅力的な仕組みが モンスター配合である。中毒性が高すぎて、「気が付いたら徹夜していた、、、☀️」なんてこともザラ。
単にモンスターを仲間にして強くするだけではなく、既存のモンスター同士を「♂+♀」で組み合わせて新たなモンスターを産ませるという、まさに「育成の次の次元」が用意されている。
配合の基本ルール
- レベル条件
- 通常、親となるモンスターはレベル10に到達していないと配合ができない制約がある。(これが地味にめんどくさい!)
- 性別条件
- ♂1体+♀1体で配合を行う点が基本となっている。
- 親となったモンスターは配合後 「どこかへ消えて」代わりにタマゴが1つ生まれ、そこで新モンスターが誕生する形式。
- 要するに2匹を消費し、新たなモンスターを1匹が誕生するってこと。
- 引き継ぎ要素
- 新たに誕生したモンスターは、親の「特技」「能力」「+値」の一部を継承することができる。
- つまり、どの親を配合に使うか、誰を犠牲にするかが戦略上非常に重要。
- 配合専用モンスターの存在
- 親同士の特定の組み合わせ(特殊配合)でしか出現しないモンスターも存在するため、配合は育成のゴールとも言える。
- 強モンスターはほぼ全てが特殊配合でしか生み出すことができない。
配合の戦略的意義
この配合システムがなぜ育成ゲームとして深みがあると評価されているか、以下のポイントがある。
- 犠牲と見返り
- 親となるモンスターが消えてしまうため、「このモンスターを使っていいか?」「この特技を持つ親を使っていいか?」という選択が生まれる。単に数を増やせばいいわけではないのだ。
- +値・特技継承の追求
- 例えば「プラス値 +10 のモンスターを作り、それを親にして+20を……」という目標を持つプレイヤーも多く、やり込み要素として機能します。
- +値が高ければ要求経験値が変わる」などの話をよく聞くけど、あまり変化を感じたことはなお。
- 多世代育成の楽しみ
- レベル上限・成長曲線・系統差などを踏まえた上で、親→子→孫のような世代交代育成を行うことで、長時間・段階的に遊べるようになっている。
- 他者との通信配合(当時仕様)
- 本作では通信ケーブルを用いて他プレイヤーのモンスターとお見合い配合できる要素もあり、他人との協力・交流が育成に影響を及ぼす点で新鮮だった。
- 筆者が子供の頃、友達とお互いにパオームを1体ずつ作って持ち寄り、お見合いをしてお互いにキングレオをゲットといったことをしていた。マジで楽しかった、、、
配合で見えてくる“やり込み”構造
配合はただ「新しいモンスターを作る」ためだけでなく、以下のような要素をも孕んでいる。
- レア・強モンスター生成
- 配合専用モンスターや隠しモンスターはいずれも強力であり、育成の一つの到達点となる。
- 配合レシピの探索
- 親の組み合わせによって子のモンスターが変化するため、最適な配合レシピを探る“収集・解析”的楽しみがある。
- 筆者が子供の頃は、発見した配合方法をノートにイラスト付きで書き残したりして遊んでいました。あの頃に戻りたい。
- +値+特技+能力の最適化
- 単に強く育てるだけでなく、「どの親を使うとこの特技が継承されるか」「攻撃力400以上+レベル33でギガスラッシュを覚えるかどうか」など、育成の細かい目標が生まれた。
- 育成ループの構築
- 配合→育成→戦闘→次の配合というサイクルを何度も回す設計が「辞めどきが分からない」育成中毒性を生んでいる。
探索・ダンジョン・扉システム
本作の舞台構造も非常に特徴的であり、探索と育成を繋ぐ重要な歯車になっている。
旅の扉システム
プレイヤーがテリーの拠点であるタイジュの国(およびその周辺)から、各地のモンスターやアイテムを探索できる「旅の扉」を通じて異世界へ旅立つという構造が取られている。
これら扉は以下のような特徴を持ちます。
- 各ゲートはランダムに生成された複数の階層(フロア)で構成されており、最奥にボスモンスターが待っている。ボスを倒すとそのゲートは「制覇済み」となり、次のゲート開放に繋がる。
- 一部のゲートは「隠しゲート」として、ゲーム本編クリア後や特定条件クリア後に出現。育成好きプレイヤー向けの高難度が用意されている。
- ゲート内では複数の部屋タイプ(ショップルーム、教会(回復)、宝箱ルーム、迷路ルーム、通常戦闘フロアなど)がランダム要素を含んで配置されており、「どこに何があるか」を探索する楽しみもある。
フィールド・戦闘までの導線
テリーはまず王国にてモンスターを仲間にし育成し、次に旅の扉に挑みボスを倒して(時には仲間にして戦力を補強し)大会参加資格を得る、という流れになっている。
育成・配合→戦闘(ゲート)→トーナメントが三段階の進行軸とも言える。
探索中、モンスターとのランダムエンカウントや特定モンスターマスター戦が起こり、レベルアップ・アイテム獲得・モンスター仲間化の機会が生まれる。
収集アイテム(ちいさなメダル等)の配置もあるため、ただ戦って進むだけでなく、探す・拾う・集めるという要素も強く感じられる。メダル集めは中々の苦行……
トーナメント・ランク戦
ストーリー的には、テリーは「モンスター格闘場」に出場し優勝を目指す。
旅の扉をクリアし、モンスターを育て、トーナメント出場資格を得るという区切りが設けられており、ゲームとして育成の目的が明確になっている。
さらに、「ランク G → D → C → B → A → S」などのクラス制が存在し、最終的にSランクに到達することで『星降りの大会』への出場権が得られる。
また、各ランクへ昇格する度に王様が新たな旅の扉を開放してくれる。
戦闘システム・モンスター編成
パーティ編成・戦闘の流れ
本作では、プレイヤーが直接攻撃を行うのではなく、モンスターを3体編成して戦う方式。
戦闘はターン制で、味方モンスターが行動→敵モンスターが行動、という流れ。プレイヤーは「指示(コマンド)を出す」または「AI任せの指示設定」(ガンガンいこうぜ等)を選ぶことができる。
また、戦闘中に「肉」をぶん投げて、敵を仲間に誘うフェーズもあるため、戦略・駆け引きが発生する。
ただし、プレイヤーが完全に戦闘に干渉しないわけではなく、戦闘中にアイテムを使って、相手にダメージを与える・味方を回復したりと援助することができる。(杖や賢者の石など)
第3章:開発秘話

シリーズ発想の起点:「配合」「モンスター育成」への転換
まず、「なぜ『モンスターを育てて戦わせる』という形式を採ったか」という根っこの部分から。
本作のプロデューサーである 犬塚太一 さんらが語るところによれば、そもそも 『モンスターを配合するゲーム』という発想がまずあり、「配合」という言葉・概念が先に出ていたという。
任天堂のインタビュー「社長が訊く」の中でも、「“配合”って単語が先にあって、最終的にゲームになっていきました」 と明言されている。
その「配合」の発想がどこから来たかというと、競馬(血統・種付け)のシステムがヒントになったという話がある。インタビューで「当時、千田幸信さん(初代プロデューサー)が競馬好きで、“モンスターで血統的な配合をゲームにできないか”という話があった」 と語られている。
つまり、「捕まえて育てる」だけではなく、「親・子・世代交代」「能力継承」「配合という戦略的な設計」という要素を核として据えることで、単なるレベル上げRPGとは違う体験を志向していた。
また、当時のゲーム市場としては、1996年に発売された『ポケットモンスター赤・緑』の「モンスター収集・育成・対戦」ブームが大きくあり、本作もその文脈を受けながら「ドラゴンクエストのモンスターを使った育成ゲーム」を作るという意図が明らかになっている。
このように、テリワンは「配合による育成ゲーム」という明確なコンセプト(モンスター収集+親子配合+育成戦略)を、ドラゴンクエストの世界観に載せて企画された作品という位置づけができる。
キャラクター・シリーズとの関係性設計
次に、「なぜ主人公がテリーで、なぜモンスターズとして外伝化されたか」という点。
インタビューにて、堀井雄二さんが「主人公をどうしようかという話になって、すでに本編で出ていたキャラクターの中からテリーの少年期がいいんじゃないか」という案が出たと語っている。
具体的には、『ドラクエ6』で登場する青年・テリー(および姉ミレーユ)を、少し前の外伝設定で用い、「テリーがモンスターマスターになる物語」という枠組みに決定されたようだ。
堀井さんが「テリーのデザインは本来『DQ6』の主人公として用意されていたものだが、主人公として使うには個性が強かったため、別キャラクターにしようということでテリーとして使わせてもらった」という話も語っている。
また、シリーズとして「ドラゴンクエストモンスターズ(DQM)シリーズ」を立ち上げるために、この第一作を 入り口の分かりやすい外伝に位置づけたという意図も読み取れる。
つまり、「モンスターを主体にした遊びをドラクエ世界で再構築する」というチャレンジが、このテリワンで始まったのだ。
なお、開発はトーセが担当しており、本編ドラクエの主要開発とは別ラインでスピンオフを展開する体制が取られていた。
ハード・開発時代背景と制約
テリワンが登場した1998年という時代・ハード環境も、開発の方向性に少なからず影響を与えている。
対応ハードはゲームボーイカラー用(ゲームボーイ本体でも動作)という仕様で、当時携帯機としては制約が多い中で、育成・配合・通信という要素を詰め込む必要があった。
「社長が訊く」のインタビューでも、「間口は広く、奥行きは深く」という設計方針が挙げられている。携帯機ユーザー(子ども含む)にも入りやすく、しかし育成好き・コレクター好きにも深く遊べる設計を目指したという話がある。
また、通信ケーブルによる他プレイヤーとのモンスター交換・配合など、携帯機ながら持ち寄り・交流要素を取り入れた点も当時としては先進的。これも育成を長く楽しませる設計の一環であったと分析できる。
ただし、ハードの制約から演出・シーン数・ムービーなどは非常に抑えられており、育成システム・ループ設計に注力されたという側面がある。記事でも「グラフィック・演出は控えめだが、育成・配合という深みが本作の強み」 と振り返っている。
要するに、「携帯機向け」「子どもにも遊びやすく」「しかし育成の深みがある」──この三脚柱が開発時の設計テーマであったと考えられる。
育成・配合システム実装の舞台裏
もう少し踏み込んで、育成・配合システムがどう企画・実装されたかの秘話を綴っていく。
先に述べたように、「配合」というアイデア自体が先行しており、これをどうゲームシステムとして落とし込むかが開発陣の大きなチャレンジであったようだ。
血統・親子継承という要素をどう「ゲーム」として楽しませるか、という設計が重要だったのだ。
親が消えて卵が生まれるという形式、能力の一部継承・特技継承・+値という隠しステータスの概念、さらには通信による配合という拡張要素などは、当時の育成ゲームの中でもかなり凝った設計だったと言える。
更に、設計段階において「どれだけモンスターを仲間にできるか」「どれだけ配合レシピを用意するか」「どれだけ多くのモンスターを図鑑に収められるか」という量も重要視されていたとされ、結果的に215種類という数が実現されている。(「ポケモンの151種類を超える」をテーマにしていたのではなかろうか)
ただし、多さを詰め込むことにはハード制約・データ制約が伴ったため、「仲間化の条件」「野生度・従順度」「+値」という隠し要素を加えることで、プレイヤーが育て方・選び方という戦略を楽しめる仕掛けを加えていた。
前出記事でも「モンスター集め+配合という構造がポケモンフォロワーと差別化された要因」 と振り返られています。 また、「大会」「扉ダンジョン」といった育成ループ外の仕掛けも、育成を遊び続けさせるための構造として設計段階で意図されていたようだ。インタビューに「お祭りソフト」「間口は広く、奥行きは深く」という言葉が出ている。
シリーズ化・外伝化という視野と契機
テリワンは単に一作完結ではなく、後にシリーズとして展開されるための「試金石」とされていたという点も興味深い。
『社長が訊く』のインタビューでは、犬塚氏が「このシリーズは毎年、春に出して夏に大会予選、秋に決勝を東京ゲームショウでやる流れを繰り返したいと考えていた」という構想が示されたという。
テリワンは「モンスターズ」というブランドを確立するための出発点であり、モンスター育成系RPGという領域におけるドラクエブランドの“新たな柱”として位置づけられていたのだ。
さらに、モンスターズシリーズ自体が「ドラクエ本編とは別の体験」「モンスターとトレーナーの関係」「育成・収集・対戦」という新しいゲームプレイを模索する場であったことも、開発当時の関係者のコメントから窺える。
インタビューでも「ドラクエらしさは言葉にできない」という言葉とともに「モンスターによる自由な遊びを作りたかった」という志向が語られている。
苦労・制約・企画上の選択
開発時には、企画・技術・マーケティングの面で様々な制約や選択があった模様。
携帯機(ゲームボーイカラー)というハード仕様により、マップの広さ・グラフィック・演出・音声などが限られていたため、「繰り返し遊べる育成ループ」に重点が置かれていたという分析がある。例えば、「グラフィックやムービーは控えめだが、育成・配合・収集で長く遊べる設計」だったという振り返りがある。
モンスターのバランス、配合レシピ設計、通信機能(リンクケーブル)実装、トーナメント・ダンジョン設計など、多岐にわたる遊び要素を一本の携帯ゲームにまとめるという点で、時間・人員・スケジュール管理にも苦労があったと推測される。
特にインタビューでは「お祭りソフト」という言葉で“手軽さ+深み”を両立させるための企画意識が語られています。
第4章:音楽「担当はもちろん”あの人”」

- 本作の音楽を担当したのは、長年に渡ってメインシリーズでおなじみの すぎやま こういち 氏。スクウェア・エニックスの作曲者プロジェクト情報において、本作『Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland』の「Composition/Arrangement」欄に、すぎやま氏の名前が記載されている。
- 本作オリジナルのBGMが数曲あるのも特徴的だが、過去シリーズのアレンジ曲も多数使用されており、懐かしさに浸ることもできる。
- すぎやま氏はドラクエシリーズ全体の音楽監督的存在であり、クラシック音楽の素養を持つ作曲家で、「ドラゴンクエスト=音楽の質」へのこだわりを常に持っていた。
- 本作では育成ゲーム・携帯機という条件もあって、フルオーケストラ録音ではなくシンセサイザー・チップチューン的な音源を用いたBGM設計がなされており、音源ハード・容量制約下での工夫が見られる。
- 例えば、『Synthesizer Suite “Dragon Quest Monsters” 〜テリーのワンダーランド〜』というアレンジCDが出ており、そこでは“シンセサイザー組曲”という言葉も使われている。筆者の友達がこのCDを持っててビックリ!😳
最後に
『テリーのワンダーランド』という作品は、ただの“懐かしいゲーム”ではなく、モンスター育成というジャンルを一段深く、そして豊かにした名作である。小さなゲームボーイの画面から広がる世界は、今振り返っても驚くほど広く、温かく、そして何よりワクワクに満ちていた。
モンスターを仲間にした瞬間の嬉しさ、配合で生まれた新しい命への期待、扉ダンジョンの奥で出会った強敵への緊張感──あのとき味わった感情は、時を経ても色褪せません。どれもが、自分だけの冒険を創り上げてくれた“宝物”のような体験だったはず。
そして今、あらためて振り返ると感じるのは、この作品は「育てる楽しさ」と「冒険する喜び」を、ひとつの物語に美しくまとめたゲームだったということ。
ハードの制約を工夫で乗り越え、モンスターたちの世界をここまで鮮やかに描いた開発陣の情熱にも、改めて敬意を抱かずにはいられない。
ぜひこの記事をきっかけに、もう一度“テリーのワンダーランド”を旅してみてほしい。
あの頃ワクワクしながら開いた旅の扉は、きっと今もあなたを待っている。
星降りの大会で願いを叶えたあの日のように、あなたの冒険がこれからも続いていきますように。