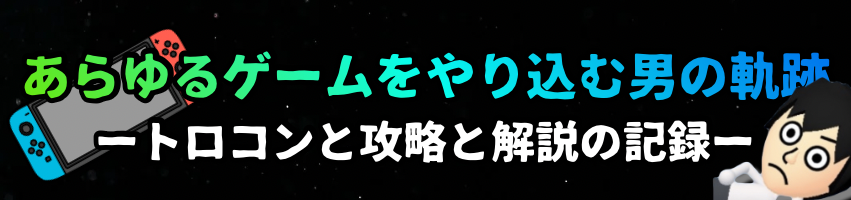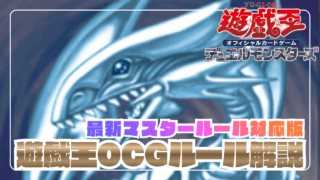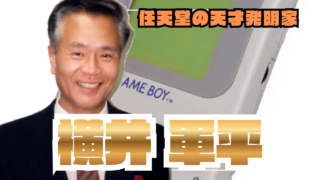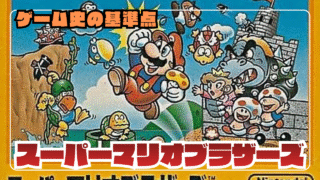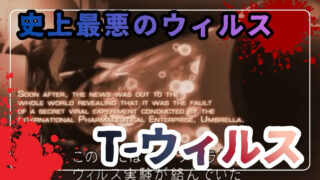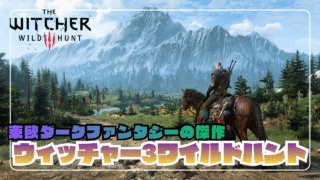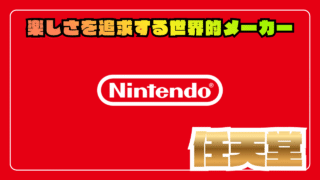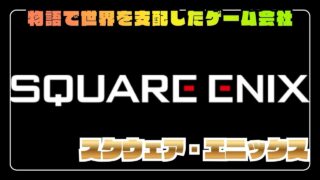1889年、京都の一角で小さな花札屋が誕生した。
職人が一枚ずつ手描きで仕上げる花札を売る、どこにでもありそうで、どこにもない。それが、後に世界のエンターテインメントを変えてしまう会社──任天堂(当時・任天堂骨牌)である。
「ファミコン」「ゲームボーイ」「スーパーマリオ」「ゼルダの伝説」「Switch」。これらは今や、世代や国境を超える文化になった。
けれど、その裏には、創業者の決断、天才たちのひらめき、そして数々の失敗と復活の物語が隠されていた。
この記事では、そんな任天堂の130年以上に及ぶ歴史を、創業の花札時代から現代のSwitchまで、一本の“物語”としてじっくり紐解いて行く。
あなたの知らない任天堂に、きっと出会えるはずだ。
時を超える任天堂物語 ~ 花札から世界的ゲーム企業へ

1889年頃の京都にあった創業当時の任天堂本店。ここから物語が始まる。
第1章『創業の背景と山内房治郎』

時は1889年(明治22年)、場所は京都・下京区。若き職人、山内房治郎が小さな花札の製造所「任天堂骨牌(こっぱい)」を創業。(100年近くも前の偉人なので写真がない…)
当時、日本では賭博取締の影響で一般的なトランプの使用が制限されており、その代替として花札が密かな人気を博していた。
房治郎は自ら手描きした花札を売り出し、このニッチ市場に勝負を挑んだのある。任天堂という社名の由来については諸説あるが、「運を天に任せる」という意味だとよく言われいる。(実際のところ真相は創業者の家族にもわからないらしい。めちゃくちゃ興味深い…)
創業当初、花札は博徒やヤクザの賭場でよく使われる遊び道具であった。他のメーカーはその悪評を恐れて市場から手を引く中、房治郎はあえて踏みとどまり、京都で花札生産のトップ企業へと登り詰める。
彼は巧みな販売戦略も打ち出した。例えば、『明治の煙草王』と呼ばれた実業家・村井吉兵衛と提携し、煙草の流通網に花札やトランプを乗せて全国へ販路を広げたのである。こうした努力により、房治郎が隠居する頃には任天堂は日本一のカードメーカーとなっていた。
房治郎の企業家魂は花札に留まらなかった。1902年(明治35年)には国内初となる洋風トランプの製造にも着手し、市場をさらに開拓して行く。家業を後継する男子がいなかった山内家では、日本の商家の習わしに従い婿養子を迎える。
房治郎の引退後は養子の山内積良(せきりょう、養女の夫)が事業を継ぎ、1929年には任天堂の2代目社長となる。かくして任天堂は、明治・大正・昭和へと時代を超えて花札・トランプ事業を続けていくのである。
第2章『花札から玩具への転換』

第二次世界大戦後、日本は高度経済成長期を迎える。それと同時に任天堂もまた新たな挑戦の時代を迎えていた。
3代目社長に就任したのは創業者の曾孫にあたる山内溥(Hiroshi Yamauchi)氏。1949年、弱冠22歳で社長に就任した山内溥は、それまで家業の花札・トランプ製造に依存していた任天堂を多角化しようと奔走する。
というのも、1950年代後半にディズニーキャラクター入りトランプをヒットさせたものの 、その後カードゲーム市場は徐々に頭打ちになっていたからです。溥は「次のキラー商品」を求めてあらゆる実験に打って出た。
1960年代、任天堂は今では想像もつかないような事業に次々と手を出す。例えば、札幌でタクシー会社『ダイヤ交通株式会社』を経営してみたり、インスタント食品(即席ライス)を販売してみたり、挙句の果てには京都でラブホテルのチェーン展開まで検討した。しかし、これらの試みはいずれも大きな成功には至らなかった。社業は迷走し、一時は「任天堂もここまでか…」と囁かれるほど業績も低迷。

山本さんが社長就任を依頼された際、山本家の身内を全て排除することを条件にしたエピソードがある。これは経営に関しての勉強にもなる話だよな。

そんな折、ひとりの若き社員が運命を変える発明をする。工場の機械整備を任されていた横井軍平氏という社員が、空き時間に廃材で面白いオモチャを作って遊んでいたのである。
そのオモチャとは、アコーディオンのように伸び縮みする『ウルトラハンド』だった。ある日それをたまたま見つけた山内溥社長は、「それを商品化せよ」と命じる。1966年に発売されたウルトラハンドは大ヒット商品となった。発売2か月で40万個を売り上げ、最終的には100万個超を販売する空前のヒットとなったのである。


ウルトラハンドの成功は沈みかけていた任天堂にとってまさに救世主だった。「花札屋」の殻を破り、玩具メーカー任天堂への転身を決定づけた瞬間だった。
「ウルトラ○○」シリーズとして翌年には『ピンポン玉発射玩具ウルトラマシン(1967年)』、『愛のテスト測定器ラブテスター(1969年)』などユニークなおもちゃを次々開発。任天堂はこの頃「面白いものなら何でも作ってみよう」という社風で、意表を突く製品を次々と世に送り出していた。

中でも1969年発売の『光線銃シリーズ』は電子玩具の走りとしてヒットし、これが後の電子ゲーム開発の布石ともなって行く。
かくして任天堂は1960年代後半から1970年代にかけて、伝統の花札事業に加えて玩具メーカーとして第二の創業期を迎えたのだった。
第3章『テレビゲームへの参入とファミコン革命』

1960年代末から70年代に入ると、世界では新たなエンターテインメントが胎動していた。そう、テレビゲームの誕生である。アメリカで『ポン』などのアーケードゲームが流行し始めると、敏感な山内溥は早速その可能性に着目する。
1970年、任天堂内に電子ゲーム専門の開発部門を設立し、横井氏ら玩具部門の人材を電子ゲーム開発に転属させた。こうして任天堂はゲームメーカーへの道を歩み始める。
最初期には試行錯誤もあった。1977年には家庭用テレビゲーム機「カラーテレビゲーム15」「カラーテレビゲーム6」を日本で発売。これは既存のゲーム(ブロック崩しなど)を遊ぶ専用機だったが、一定の人気を博した。
そして1970年代末、任天堂はアーケードゲーム産業にも参入する。いくつかゲームを出す中で、米国進出用に開発した「レーダースコープ」というゲームが思ったほど売れず、大量の在庫が北米倉庫に眠る事態となったこのピンチを救うため、任天堂米国法人(NOA)の荒川實社長は日本の山内溥に「新しいゲームを作ってほしい」と懇願する。
しかし当時任天堂の開発陣は他プロジェクトで手一杯…。そこで白羽の矢が立ったのが、開発者ではなく美術スタッフだった若者、宮本茂氏だった。
宮本茂が手がけた新ゲームは、まだ無名だった大工のマリオとゴリラのドタバタ劇――そう、「ドンキーコング」である。1981年にアーケードで登場したドンキーコングは北米で大ヒットを記録し、任天堂は一躍ゲームメーカーとして脚光を浴びる。
マリオ(当時はジャンプマンという名前だった)は任天堂の看板キャラクターとなり、宮本茂は後に“現代ビデオゲームの父”とも称されるクリエイターとして頭角を現した。
アーケードで成功を収めた任天堂は、次なる勝負の場として家庭用ゲーム機に目を向ける。1983年、日本で家庭用ゲーム機『ファミリーコンピュータ』(通称ファミコン)が発売。ファミコンは当初こそ生産不良に悩まされたが、後に品質改善し、空前の家庭用ゲームブームを巻き起こす。1985年には宮本茂の手によるキラーソフト『スーパーマリオブラザーズ』が発売され、子どもから大人まで熱中する社会現象を生む。
ファミコンの勢いは海を越え、1985年から北米や欧州でもNES(海外版ファミコン)として展開される。当時北米ではビデオゲーム市場が一度崩壊していたが、NESとマリオの登場は見事に市場を復活させる。
1989年には「米国の家庭の25%以上に任天堂のゲーム機がある」と報じられるほどの普及ぶりだったという。ファミコンは全世界で6,000万台以上を売り上げ、任天堂は80年代後半に世界的なゲーム企業としての地位を確立した。
第4章『携帯ゲームと次世代ハードの展開』

ファミコンの成功に安住することなく、任天堂は新たなゲーム体験を次々と提供していく。その一つが携帯ゲーム機という新分野だった。
話は1980年に遡るが、横井氏の発案により世界初の携帯型液晶ゲーム機「ゲーム&ウオッチ」が発売される。シンプルなゲームが遊べるカードサイズの端末は世界的ヒットとなり、任天堂は「いつでもどこでも遊べるゲーム」という市場を切り拓く。
そして1989年、横井氏のチームが開発した携帯ゲーム機「ゲームボーイ」が誕生。ゲームボーイはモノクロ画面ながらも交換式カートリッジによる多彩なゲームが魅力で、発売と同時に飛ぶように売れる。
日本では発売からわずか2週間で初回30万台が完売、北米でも発売初日に4万台が売れる滑り出しだった。さらにゲームボーイはロシア生まれのパズル「テトリス」を同梱したことも功を奏し、大人層にも普及。
結果的に全世界で1億台以上を販売する大ヒット商品となり、「携帯ゲームといえば任天堂」というブランドイメージを確立した。
一方、据置型ゲーム機の進化も続く。1990年、ファミコンの後継となる「スーパーファミコン」が発売された。スーパーファミコンは16ビットCPUによる当時最先端の美麗なグラフィックとサウンドを備え、発売当初の30万台は即日完売する人気ぶりだった。
16ビット機時代は、任天堂とセガというライバル会社との激しい競争も展開された。セガのメガドライブ(Genesis)が北米市場でシェアを奪い、「Genesis does what Nintendon’t(ジェネシスにできて任天堂にできないこと)」といった攻撃的広告を打ち出すなど熾烈なテレビゲーム戦争が繰り広げられた。
それでも任天堂はマリオやゼルダ、ドンキーコングといった強力ソフトで対抗し、結果的にスーパーファミコンは全世界累計で約4,900万台という販売台数を記録。16ビット世代の勝者の一角となった。
ところが1990年代後半、新たな強敵が出現する。かつて協業関係にあったソニー(SONY)が、自社開発の「プレイステーション」(PS、1994年発売)でゲーム市場に参入。実は任天堂はスーパーファミコン用のCD-ROMアダプタをソニーと共同開発する計画があったが、山内溥は途中で方針転換し別企業フィリップスとの提携を選んだ。
この決裂に怒ったソニーが単独で発売したのがPSであり、結果として任天堂は強力な競合相手を生むことになってしまう。PSは当時の主流メディアであったCD-ROMを活用し、サードパーティ(他社ゲーム開発会社)の支持も集めて世界的に大成功を収める。
任天堂も次世代機「NINTENDO64」(64ビット機)で巻き返しを図る。1996年に発売されたNINTENDO64は3Dポリゴン表現やアナログスティック操作など画期的な機能を備え、『スーパーマリオ64』や『ゼルダの伝説 時のオカリナ』といった名作を生み出す。
しかし記録媒体にロムカートリッジを採用したことでソフトの供給力でPSに劣り、市場シェアではPSの後塵を拝する結果となる。それでもNINTENDO64は全世界で約3,300万台を売り上げ、任天堂らしい独創的ゲーム体験(4人同時プレイの『大乱闘スマッシュブラザーズ』など)を提供し続けた。
この時期、携帯ゲーム分野でも大きな展開がありました。ゲームボーイの後継として『ゲームボーイカラー(1998年)』や高性能化した『ゲームボーイアドバンス(2001年)』が登場し、安定した人気を維持。特にゲームボーイでは1996年に生まれたロールプレイングゲーム『ポケットモンスター赤・緑』が世界的大ブームとなり、キャラクタービジネスの新たな柱に成長した。
据置機では2001年に『ニンテンドーゲームキューブ』が発売されているが、この頃にはソニーPS2や新規参入のマイクロソフトXboxなど競合も増え、ゲームキューブの販売台数は約2,200万台と前世代より苦戦を強いられた(ゲームキューブ時代には業績低迷で任天堂本社が経営危機との噂も流れた)。

ゲームボーイと言えば、やはり「バックライトがない」こと。暗い場所では画面が全く見えないので、親にバレないように夜に隠れて遊ぶのが不可能だった。
第5章『世界を魅了したキーパーソンたち』

宮本茂 :現代ゲームの父
任天堂の歩みには、常に才能あふれるキーパーソンの存在があった。その代表格がゲームデザイナーの宮本茂氏。宮本氏は入社当初アート担当でしたが、先述の通り『ドンキーコング』でゲームデザイナーとしてデビューし、以後『マリオ』『ゼルダの伝説』『スターフォックス』など数々の名作シリーズを手がけた。
その独創的なアイデアと遊び心から、彼は「現代ゲームの父」とも称されている。幼少期に京都の田舎で洞窟探検をした体験が『ゼルダ』の冒険に繋がった…というエピソードは有名で、常に遊びの本質を追求する宮本氏の姿勢は任天堂の開発精神そのものと言える。
横井軍平:任天堂の発明王
もう一人、「任天堂の発明王」と呼ぶべき人物が横井軍平氏。横井氏は玩具部門出身ながら、ウルトラハンドで会社を大ヒットに導き、その後もゲーム&ウオッチやゲームボーイといったハードを生み出した立役者である。
彼のモットーは「枯れた技術の水平思考」。最新技術に飛びつくのではなく、枯れて安価になった技術を組み合わせて新価値を生むという発想で、ゲーム&ウオッチの液晶技術やゲームボーイのモノクロ表示などを敢えて採用したという。その成果として生まれた製品はどれも大ヒットし、任天堂の土台を支えた。
1995年に立体視ゲーム機バーチャルボーイの失敗を機に横井氏は退社するが、「ゲームボーイポケット」を最後に送り出し花道を飾った後の退職だった(その翌年に交通事故で逝去)。
岩田聡:任天堂 第4代社長
また、忘れてはならないのが第4代社長の岩田聡氏。もともと任天堂のセカンドパーティ企業HAL研究所のプログラマー出身で、『星のカービィ』シリーズなどを手がけた岩田氏は、2002年に山内溥の後任として任天堂社長に就任した。
生粋の開発者がトップに立ったことで、任天堂はより「ユーザー視点」に立った経営へと舵を切る。岩田氏は社長就任直後、ゲーム市場が縮小傾向にあることに危機感を抱き「ゲーム人口の拡大」を掲げる大胆な戦略を打ち出す。これはゲームファン以外の人々にも遊びの楽しさを届けようという試みで、後述するニンテンドーDSやWiiの大成功によって見事に実現する。
岩田氏自身、「社長としてではなく開発者としてゲームに向き合う」という信条を持ち続け、任天堂ダイレクトで自らゲームを紹介するなどユーザーに親しまれる存在だった。
残念ながら2015年に病で逝去されたが、彼の遺した理念は今も任天堂経営に脈々と受け継がれている。

岩田社長が出演する「社長が訊く」は今でもYouTubeで公開されており、色々な制作秘話が聞けてとにかく面白いのでオススメ。
この他にも、初代ファミコンを設計した上村雅之氏、ゲームボーイ以降のハード技術を率いた竹田玄洋氏、Switch開発を統括した高橋伸也氏、米国任天堂を率いて現地での任天堂ファン拡大に貢献した荒川實氏やレジー・フィサメイ氏など、任天堂には数えきれないほどの重要人物が存在する。
彼らの情熱と才能が結集し、任天堂の物語は紡がれてきたと言える。
第6章:イノベーションの連続:Wii、DS、そしてSwitch

2000年代に入り、ゲーム業界はよりハイテク志向を強めていました。ソニーやマイクロソフトが高性能路線でしのぎを削る中、任天堂は逆張りともいえる戦略で挑んだ。
岩田聡社長が掲げた「ゲーム人口拡大戦略」、すなわち「これまでゲームに興味のなかった人々にも遊んでもらおう」という方針である。この理念のもと生まれたのが、ニンテンドーDS(2004年)とWii(2006年)だった。
ニンテンドーDS
ニンテンドーDSは携帯機に2画面とタッチパネルという斬新なインターフェースを導入し、子供だけでなく主婦や高齢者まで巻き込むブームを起こした。(普段ゲームをやらない筆者の母が夢中になってDSを遊びまくっていた)
脳を鍛える大人向けゲームや、通信機能を活かした友達とのお絵描きチャットなど、新しい遊び方が次々提案され、DSは全世界1億5千万台超という史上空前の売上を記録する。(これは当時歴代携帯ゲーム機の最高記録) 。岩田社長の言う「5年後に成果が出なければクビ覚悟」の戦略は、わずか1年で大成功を収めた。
Wii
続くWiiは据置型ゲーム機でありながら、従来のゲームファン以外を意識してデザインされた。最大の特徴は直感的に操作できる「Wiiリモコン」である。細長いリモコン型コントローラを振ったり傾けたりするだけで、画面の中のキャラクターが動く――この体感操作は画期的だった。
「自分にもできそう」と思わせたことで、お父さんお母さんから祖父母まで家族みんながテレビの前でゴルフスイングしたりボウリングしたりする光景が世界中で見られあ。Wii本体も全世界で1億台を超えるセールスを達成し 、任天堂は据置機市場でも復活を遂げる。まさに『ゲームで世界に笑顔を』という任天堂らしい青海戦略(ブルーオーシャン戦略)の成功例だった。
ニンテンドー3DS と Wii U
しかしイノベーションの裏にはリスクもある。DSとWiiで大成功を収めた後、後継として発売された携帯機『ニンテンドー3DS(2011年)』や据置機『Wii U(2012年)』は、前世代ほどの勢いを生み出せなかった。
特にWii Uはタブレット型コントローラによる2画面プレイという意欲作だったが、コンセプトが十分伝わらず「Wiiの周辺機器か何か?」と誤解されてしまう。ローンチ時のソフト不足やサードパーティ離れも重なり、世界販売台数はわずか約1,356万台と任天堂据置機で史上最低の成績に終わる。
任天堂自身「Wii Uは失敗だった」と認めるほどの苦境で、次期ハードの成否が社運を左右する事態となる。
Nintendo Switch
その正念場で任天堂が総力を挙げて開発したのが、2017年発売の『Nintendo Switch』。Switchは据置機としても携帯機としても使えるハイブリッドコンセプトを打ち出し、据置と携帯のラインを事実上一本化する思い切った戦略に出た。
Wii Uでの反省から、コンセプトは「いつでもどこでも誰とでも遊べる」と非常に明快で、発売と同時に『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』など強力タイトルが揃ったこともあり、スタートダッシュに成功する。
Switchの勢いは留まるところを知らず、品薄が続くほどの人気となりました。結果的にSwitchは世界累計販売台数が1億台を優に超え、任天堂史上でも有数のヒットハードに成長している。Wii Uの失敗から学んだ「分かりやすさ」と「ソフトの充実」が見事に実を結んだ形である。
Switch時代に任天堂はソフト面でも充実を極めます。『スーパーマリオ オデッセイ』『あつまれ どうぶつの森』『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』など、任天堂のオールスタータイトルが軒並み記録的ヒットを連発。
更にインディーゲームの積極的な取り込みや、他社人気ソフト(モンハンやMinecraftなど)の誘致にも成功し、プラットフォームとしての魅力を高めた。またSwitchはオンラインサービス「Nintendo Switch Online」でレトロゲーム配信や世界協力プレイといった新たな遊びも提供し、発売から数年が経った後でも高いアクティブユーザー数を維持していた。
最後に
任天堂の歴史を振り返ると、「よくこんな会社が生まれたな…!」と驚く瞬間の連続である。
花札から宇宙を救うヒゲの配管工まで飛躍しすぎだが、それがまた任天堂らしさ。
記事を書きながら、任天堂について詳しく調べながら、私自身も改めて「遊びの力ってすごい」と感じた。
もしあなたの思い出に残っている任天堂作品はなんですか?
語り合えば、それもまた一つの新しい物語になるはず。