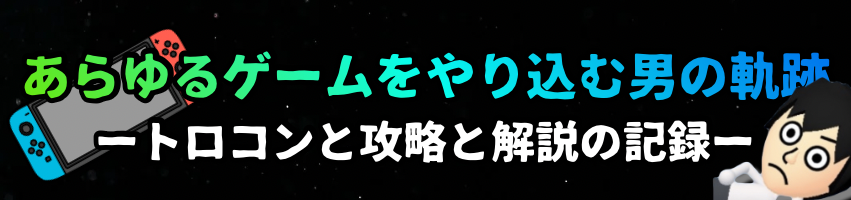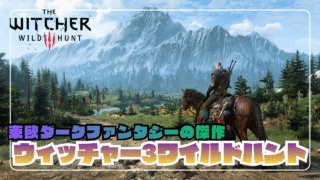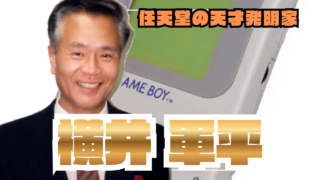バイオハザードシリーズにおけるゾンビの詳細解説
「バイオハザード」(Resident Evil)シリーズの象徴的存在である“ゾンビ”は、シリーズの恐怖と世界観を語る上で欠かせない要素である。
本稿では、ナンバリングタイトル(本編シリーズ)だけでなく、外伝作品やリメイク作品、フルCGアニメ作品におけるゾンビの描写や役割について、多角的に解説していく(実写映画は対象外)。
以下では、ゾンビ誕生の経緯から初登場シーンの衝撃、シリーズでの進化とバリエーション、ゲームプレイ上の脅威と戦術、ビジュアル面での変遷、開発者インタビューで語られた意図、CGアニメや外伝での描かれ方、他の感染者との違い、ファンやメディアの評価、そしてシリーズにおける象徴性と今後までを網羅的に考察していく。
ゾンビ誕生の経緯:T-ウィルス研究とアンブレラ社の野望

始祖ウィルスとT-ウィルス開発
バイオハザードシリーズのゾンビは、アンブレラ社という架空の巨大製薬企業が開発した生物兵器用ウィルス「T-ウィルス」によって生み出された存在である。
T-ウィルスのベースとなったのは、1960年代にアンブレラ創設メンバーの一人ジェームス・マーカス博士らがアフリカの古代遺跡で発見した「始祖ウィルス」というRNAウィルスだった。
マーカスは始祖ウィルスに様々な遺伝子操作を施し、「Tyrant(タイラント=暴君)」の頭文字を取った「T-ウィルス」と呼ばれる変異株を創造した。
当初アンブレラ社はこのT-ウィルスを“新種の薬剤”として軍事利用することを画策しており、表向きには製薬会社としての顔を保ちながら裏で違法な人体実験を重ねていた。
アンブレラ社の思惑:B.O.W.開発

アンブレラ社がT-ウィルスを開発した真の目的は、「B.O.W.(生物兵器)」と呼ばれる戦闘生物を作り出すことだった。その最終目標は、人間をウィルスで変異させて強力な兵士=タイラントを生み出し、敵対勢力に対する圧倒的戦力とすること。
実際、T-ウィルスの名称に「タイラント」の名が冠されていることからも、究極的には知能と戦闘能力を兼ね備えたタイラント級B.O.W.を製造・量産する野望があったことが窺える。
しかし、T-ウィルスは当初の想定通りには働かず、圧倒的多数の被験体(感染者)はタイラントどころか凶暴化した“ゾンビ”と化してしまう。タイラントのような高度なB.O.W.を生み出すには、生来の適性(ウィルス完全適合者)が1000万人に1人程度という極めて稀な条件が必要だったのである。その結果、ゾンビはアンブレラ社の生物兵器研究の「副産物」として大量に発生することになった。
兵器としてのゾンビ:利用価値と限界
アンブレラ社内でも、ゾンビそのものの戦闘力には当初から大きな期待は寄せられていなかった。機能停止した大脳により知能が著しく低下したゾンビは、道具や武器を使うことができず、組織的な戦力として扱うのが困難だったからである。
アンブレラの機密資料「ウェスカーズリポート2」では、T-ウィルス兵器の主目的は「敵軍をゾンビ化させ無力化する」ことであり、ゾンビ自体に敵兵を殲滅させる性能は求められていなかったとされる
。すなわち、ゾンビの役割は「自ら徘徊して敵対勢力の人間を襲い、T-ウィルス感染を広げること」にあったのである。これは、核兵器における放射能のように、ゾンビを二次的な汚染拡大の手段と位置づけた戦略だった。
もっとも、結果的にT-ウィルスの流出事故によって起きたラクーンシティ壊滅事件(後述)では、まさにアンブレラ社の目論見通りにゾンビ感染が広がり、生者が次々と屠られて市全体が死の街と化した。
T-ウィルスの拡散が引き起こす“バイオハザード(生物災害)”こそがシリーズタイトルの由来であり 、ゾンビはその惨劇の象徴とも言える。

やはり「バイオ=ゾンビ」ってイメージが強いけど、かと言って後のシリーズで安易に登場させて欲しくないよね。
初代『バイオハザード』でのゾンビ登場と演出の衝撃
洋館事件と最初のゾンビ遭遇
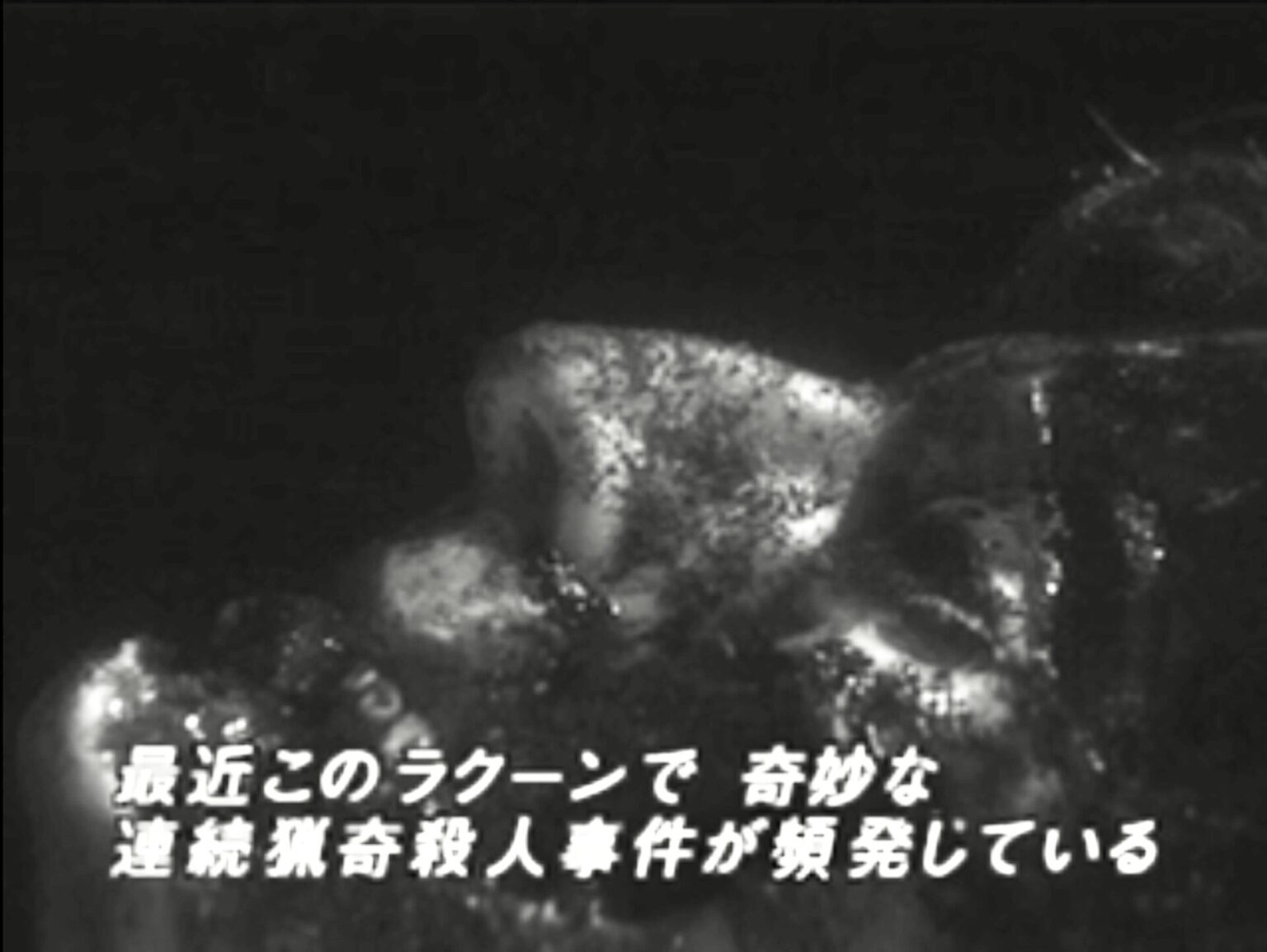
シリーズ第一作『バイオハザード』(1996年発売。日本国外版タイトルはResident Evil)の物語は、1998年7月のアークレイ山地洋館事件から始まる。
主人公たち特殊部隊S.T.A.R.S.隊員は、不気味な洋館内部で初めてゾンビと遭遇。薄暗い廊下でうずくまる人影に近づいた瞬間、ゆっくりと振り向いたその男の顔は血まみれで、人肉を喰らう“ゾンビ”だったのである。
この「振り向きゾンビ」のムービーシーンは、わずかな時間ながらゲーム史に残る強烈なインパクトを残した。
緊張感漂うオープニングから洋館探索が始まってすぐ、不意打ちのように差し込まれたこのゾンビ初遭遇シーンは、当時のプレイヤーに計り知れない衝撃と恐怖を与えたと評されている。その衝撃は「恐らくゲーム史上でも最多のプレイヤーを驚かせた場面」とも形容されるほどだった。
振り向きゾンビの犠牲者となっていたのはS.T.A.R.S.隊員のケネスであり、生ける屍と化した元同僚が人肉を貪るというショッキングな演出は物語上のインパクトも絶大だった。
開発者インタビューによれば、この最初のゾンビムービーは外部のCG制作会社に発注されたものの、当初納品されたモデルがゲーム本編と異なる禿頭の白いゾンビだったため、急遽ゲーム側でも「真っ白ハゲゾンビ」を合わせて出すなど舞台裏の苦労もあったようだ。

初代のゾンビって粗いポリゴンだけど、それでもぶっちぎりで怖かったよね。子供の頃の夢に出てきたくらいだからな…
“犬ゾンビの奇襲とサバイバルホラーの確率”

初代『バイオハザード』でもう一つ特筆すべきは、「ゾンビ犬」ことケルベロスによる有名な奇襲シーンだろう。
ゲーム序盤、何の変哲もない静かな廊下を歩いていると、窓ガラスを「ガシャーン!」という音とともに皮膚のただれた狂犬が突き破って飛び込んで来る。
この犬型ゾンビの登場シーンは、振り向きゾンビに次ぐ初代の最恐トラウマ演出として知られ、多くのプレイヤーが思わずコントローラーを手放しそうになった瞬間だった。
電撃オンラインの解説によれば、この場面の恐ろしさは音響面の工夫にも支えられており、BGMをあえて流さず環境音のみで静寂を演出した中でガラス破壊音が響くことで心拍数を跳ね上げる効果を上げていたとされている。
ケルベロスとの遭遇は、洋館に逃げ込む直前にも入口で群れに襲われる形で描かれており 、プレイヤーは開始早々に逃げ場の無い恐怖を味わうことになる。
初代のゾンビ演出が与えた衝撃と恐怖感は20年以上経った現在でも語り草となっており、公式企画でも「ゲーム史に残る名シーン」として振り向きゾンビや犬ゾンビの登場がしばしば取り上げられている。
このように、ゾンビはシリーズ開始当初からプレイヤーに強烈な印象を植え付け、バイオハザード=ゾンビというイメージを確立した。
シリーズにおけるゾンビの進化と多様なバリエーション
初代以降、バイオハザードシリーズは多数の続編・派生作品が制作され、それぞれに特徴的なゾンビや派生クリーチャーが登場した。
ゾンビ犬やクリムゾン・ヘッドなどのバリエーション、そして作品ごとの表現の進化について、主な例を挙げつつ解説する。
ラクーンシティと大量発生する都市型ゾンビ(『2』『3』)

1998年9月のラクーンシティ事件を描いた『バイオハザード2』と『3 LAST ESCAPE』では、郊外の洋館に留まっていたバイオハザードが市街地へと拡大し、大量のゾンビが街を埋め尽くした。
『2』では大勢のゾンビが警察署を含む街中で主人公に襲いかかり、特にガラス窓を突き破って侵入するシーンや狭い通路で群がるシーンなど、前作以上に多数のゾンビによる包囲の恐怖が演出されている。
舞台が洋館から市街へ移ったことで、警官や市民など様々な衣装・職業のゾンビが登場し、ビジュアル面でもバリエーションが増えた。例えば、ラクーン市警の制服警官ゾンビや、市民服ゾンビなどはシリーズの中でも象徴的なデザインとしてファンの記憶に残っている(海外ファンから「RE2の警官ゾンビは最も象徴的だ」という声もあるほど)。

また、『2』ではゾンビからさらなる突然変異を遂げた新種クリーチャー「リッカー」が登場した。リッカーは全身の皮膚が剥がれて脳と筋繊維が露出し、鋭い爪と長い舌を持つ四足歩行の怪物。
公式設定では、「多数の人間を捕食し栄養を蓄えた一部のゾンビが変異したもの」と説明されており 、ゾンビ→リッカーへの進化はT-ウィルスの二次変異の一例とされている。
目が退化して盲目となった代わりに聴覚が発達しており、生存者の足音に反応して忍び寄る演出は、ゾンビとは異なる新たな恐怖を生み出した。
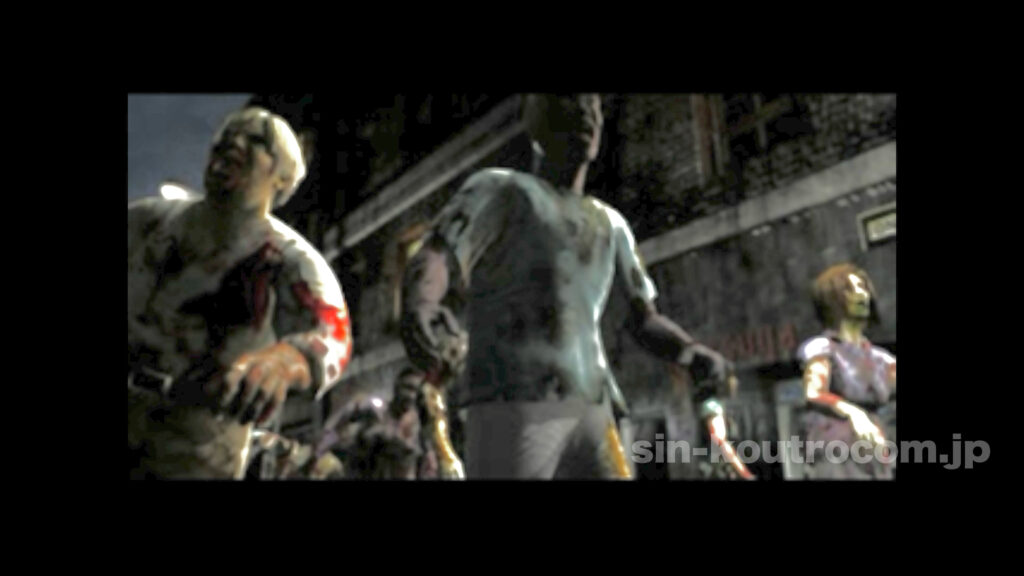
『バイオハザード3 LAST ESCAPE』では、時系列的には『2』と同時期のラクーンシティを舞台に、ジル・バレンタインが大量のゾンビからの脱出を図る。
『3』は追跡者(ネメシス)に追われ続ける恐怖がフィーチャーされているが、同時にランダム要素で配置が変化する無数のゾンビが登場し、油断を誘って来る。
前作までのゾンビに比べ、『3』のゾンビは動きがやや素早くなり、倒れたふりから奇襲するなどトリッキーな行動も見せるようになった。
また、一部のゾンビは硫酸など特殊な攻撃で上半身だけになっても這い寄ってくるなど、しぶとさも向上している。
特筆すべきは、『2』には主人公ジル・バレンタインの元戦友であるブラッド・ヴィッカーズ隊員がゾンビ化して登場する場面があること。ブラッドは『1』から登場するS.T.A.R.S.隊員で、ラクーンシティでネメシスに惨殺された後にT-ウィルスへ感染し、蘇った姿で警察署前に現れる。
知人キャラクターがゾンビ化して現れる演出はシリーズで繰り返し用いられるようになり、『CODE: Veronica』でも主人公スティーブの父親がゾンビ化して襲い掛かるなど、ドラマ性を深める役割を担った。
新たな驚異:クリムゾン・ヘッド(リメイク版)

2002年にゲームキューブ向けに発売されたリメイク版『バイオハザード』(通称「無印リメイク」または『RE:1』)では、グラフィック表現や演出の刷新に伴い、新種のゾンビ変異体「クリムゾン・ヘッド(紅頭)」が導入された。
クリムゾン・ヘッドとは、一度倒された通常ゾンビの死体が一定時間経過後に再活性化し、さらに凶暴化・高速化した個体を指す。
その名の通り体色は赤黒く変色し、長く鋭い爪を持って俊敏に走り回るため、従来の「遅いゾンビ」の定石が通用しない。クリムゾン・ヘッド化現象(作中では「V-ACT」現象と呼称)により蘇ったゾンビは、自身の邪魔になる他の通常ゾンビを殴り倒すほどの凶暴さでプレイヤーに襲いかかる。
開発スタッフは、初代を知り尽くしたプレイヤーほど驚かせるためにこの新要素を導入したとされている。実際、リメイク版『biohazard』はホラーゲームとして可能性を極限まで追求した作品と評価され、初代を遊んだことがある人ほど引っかかる巧妙な仕掛けが施されていると評論家も称賛している。
プレイヤーはゾンビを倒すだけでは安心できず、「頭部を破壊するか焼却しなければ再び蘇る」という新たな緊張を強いられた。これは死体の処理というリソース管理要素を生み、限られた燃料でどのゾンビを焼却するか戦略的判断が求められる独自のゲーム性にも繋がった。
リメイク版ではクリムゾン・ヘッドの元祖となった特異個体「クリムゾン・ヘッド・プロトタイプ1」も登場する。洋館地下墓地に封印されていたこの個体は、世界で初めてV-ACT変異が確認された記録上の第一号ゾンビであり、通常のクリムゾン・ヘッド以上に手強い存在だった。
プレイヤーはキーアイテム入手のためにこのプロトタイプを倒す必要があり、当時多くのプレイヤーがその猛攻に肝を冷やしたものである。

このクリムゾンヘッドは個人的にシリーズで最もビビった要素だった。「銃で倒したのに死体が消えないっていう違和感」を感じてたけど、まさか復活するとは…
様々な派生ゾンビの登場
シリーズが進むにつれ、単なる人間由来のゾンビだけでなく環境要因や他生物との融合による変異体も数多く生まれた。以下、いくつかユニークな派生ゾンビを紹介していく。
ゾンビ犬(ケルベロス)
前述のように『1』から登場したゾンビ化したドーベルマン犬。正式名称は「MA-39 Cerberus」で、T-ウィルスを投与された軍用犬が脱走したものとされている。
素早い動きで飛びかかり、プレイヤーを転倒させて噛みつくため、屋外や廊下での脅威となった。
以降の作品でも定番クリーチャーとして登場し、『RE: ヴェンデッタ』などCG映画版でも凶悪なゾンビ犬が猛威を振るう。
動物のゾンビ
犬以外にも、カラスやヘビ(アークレイの森の蛇=アダー) 、巨大なサメ(ネプチューン) など、動物がT-ウィルスに感染してクリーチャー化した例がある。
カラスは群れで襲う上に弾薬の無駄遣いになりやすい厄介な存在で、『2』では警察署廊下を飛び回るなど不気味な演出がなされた。
ヘビは『1』洋館外庭で無数に降ってきてプレイヤーを毒状態にするなど嫌がらせ的な役回りだった。
ゾンビ化したサメのネプチューンは『1』地下施設の水槽で登場し、停電によって水位が下がるとバタバタ跳ねる姿がある意味恐怖と滑稽さを演出した。
強化型ゾンビ(ゾンビ改)
『2』には、アンブレラが人工培養で強化しようと試みた強化型ゾンビが極稀に登場する。
筋肉組織が剥き出しになったような外見で攻撃力が高い特殊個体だが、B.O.W.としては失敗だったのか後のシリーズには未登場 (リメイク版では通常ゾンビより弱体化され、再出現もしなくなった )。
植物融合型ゾンビ(プラントゾンビ)
『バイオハザード アウトブレイク File2』では、植物に寄生・融合されたグリーンゾンビが登場した。
頭部に開花した植物が毒花粉を撒き散らす厄介な特性があり、植物系B.O.W.(プラント42など)の要素とゾンビの融合が見られる。
寄生虫埋込型ゾンビ
『バイオハザード CODE: Veronica』では、腹部に未知の寄生虫が植え付けられたゾンビがおり、倒すと一定確率で体内の寄生虫が飛び出して襲ってくるという演出があった。
倒した後も油断できない仕掛けとしてプレイヤーを驚かせた。
ガス処理型ゾンビ
『バイオハザード RE:2(2019年のリメイク2)』のエクストラモード「The 豆腐 Survivor」などに登場するP-εガスゾンビは、アンブレラの神経ガスを浴びて変異し、全身が紫色に変色して口から毒ガスを吐く特殊ゾンビ。
通常のゾンビとは異なる攻撃手段を持つ派生例。
異常再生型ゾンビ(ペイルヘッド)
こちらも『RE:2』追加モードなどに登場した突然変異体で、全身が白く変色し、凄まじい再生能力を備えたゾンビ。
損傷箇所を即座に再生するため通常武器では倒しにくく、高い機動力も持つ強敵だが、体力が減ると動きが鈍るという弱点も設定されている。
その姿形は朽ち果てない白い肌に毛の無い人型で、開発スタッフによれば『7』の“Molded”(後述)にも少し似ているとのこと。
『6』の変異ゾンビ群
物議を醸したアクション寄りの作品『バイオハザード6』だが、レオン編ではC-ウィルスによるゾンビが登場した(後述の通り、同作ではウィルス感染経路によってゾンビ化するケースとしないケースがある設定。 )。
『6』では従来より動作が速く攻撃的なゾンビも多く、さらに特定条件で突然変異する個体が存在します。例えば、“ブラッドショット”は筋組織が露出した高速ゾンビで 、こちらは一定のダメージを受けた通常ゾンビが一気に変異して発生することがある。
また、“シュリーカー”は発達した発声器官で大音量の叫び声を上げ、周囲のゾンビを呼び寄せるという厄介な個体。
叫び声を上げる喉が弱点で、倒すと最期の絶叫で周囲のゾンビを巻き添えに爆散させるという特異な性質も持っている。
さらに、“ウーパー”と呼ばれる超大型ゾンビも登場し、巨体による突進や振り回しで脅威となりました (上位種の「ウーパー・シュプリーム」はより巨大で強力)。
以上のように、シリーズ各作品でゾンビは様々な形態に“進化”し、多彩なバリエーションを見せてきた。
背景設定上はすべてT-ウィルス(あるいはその派生ウィルス)の影響によるものだが、プレイヤー視点では「同じゾンビでもこんなに違う!」という新鮮な驚きが毎回提供されてきたと言えるだろう。
こうしたバリエーションはゲームデザイン上の刺激を与えると同時に、T-ウィルスの変異性の高さやバイオハザード世界の生物災害の奥深さを物語る要素ともなっている。
ゲームプレイ上でのゾンビの脅威と対処戦術

ゾンビはシリーズを通じて最も頻繁に遭遇する敵であり、そのAI挙動、出現数、耐久性などは各作品のゲーム性を大きく左右している。
ここではゲームプレイ上の視点から、ゾンビがどのような脅威となり、プレイヤーはどんな戦術で対処してきたのかを解説していく。
基本挙動:遅いが執拗、知能低下と残存本能
古典的なT-ウィルスゾンビの挙動は、動きが鈍重で足が遅いことが特徴。これは前頭葉の壊死による知能低下で俊敏な行動や回避ができないためだが、反面腕力は生前より増しているとも設定されている。
噛みつきと引っ掻き以外の攻撃手段を持たないため、プレイヤーはある程度距離を取って対処できるデザインになっている。
開発者の門井一憲氏(RE:2ディレクター)は「ゾンビは遅いほうがいい」と考えていると述べており、その理由として「目の前にじわじわ迫ってきて『どうしよう!?』と焦る時間が大事」だからだと語っている。
実際、最新作のRE:2でもゾンビは(走る個体も珍しくなくなった時代にあえて)緩慢な動きを踏襲し、撃っても撃っても倒れずじりじり距離を詰めてくる不気味さを演出している。
ただし「遅い」とはいえ執拗に追ってくるのがゾンビの恐ろしさである。ドアを開ける程度の知能は残っている個体もあり(『1』では一部ゾンビが扉を開けて他部屋へ侵入) 、大群で出くわすと一般市民では簡単に逃げ切れない。
シリーズ屈指の生存者であるレオン・S・ケネディでさえ、『2』オープニングでは車中でゾンビに腕を掴まれており、一歩間違えば初陣で命を落としていた描写がある。
「一体では脅威でなくとも、数と不意打ちで圧倒する」のがゾンビの本質的な脅威と言えるだろう。実際にラクーンシティ消滅事件(1998年9月)の際も、政府が事態を把握する前に感染者(ゾンビ)が溢れ返り、後手に回ったことで手が付けられなくなった。
耐久性とダメージ表現
ゾンビの耐久力(HP)は作品や個体によってまちまちだが、概ね頭部が弱点である点は共通している。
ゲーム的には頭部への攻撃がクリティカル(即死)になる可能性が設定されていることが多く、ショットガン等で頭を吹き飛ばせば一撃で倒せる場合がある。
逆に頭を残して胴体を破壊した場合、這いずり状態で生存者にしがみつく執念も見せる(例:RE:2で足を潰されたゾンビが匍匐前進する)。
映画版との違いとして興味深いのは、「ゲーム版では部位を問わず一定量のダメージを与えれば死亡判定になる」が、「CG映画版では頭部破壊以外では倒せない」という差異。映画『ディジェネレーション』ではレオンが頭以外撃ってもキリがないゾンビの恐怖を語っており、これはゲームとの差を強調する設定となっている。
耐久性に関連して、近年の作品はゾンビのダメージ表現が非常に細かく描写されるようになった。リメイク版『RE:2』(2019)では、銃撃箇所に応じてゾンビの肉が抉れ骨が露出し、足を撃てば足を引きずり、腕を破壊すれば這ってくる、といったリアルな反応を示す。
門井ディレクターは「ゾンビの恐ろしさには本当にこだわっていて、弾丸が当たった部位が傷つきダメージ量でリアクションが変化する」よう細かくモーションを作り込んだと述べている。
さらに「噛まれたとき主人公に噛み跡が残る」といった演出も取り入れ、恐怖感とリアリティを高めている。これらのこだわりは、単なるグラフィック向上にとどまらず、プレイヤーに「効いてるのか?倒せたのか?」という不安を与えることでゲーム体験を深化させている。
戦術:戦うか逃げるか、リソース管理

サバイバルホラーにおいてゾンビと対峙したとき、プレイヤーは「倒すべきか、回避すべきか」常に判断を迫られる。
特に古い作品では弾薬が極端に少なく設定されているため、全てのゾンビを倒すのは非現実的。そこで「危険な位置にいる敵だけ倒し、それ以外はかわして進む」という節約プレイが推奨される。
『1』~『3』の固定カメラ時代は部屋ごとの敵数も限られていたため、敵配置を覚えて最短経路で回避するといった攻略法が生まれた。
逆に『アウトブレイク』シリーズのようにオンライン協力プレイを想定した作品では、次から次へとゾンビが出現する状況下を仲間と協力して突破するアクション性も求められた。
どうしても戦闘が避けられない場合、武器選択と狙う部位が戦術の要になる。
例えば、ハンドガンは弾数こそ多いもののゾンビを倒すのに何発も必要。ショットガンなら近距離で頭部を吹き飛ばせるが、弾が貴重。ナイフは弾薬節約の最終手段だが、リーチが短く下手に斬りかかると噛まれてしまうリスクもある。
実際、初代開発中に門井氏が「ナイフでゾンビを簡単に倒せるよう調整していたら三上(真司)さんに怒られた」というエピソードがあり、「斬りつけたら一度は噛まれるくらいのテンポがいい」と言われたと振り返っている。
これはゾンビの恐怖演出上、「安易に近接攻撃で処理できない絶妙な強さ」に調整する狙いがあったことを示している。
シリーズ後期になると、防御アイテムの活用も戦術に組み込まれた。リメイク『1』では緊急回避用のダガーナイフやスタンガンで掴まれ時の被害をゼロにでき、『RE:2』でもナイフや手榴弾を噛まれ際にカウンターで使用し難を逃れるシステムがある。
これらは「最終手段としての護身用具」として位置付けられ、ゾンビに囲まれても即ゲームオーバーにならない代わりに、使えば消耗するリソースというジレンマを生んだ。
難易度が上がるとゾンビの数や耐久が増すのはもちろん、配置やAIもいやらしく調整される。例えば、高難易度では扉付近に待ち伏せして掴みかかるゾンビが増えたり、倒したふりから起き上がる確率が上がったりする。
こうした変更にもプレイヤーは順応する必要があり、「なるべく壁沿いを走って距離を取る」「瀕死のふりをしたゾンビは予防で追撃する」など経験知が活きてくる。
一方で、作品によっては「全滅させて安全地帯化する」戦法も有効だった。代表例は『RE:3』で、街のある区域を一掃すればアイテム探索が格段に楽になるため、火炎弾など強力武器を投入してでも殲滅する価値があった。
また『コード:ベロニカ』ではナイフが異常に強く設定されており、習熟すればほとんど弾を使わずゾンビを処理できるため「ナイフ無双ゲー」と呼ばれたりもしました(その代償か、次作『4』ではナイフが弱体化したが、ゲームシステム的に使い勝手が向上している)。
このようにゾンビとの対峙は戦闘とリソース管理の両面でプレイヤーに判断を求めるゲームデザインとなっており、それがサバイバルホラーの緊張感を支えている。「見た目は雑魚でも、攻略上は最も厄介な敵」という位置付けは、バイオハザードならではの醍醐味と言えるだろう。
ビジュアル・アートデザインの変遷

ゾンビの視覚的な表現も、シリーズの進化とともに大きく変わってきた。
技術の発展によりポリゴン数や描画性能が向上したことで、よりグロテスクでリアルなゾンビ像が描かれるようになった。その変遷を振り返ってみよう。
初期作品のローポリゴンから実写調へ
初代『バイオハザード』(PS1版)のゾンビモデルは、現在から見れば粗いローポリゴンだった。当時はプリレンダリング背景に低ポリゴンキャラクターという構成だったため、ゾンビも全体的に角張った体躯でテクスチャもぼんやりしていた。
しかし、そんな制約の中でも開発陣は「血塗れで腐敗した人間」らしさを見事に表現しており、襤褸の服や垂れ下がる片腕、肌の変色などで不気味さを醸成していた。
口元を赤く染めたゾンビの立ち姿が振り向く名シーンは、荒いグラフィックながら想像力を刺激し、多くのプレイヤーにトラウマを植え付けた。
1998年発売の『2』や1999年『3』では、ハードは同じPS1でしたがモデリングとテクスチャが洗練され、ゾンビの種類も増えたため視覚的バリエーションが豊かになった。
例えば、『2』の女性ゾンビモデルや『3』の帽子を被った男性ゾンビなど、複数のベースモデルが用意されていたので、群衆シーンでも同じ見た目ばかりにならない工夫がされていた。
また、ムービーシーンではより高解像度のレンダリングモデルが使われ、腸がはみ出したゾンビや上半身だけのゾンビなど、直接的なグロテスク描写も追加された。
ゲームキューブ版リメイク(2002年)ではハード性能飛躍によりゾンビのビジュアルは飛躍的にリアル化した。肌の質感や濁った眼球、牙の生えた口内など細部まで作り込まれ、照明効果で湿ったような生臭さまで感じさせる。
赤褐色に錆びた血痕表現も相まって、「画面から臭いが漂ってきそう」と評される程だった。当時の雑誌インタビューでは、開発チームが「恐怖感を支えるのはグラフィックのリアルさ」と語っており、三上真司氏も「バイオの本質部分はまず怖いこと、それからリアルな世界観であること」と述べている。
ゾンビのリアルな造形は、そのままプレイヤーの恐怖直結に繋がる要素として重視されたのである。
近年作品のゴア表現と多様性え
HD世代以降(『4』以降)になると、敵クリーチャーは多様化したが、クラシックなゾンビ像が再登場するのは久しぶりとなった(『4』『5』では後述の寄生体クリーチャーがメインに置き換わったため)。
2012年の『6』で約13年ぶりに本編にゾンビが復活した際は、CEROレーティング上の表現規制もありながら、可能な範囲で肉体欠損表現や流血が描かれた。
また群衆シーンでは、『5』までのプラーガ系クリーチャーにはなかった朽ちた死臭漂う色彩(肌の青白さや血の黒ずみ)を持つ敵が久々に出現し、往年のファンには「やはりバイオはゾンビ」と再認識させるビジュアルだった。
リアル志向の極致ともいえるのがリメイク2作目『バイオハザードRE:2』(2019年)。REエンジンによるフォトリアルなレンダリングで描かれたゾンビは、服装や体格にバリエーションが豊富なだけでなく、上述したように被弾による破壊表現が細密。
特筆すべきは頭部損壊のグロ描写で、ショットガンを撃った際に頭蓋骨が砕け散り脳漿が飛び散る様子まで克明に描いている。これらの表現は年齢規制(CERO Z相当)ギリギリまで攻めたもので、開発陣も「Z版でなければ実現できなかった」とコメントしている。
また、ゾンビのコスチューム面のデザインも興味深い変遷がある。初代では主に洋館研究員風の白衣ゾンビや茶色シャツの男ゾンビなど限られたパターンでしたが、シリーズが進むにつれその場所に合わせた服装が用意された。
『2』では警官ゾンビや市民服ゾンビ、『CV』では軍服島民ゾンビ、『0』では乗客スーツ姿のゾンビなど、多彩。
RE:2ではそれをさらに発展させ、ラクーン署内のゾンビも男女・人種様々で、ある者は腕章付き警官、ある者は私服の一般人といった具合に生活感を伴うディテールが付加された。
「生活していた人々がある日突然ゾンビに変わった」というリアリティが増すほど、プレイヤーは単なる敵としてでなく悲劇の産物として彼らを見ることになった。こうした哀れみの要素もまた、ビジュアルデザインがもたらす感情効果と言える。
クリーチャーデザインの意図
デザイン面で興味深いのは、ゾンビという古典的存在をどう新鮮に見せるか開発側が常に工夫している点で。例として、『バイオハザード ダムネーション』(2012年のCG映画)では敵はプラーガ寄生兵でしたが、敢えて動作をぎこちなくし言葉もほぼ発さないよう描写することで、外見は寄生体でもまるでゾンビのような不気味さを演出している。
一方、ゲームの『4』ではそれまでのノロノロゾンビを刷新し、日常会話を喋るガナードという斬新な敵像を打ち出した。このように、伝統的な遅いゾンビと現代的な速い感染者という対比軸で、作品ごとにアートコンセプトが揺れ動いている。
門井氏は「最近では走るゾンビも珍しくないが、バイオではあえて遅くしている」と述べており 、シリーズにおいては緩慢な怖さを重視する方向性がうかがえる。
さらに、ゾンビの意匠にはオマージュも込められています。制作スタッフはジョージ・A・ロメロ監督の『ゾンビ(Dawn of the Dead)』など古典的ゾンビ映画に強く影響を受けており 、灰青色の肌や飢餓にうめく様はまさにロメロ映画の延長線上にある。
実際、1990年代当時はゾンビ映画が下火だったが、バイオハザードのヒットにより再びゾンビブームが巻き起こったとも言われる。その意味で、バイオハザードのゾンビデザインは古典ホラーの正統進化と評されている。
まとめると、ポリゴンの粗い時代から実写と見紛う現在まで、ゾンビのビジュアルは劇的に進化して行った。
しかし根底にあるコンセプト、つまり「死者のようでいて完全には死んでいない、グロテスクで哀れな存在」というイメージは一貫している。シリーズスタッフもその本質を踏まえつつ各時代の最新技術でゾンビ像をアップデートしてきたと言える。
開発スタッフの証言・インタビューから見るゾンビの裏側
バイオハザードシリーズのクリーチャー描写については、開発スタッフが様々な場面でその意図や苦労を語っている。ここでは特にゾンビに関する興味深い開発裏話や制作思想をピックアップして紹介する。
「ホラーゲーム×ゾンビ」誕生のきっかけ
シリーズの生みの親、三上真司氏は大のゾンビ映画好きとして知られている。初代『バイオハザード』の企画段階について、当時プランナーだった門井一憲氏はインタビューで「まず“とにかく怖いゲームを作る”という目標があって、三上さんがゾンビ映画好きだったのでゾンビの登場が決まった」と証言している。
企画当初は他にも色々なモンスター案があったようだが、最終的にゾンビが中心に据えられたといい、これが結果的にバイオハザード=ゾンビという強烈な印象を与えることに繋がった。
もし三上氏がゾンビ好きでなかったら、シリーズの方向性も違ったものになっていたかもしれない。
三上氏自身も後年のインタビューで「『バイオ』の本質はまず怖がらせること、そしてリアルな世界観である」と語っており 、ゾンビはその「怖いリアルな世界観」を象徴する存在だっただろう。
企画段階でスタッフ全員にホラー映画研究をさせたり、カプコンの過去ホラーゲームをプレイして恐怖演出を勉強したという逸話もあり、ゾンビ登場シーンの完成度の高さは並々ならぬ研究の賜物だった。
絶妙なゲームバランス調整
初代ディレクターの三上氏やプランナーの門井氏の発言からは、ゾンビの強さ調整に関するこだわりが感じられる。前述の通り、門井氏はナイフ攻撃の調整で「斬って怯ませ続けて簡単に倒せる」設定にしていたところ三上氏にダメ出しされ、「一度斬ったら一度噛まれるくらいがいい」とアドバイスされたと述べている。
この背景には、ゾンビが単なる雑魚ではなく一対一でも脅威となり得る存在感を持たせたいという狙いがあったと思われる。実際、初代~RE:2に至るまで、ゾンビ1体に油断して噛まれると体力がごっそり減り、下手をすると連続攻撃で死亡する危険すらある。
開発者は「プレイヤーを追い詰めすぎず、しかし気を抜けばやられる」という絶妙なラインを探りながらゾンビの強さを設定していたのだろう。
また、恐怖演出に関して門井氏は他人のプレイを見る重要性に触れており、開発スタッフで慣れてしまった自分達では怖くない部分でも初見の人は非常に驚くことがあると語っている。
例に挙げているのが窓から犬ゾンビが飛び込むシーンで、スタッフはそこまで驚くとは思わなかったのに、初めて遊んだ人は悲鳴を上げるほど驚いたとのこと。
この経験から「狙い通りにプレイヤーが驚いてくれると『よしよし』とほくそ笑む」と冗談交じりに語っており 、開発陣がいかにプレイヤーの反応を想定しながら演出を仕込んでいるかが伺える。
新たな挑戦:クリムゾン・ヘッド誕生秘話
無印リメイク版で導入されたクリムゾン・ヘッドは、初代プレイヤーへのサプライズとして効果絶大だった。開発インタビューでは、当時のディレクターが「初代を知っている人ほど驚かせたい」と意図してクリムゾン化システムを考案したことが語られている。
具体的には、「死体が蘇る」というゾンビ映画では定番ながらゲームではまだ実装されていなかった要素を組み込むことで、初見でも懐古ファンでも新鮮な恐怖を提供できると考えたそうだ。
実装にあたってはクリムゾン化までの猶予時間や燃焼アイテムの配置バランスなど調整が難航したようだが、結果的にシリーズ屈指のトラウマクリーチャーが誕生した。
後年、カプコンが実施した人気投票企画でもクリムゾン・ヘッドは上位に食い込む人気ぶりで、「リメイクで最も恐ろしく生まれ変わったゾンビ」として強く印象付けられている。
REエンジンでのこだわり
最近の開発者発言として注目すべきは、REエンジン作品でゾンビを再現する際のこだわり。門井氏(RE:2)によれば、「ゾンビに噛まれたらちゃんと傷跡が残るようにした」のは、VR時代も見据えた没入感向上のためだったとのこと。
また、RE:2の開発過程ではゾンビの頭部破壊表現が過激すぎて規制に抵触しないギリギリを模索したそうだ。
例えば、日本版では頭部欠損後に脳が見えないよう内部を黒くする、といった微調整を行いながら表現の限界を攻めたとメイキング映像で語られている(参考:RE:2開発者インタビュー映像)。こうした情熱は、「ゾンビを怖がってほしい」という開発者の一念に他ならない。
「ゾンビはバイオの顔」
制作陣にとってゾンビとはどんな存在なのか――あるプロデューサーは「ゾンビはバイオハザードの“顔”だ」と述べている。実際、シリーズ25周年企画など公式プロモーションでもゾンビが真っ先にフィーチャーされており、開発側もゾンビに対して特別な愛着と誇りを持っていることが窺える。
カプコン公式の投票企画(映画化の際に好きなクリーチャーランキング)でも、ゾンビが1位を獲得したというエピソードがある。アメリカのファンは特にゾンビ愛が強く、タイラントよりゾンビを推した結果、映画でタイラントの出番が無くなったという裏話まであるほど。
総じて、開発スタッフの言葉からは「ゾンビ抜きにバイオハザードは語れない」という強いメッセージが感じられる。初代から最新作まで脈々と受け継がれるゾンビ像には、そうしたクリエイターたちの想いが込められている。
CGアニメ作品や外伝で描かれたゾンビ
バイオハザードはゲームだけでなくフルCGアニメ映画や小説、スピンオフゲームなど様々なメディア展開がなされている。
それらに登場するゾンビの描かれ方にも、ゲーム本編とは異なる特徴や補足設定が存在する。ここでは主要なCGアニメ作品と代表的な外伝ゲームにおけるゾンビ(または類似クリーチャー)の描写を解説する。
CG映画シリーズでのゾンビ
カプコン制作によるバイオハザードCG映画は、『ディジェネレーション』(2008年)、『ダムネーション』(2012年)、『ヴェンデッタ』(2017年)、『デスアイランド』(2023年)などがある。
バイオハザード ディジェネレーション
ラクーン壊滅から7年後の2005年、アメリカ中西部のハーバードヴィル空港を舞台にした作品。テロリストが空港にT-ウィルスをばら撒いたことで利用客が次々ゾンビ化し、空港は阿鼻叫喚の地獄絵図と化した。
クレア・レッドフィールドやレオン・S・ケネディが生存者救出に奔走するが、時を同じくしてT-ウィルスに感染した旅客機が滑走路に墜落し、乗員乗客全員がゾンビ化してさまよい出るという最悪の事態に発展する。
映画ならではの描写として、ゾンビは頭部を破壊しない限り倒せないリアル志向があり、レオンたちはヘッドショットを狙って応戦する(ゲームのように適当に撃って倒せるものではないと強調されている)。
また、空港内は完全封鎖され特殊部隊が突入するが、中は「ゾンビの巣窟」と化しており 、ゲーム以上の大規模アウトブレイクが描かれた。本作はCG映画第1弾としてゲームファンの支持も高く、後に空港脱出劇の部分がゲーム『バイオハザード ディジェネレーション(モバイル版)』としても遊べるようになっている。
バイオハザード ダムネーション
東欧の内戦国を舞台に、レオンが生物兵器の実態を追う物語。ウィルスではなく寄生生物プラーガが兵士に使われており、ゾンビらしき従属種プラーガ感染者(ガナードに相当)が登場する。
ゲーム版『4』以降のガナードは知能があり言葉も話すが、この映画では動作がぎこちなく言語もほぼ話さないため、見た目はゾンビに近い描写がなされている。
小説版冒頭では、大群のプラーガ兵が支配種プラーガ持ちに率いられて政府軍を襲撃するシーンがあり、まるでロメロ映画のゾンビ集団戦の様相を呈している。一方で映画中盤にはリッカーも大量投入され、こちらはT-ウィルス由来クリーチャーだがプラーガで制御されている設定になっている。
なお、『ダムネーション』には厳密な意味でのT-ウィルスゾンビは登場しないが、小説版ではリッカーに襲われT-ウィルスに感染した兵士がゾンビ化する描写が冒頭にあり、わずかながらゾンビが登場している。
バイオハザード ヴェンデッタ
ニューヨークでのバイオテロを描いた作品で、クリス・レッドフィールド、レオン・S・ケネディ、レベッカ・チェンバースが共演する。本作では悪の商人グレン・アリアスが開発した新種の「A-ウィルス」が使用され、これによって多数の一般市民がゾンビ化病を発症する。
A-ウィルスによるゾンビは特殊で、C-ウィルス系ゾンビ並みの俊敏さと、T-ウィルス系を遥かに上回る感染力を兼ね備えている。
さらに特徴的なのは、アリアスがこのウィルスに敵味方識別能力を持たせた点。感染者たちは知能の一部が残され、仲間(ウィルス投与者)と敵(標的)を区別して襲うという、ある意味アンブレラ社が成し得なかった“コントロール可能なゾンビ兵”となっている。
劇中ではBSAA特殊部隊とレオン&クリスが協力し、大量発生したニューヨークのゾンビ群を一掃するアクションシーンがクライマックスで描かれる。このシーンは「CG映画ならではの豪快なゾンビ殲滅シーン」としてファンにも好評で、怨敵への復讐に燃えるクリスとレオンが肩を並べて銃を乱射しゾンビの群れをなぎ倒す様は爽快でもあった(ホラー色よりアクション色が強い作品です)。
なお本作ではゾンビ犬(ケルベロス)やゾンビ化した子供といったショッキングな存在も登場し、シリーズのお約束と新規性を織り交ぜた演出がなされている。
バイオハザード:デスアイランド
2023年公開のCG映画最新作。ラクーン事件から25年後の世界で、アルカトラズ島が舞台となっている。ここではシリーズ主要キャラであるレオン、クリス、ジル、レベッカ、クレアが勢揃いし、元科学者のディランが仕掛けるウィルステロに立ち向かう。
ディランはT-ウィルスとG-ウィルスを組み合わせた新種を拡散し、アルカトラズ島の職員や観光客を大量にゾンビ化させた。
終盤では主要キャラたちがゾンビの群れに囲まれ窮地に陥るシーンもあり、5人の共闘で島中のゾンビを殲滅する総力戦が展開される。
『デスアイランド』は歴代主人公たちとゾンビの直接対決が描かれた初の映像作品として見応えがあり、ファンサービス的な意味合いも強い作品だった。
以上のように、CG映画シリーズではゲーム本編さながらかそれ以上のスケールでゾンビアウトブレイクが描かれている。
特に空港やニューヨーク市街といった公共の大空間でのパニック描写は映画ならではで、ゲームとは一味違う恐怖と興奮を提供している。
また、映画独自の設定(A-ウィルスの敵味方識別など)も本編ストーリーを補完・発展させるものとして興味深い要素。
外伝ゲーム作品でのゾンビ描写
本編以外のゲーム作品でもゾンビは度々登場している。それぞれシチュエーションが異なるため、ゲーム性に合わせた描かれ方がされている。
『バイオハザード アウトブレイク』シリーズ(2003-2004年)
「もし一般市民がラクーンシティでゾンビ災害に巻き込まれたら」というコンセプトの外伝。複数の市民キャラクターから一人を選び、生存者同士で協力しながらシナリオを脱出する(オンライン協力対応)。
このシリーズではユニークなシステムとして、時間経過でウィルス感染率が上昇し、100%になると自キャラがゾンビ化してしまうことが挙げられる。
ゾンビ化後もしばらくは自キャラを操作可能で、仲間に襲いかかることもできるというブラックな要素だった。アウトブレイクではゾンビ犬や象のゾンビ(動物園ステージで登場)などバラエティに富んだゾンビも描かれており、「ゾンビ化した動物は人間以上に危険」という教訓をプレイヤーに植え付けた。
また、不特定多数のNPC市民が襲われゾンビ化する過程も描かれ、一般人視点から見た絶望的なゾンビパニックを体験できる作品だった。
『ガンサバイバー』『デッドエイム』シリーズ
ガンシューティング形式のスピンオフゲームでは、基本的な敵配置や挙動は本編に準じているが、プレイヤーの行動が主観視点・銃撃メインになるため、ゾンビもシューティング的な脅威となっている。
例えば、『デッドエイム』(2003年)では洋上の豪華客船が舞台で、暗闇の通路を徘徊する乗客ゾンビたちをガンコンで撃退して進んで行く。ガンシューティングでは多数の敵を撃ちまくる爽快感も重視されるため、本編よりもゾンビ撃破が軽快かつ大量になる。
その分、ゾンビのスポーン数も多く設定され、次々現れる敵を正確に撃ち倒すエイム力が試された。本編のようなリソース管理よりリフレックス重視のデザインのため、同じゾンビでもゲームジャンルが変われば脅威度も変化する好例と言える。
『ザ・マーセナリーズ 3D』『バイオハザード アンブレラコア』など
アクションシューティング寄りの外伝では、ゾンビはスコア稼ぎや戦略オブジェクトとして使われた。例えば、『アンブレラコア』(対戦TPS、2016年)では、フィールド上に徘徊するゾンビに自分の匂いを隠すジャマーを装備して見つからないようにしつつ、相手プレイヤーのジャマーを壊してゾンビに襲わせるという独特の駆け引きがあった。
ゾンビはプレイヤー同士の戦闘に乱入する第三勢力として作用し、対戦における戦術の一部となっていた。このように、ゾンビは対人戦ゲームの中でもバイオシリーズらしさを演出するギミックとして活用されていたのである。
アニメシリーズ『インフィニットダークネス』
2021年にはNetflixでCGアニメシリーズ『バイオハザード:インフィニット ダークネス』が配信された。全4話の短いシリーズだったが、そこでもゾンビが登場している。物語前半ではホワイトハウスが舞台となり、大統領執務室にゾンビが出現してレオンや米シークレットサービスと交戦するシーンがある。
また後半の中国でのエピソードでも、地下施設に閉じ込められた兵士たちがゾンビ化し、暗闇の中クレア達に襲いかかる場面が描かれた。
インフィニットダークネスでは、ゲーム中では直接描かれなかった政権中枢でのバイオテロという新鮮なシチュエーションでゾンビパニックが展開し、シリーズの物語世界を広げた。
以上、外伝作品やCGアニメにおけるゾンビ描写を見てきた。媒体やゲーム性が変わっても、ゾンビの恐怖演出や活用法にはシリーズらしさが貫かれていることが分かる。
ファンにとっても、そうした他メディアでゾンビがどう扱われるかは興味深いポイントであり、本編とは一味違ったゾンビ像を楽しめる要素となっている。
ファンやメディアの評価
ゾンビ=バイオハザードの象徴というイメージは、シリーズファンにも深く浸透している。ここでは、ゾンビに対するファン・メディアからの評価や反応をいくつか紹介。
ファンからの人気と不満の両面
前述したように、北米で映画化の際に行われたモンスター人気投票ではゾンビが堂々の1位となり、タイラントなど他のクリーチャーを抑える結果となった。これは「とにかくゾンビが好き」というファン層が厚く存在する証左だろう。
ゾンビは敵キャラでありながらマスコット的な愛され方もされており、関連商品(フィギュアやTシャツ等)でもゾンビがモチーフになることが多々ある。例えば、S.T.A.R.S.警官ゾンビのフィギュアやクリムゾン・ヘッドのスタチューなどが販売され、コレクターの人気を博した。
一方で、シリーズ途中でゾンビが登場しなくなった時期(『4』『5』)には、「ゾンビが出ないなんてバイオじゃない」と嘆く往年ファンの声も聞かれた。実際、『4』開発当時のインタビューでは三上氏が「ゾンビものでマンネリと言われたから大胆に変えた」と語っており、新路線は賭けだったと振り返っている(結果的には『4』はシリーズ転換の大成功として歴史に残ったが)。
このように、ファンの中でもゾンビの扱いに対する意見は分かれることがあり、ゾンビ回帰を望む声と新規軸を評価する声のバランスが難しいところ。
カプコンはその調整にも長けており、例えば『バイオハザード6』ではレオン編で原点回帰のゾンビホラーをやりつつ、他編で新タイプも出す構成にした。
また『7』でガラッと敵を変えつつ、その次の『RE:2』リメイクで超リアルなゾンビを投入しファンを歓喜させるというサイクルも取った。これらの戦略は奏功し、『RE:2』は「ゾンビが本当に怖い」「帰ってきたバイオハザード」と批評家・ファンから高く評価された。
メディアによるホラー表現の評価
ゲームメディアの記事やレビューでも、バイオハザードのゾンビ演出は繰り返し取り上げられている。「最初にゾンビと遭遇するシーンの衝撃」は多くの媒体で名場面として言及され 、電ファミニコゲーマーの特集では「振り向きゾンビやタイラントに驚かされて20年」というタイトルでシリーズの歴史を振り返っていた。
また、バイオハザードがホラーゲーム史に与えた影響として、「洋館事件以降ゾンビがゲームの主役モンスターに返り咲いた」という分析もある。90年代末から2000年代にかけては様々なゾンビゲーム(デッドライジング、Left4Deadなど)が隆盛したが、その火付け役は間違いなくバイオハザードだった。こうした観点から、ゲームジャーナリストたちはバイオハザードのゾンビ演出をホラー史の金字塔として評価することが多い。
他方、「なぜ初代バイオは怖くて4は怖くないのか?」という分析記事では、ゾンビという存在が持つ恐怖の質についても語られている。初代が怖かったのは、ゾンビ自体の恐ろしさもさることながら、固定カメラや音響など総合演出でゾンビの怖さを増幅していたからだという指摘。
逆に『4』はゲームとして非常によく出来ているが恐怖という点では後退した、と結論付けられており 、そこにはゾンビの不在(代わりにガナード)が一因として挙げられている。
つまりゾンビの存在そのものが恐怖の源泉であり、敵がただの寄生村人になると恐怖の質が変わってしまう、と分析されている。
シリーズ内でのゾンビの存在感
シリーズ作品ごとの評価を見ても、ゾンビの存在感はしばしば話題に上がる。高評価を受けている作品にはゾンビが登場していることが多い点は注目される。
例えば、ファンから名作との呼び声が高い『RE:2』やリメイク版『初代』、あるいは外伝でも『アウトブレイク』はゾンビパニックとして支持されている。逆にシリーズ評価が割れる『4』『5』『8』などはゾンビが出ない作品(ゲーム性は優秀なため売上は好調だが、「怖さ」という意味で物足りないと感じる層もいる)。
もっとも、これは単純にゾンビがいる=良い作品という話ではなく、ゾンビをどう演出するかが作品評価に繋がるということだと思われる。実際『RE:3』リメイクはゾンビは出てもボリューム不足が指摘され評価は伸び悩み、ゾンビ無しでも『7』は怖さを取り戻したと評価された。
いずれにせよ、メディアもファンもゾンビをシリーズの代名詞と見做しているのは間違いない。シリーズ25周年記念のカプコン公式施策でも、歴代ゾンビのギャラリーや人気投票が行われ盛り上がった。
こうした企画で印象的なのは、単なる敵キャラで終わらず「このゾンビ好き!」という話題になる点です。たとえば「一番好きなゾンビモデルは?初代の緑コートゾンビVS2の警官ゾンビ」なんて海外掲示板のスレッドもあり 、ファンがゾンビ一体一体に愛着を持って語り合っている。
最後に
総括すると、ゾンビはバイオハザードシリーズの原点であり永遠のテーマである。
寄り道をしたり姿を消したりすることはあっても、最終的にはシリーズの根幹に戻ってくる存在だと言える。
プレイヤーにとってゾンビは恐怖の対象であると同時に懐かしさやシリーズのアイデンティティを感じる相手でもある。カプコンもそのことを熟知しており、折に触れてゾンビの魅力を再提示してくれるだろう。
これから先、技術や表現規制がどう変わろうとも、ゾンビが歩み続ける限りバイオハザードは不死鳥の如く蘇り続けるに違いない。
シリーズ30周年、40周年を迎える頃には、また新たな形で我々はゾンビと対峙していることだろう。その日が来るまで、かつて洋館で震え上がった記憶を胸に、我々は次なる“バイオハザード”を待ちたいと思う。