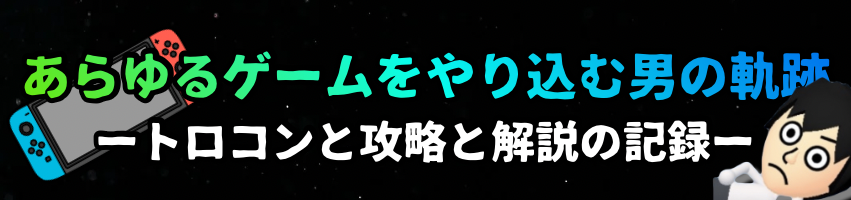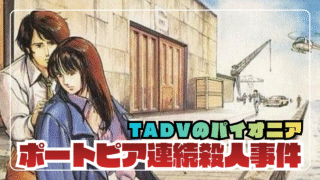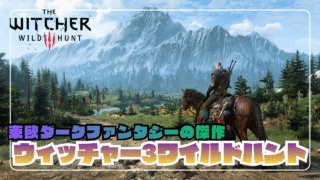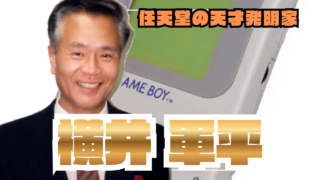⚠️この記事は、筆者の熱があまりにも強すぎてトータル24,000字を超えております。時間がある時に腰を据えてゆっくりお読みください(笑)
1987年。日本のゲーム業界の片隅、1つのタイトルが生まれようとしていた。小さなゲーム会社、スクウェア(当時)は、利益が思わしくなく、崖っぷちの状況にあった。
そんな中、若きゲームクリエイター、坂口博信(Hironobu Sakaguchi)氏は、自らの夢を掛けて「最後の作品」を掲げた。
彼は長年、コンピュータRPGというジャンルに憧れており、テーブルトークRPGやPC‐ゲームの名作からインスピレーションを受けていた。
当時、ファミコン向けに本格的なRPGを作ることは、会社にとって大きな賭けだった。なぜなら、コストや技術的ハードルが高く、成功例も限られていたからだ。
だが、坂口氏はこう訴えた――「このままでは終われない。最後に、夢を賭けた作品をつくる」。それが「FINAL FANTASY」という名の、光と闇の物語の始まりである。
タイトルの「Final(最後)」という言葉には、彼自身と会社の切羽詰まった思いが投影されていた。実際、坂口氏は「このゲームが売れなければ、ゲーム業界を去るつもりだった」と後に語っている。
本記事では、その伝説の裏にある「ゲームシステム」「ストーリー」「開発秘話」を解説して行こうと思う。
『ファイナルファンタジー』とは?
※本記事で使用している画像は『ファイナルファンタジー ピクセルリマスター版』のものです。

- 発売日:1987年12月18日
- 開発・発売:スクウェア(現:スクウェア・エニックス)
- プラットフォーム:ファミリーコンピュータ/ゲームボーイアドバンス/PlayStation/PlayStation Portable/PlayStation 3/PlayStation 4/Nintendo Switch/Wii U/Nintendo 3DS
- ジャンル:ロールプレイングゲーム(RPG)
- シリーズ:ファイナルファンタジーシリーズ
第1章:ストーリー ― クリスタルの声と光の戦士たち

本作の詳しいストーリーは以下のページをどうぞ。
登場キャラクターの詳細は以下のページをどうぞ。
第2章:システムの胎動 ― 古きRPGのフォーマットを越えて

FF1のゲームシステムは、当時すでに存在していたRPGの枠組みを踏襲しつつも、独自の工夫や特徴を加えたものである。
ここでは戦闘システム、ジョブと成長要素、世界マップと冒険の広がり、アイテムと魔法といった観点から、その内容を詳しく見て行こう。
戦闘システム:コマンド選択式+サイドビューの草分け
戦闘はターン制のコマンド選択式で進行する。プレイヤーは各キャラクターに対し「たたかう」「まほう」「アイテム」などのコマンドを入力し、敵味方が素早さ順に行動することでラウンドが展開して行く。
特徴的なのは、ファミコンRPGでは初めて自分のパーティキャラクターが画面右側にグラフィックで表示され、敵モンスターは左側に表示されたこと。
当時主流だった『ドラゴンクエスト』シリーズなどの一人称視点の戦闘とは異なり、横から見たサイドビュー戦闘を採用したことで、キャラクターの姿や攻撃モーションが確認できる臨場感が生まれた。このサイドビュー戦闘のアイデアは、後述する石井浩一氏(当時スクウェアの新人プランナー)が企画段階から温めていたもので、彼の中で明確なビジョンがあったとされている。
コマンド入力式の戦闘は戦略性も備えていた。攻撃対象や使用魔法を選ぶ際、敵の残りHPを見極めて指示を出す必要がある。初代FFには「ターゲットが既に倒されていた場合、攻撃が空振りになる」という仕様(いわゆる空振りバグ)があった。
例えば二人の戦士が同じ敵を狙い、一人目で敵を倒してしまうと、二人目は空振りしてしまう。この仕様上のクセは後年のシリーズ作品では改善されたが、当時は「無駄撃ちを避けるために攻撃対象を分散させる」といった駆け引きが生まれる一因でもあった(この点は裏話の項でバグとして詳述)。
ただし、このような要素はゲームボーイ『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』でも見られた。
ジョブ(職業)と成長要素:6つのクラスとクラスチェンジ
ゲーム開始時、プレイヤーは4人パーティのメンバーを作成する。用意された6種類のキャラクタークラス(職業)から4人分を選択し、それぞれ名前を付ける。選べるクラスは以下の通り。
- 戦士(Fighter) – 攻撃力・防御力に優れ、最強の武具を装備可能。後述のクラスチェンジで「ナイト」になる。
- シーフ(Thief) – 素早さと幸運が高く、敵からの逃走成功率が高いクラス。クラスチェンジで「忍者」になる。
- モンク(Black Belt/Karateka) – 武器に頼らず拳で戦う格闘家。育つと素手が最強になる特殊なクラス。クラスチェンジで「スーパーモンク」になる。
- 赤魔術士(Red Mage) – 剣による物理戦闘と、白・黒両方の魔法をそこそこ使える万能型。器用貧乏とも言われるが序盤の頼もしさは抜群。クラスチェンジで「赤魔道士」となり魔法習得上限が拡大する。
- 白魔術士(White Mage) – 回復・補助効果のある白魔法専門職。打たれ弱いがパーティの生命線。クラスチェンジ後は「白魔道士」と表記が変わり、最上級魔法まで扱えるように。
- 黒魔術士(Black Mage) – 攻撃系の黒魔法専門職。こちらも打たれ弱いが、高威力の魔法で敵を一掃できる。クラスチェンジで「黒魔道士」となり、最上級の黒魔法も使用可能に。
各クラスには固有の長所・短所が設定されており、物理攻撃主体か魔法主体か、防御に優れるか回避に秀でるか、といった違いがある。
また装備できる武器・防具や習得できる魔法のレベルにも職業ごとの制限がある。例えば戦士はほとんど全ての武器防具を扱えるが、魔法は習得できない(ナイトにクラスチェンジ後、「ケアル」などの低レベルの白魔法が使用可能になる程度)。
逆に魔術士系は強力な武器防具を装備できず打たれ弱い反面、魔法運用で真価を発揮する。
物語を進め中盤に差し掛かると、各キャラクターは一段階上位の職業へクラスチェンジできるイベントがある。これはゲーム内の特定クエスト?をクリアすることで実現し、例えば戦士はナイト、シーフは忍者…という具合に見た目も能力もパワーアップする(キャラクターグラフィックも成長した姿に変化します )。クラスチェンジにより新たに装備可能な武具や魔法も増え、一気に戦術の幅が広がる爽快な成長要素だった。
キャラクターの成長は、基本的には経験値によるレベルアップで行われる。敵との戦闘に勝利すると経験値(EXP)とお金(ギル)が手に入り、一定値の経験値を積むごとにレベルが1上昇する。
レベルアップすると最大HPや力・素早さなどのパラメータが上昇し、徐々に強敵に立ち向かえるようになる。最終的なレベル上限は50となっており、レベルが上がるほど上昇幅は小さくなるものの、コツコツと育成していく楽しみがしっかり用意されていた。
広大な世界マップと冒険の広がり:乗り物による移動
FF1の冒険の舞台は、3つの大陸と多数の島から成る広大なファンタジー世界。ゲームには「ワールドマップ」と呼ばれる縮尺の小さい全体マップが存在し、プレイヤーはこのフィールド上を移動して各地の町やダンジョンを探索する。
移動手段は基本は徒歩だが、物語の進行に応じて船・カヌー・飛空艇という3種類の乗り物が手に入る。船は海上移動を可能にし、新たな大陸への航海を演出した。
カヌーは川や浅瀬を渡るための乗り物で、水路伝いに今まで行けなかった土地へ踏み込めるようになる。そして特筆すべきは飛空艇(ひくうてい)の存在。シリーズの象徴ともなる空飛ぶ船・飛空艇は、FF1で初登場。入手後は世界中の平地に自由に離着陸でき、当時のプレイヤーに「空を飛んで世界を冒険する」高揚感を与えた。
フィールド上ではランダムエンカウントによってモンスターとの戦闘が発生する。歩いている最中だけでなく、船やカヌーで移動中にも容赦なく敵が出現するため気が抜けない(飛空艇搭乗中のみ敵遭遇はありません)。
ただし一部には例外的な固定エンカウントも存在する。例えばダンジョン内の宝箱を守るモンスターなど、決まった場所で必ず戦闘になるケースもあった。
ワールドマップ上でも、「一定条件下で必ず強敵が出現する」隠れポイントが存在する。有名なのはプラボカの町(序盤に訪れる港町)の北東に突き出た半島の先端で、そこは周囲の地域に比べ異常に強いモンスターが出現する隠れポイントだった。いわゆる「パワーの半島」とファンに呼ばれるこの場所でレベル上げに励んだプレイヤーも多かったようだ。
町やダンジョンのマップも、当時としてはかなり作り込まれていた。町には宿屋・道具屋・武器屋・防具屋・魔法屋などの施設が並び、住人に話しかけることでヒントや世界観の情報が得られる。
ダンジョンは洞窟や塔、神殿や火山、海底神殿、果ては宇宙に浮かぶ空中要塞まで多彩で、それぞれに宝箱や仕掛けが配置されている。時にはダンジョン内部でカヌーを使って溶岩の中を進む、なんて場面もあり、フィールド以外でもミニ探検を味わえるようになっている。
アイテムと魔法:限られた資源を駆使する戦略
アイテム
冒険を支えるアイテムや魔法の要素もFF1の魅力。フィールドやダンジョンではインベントリ管理が求められ、各キャラクターごとに武器4枠・防具4枠の装備欄があり、持てる道具の数にも限りがある。
回復アイテムのポーション類や状態回復アイテム(毒消しなど)を買い込む際は、この所持数制限に悩まされたものである。(99個まで)
また、本作にはテント・コテージといったユニークな消耗アイテムが登場。これらはフィールド上でのみ使用可能で、使うとHP回復(およびセーブ)ができる簡易宿泊セット。例えば「テント」は低価格で手に入る代わりに回復量が少なく、「コテージ」は高価だがHPだけでなく魔法使用回数も少し回復するといった違いがあった。
ダンジョン内ではセーブできず、一度入ると脱出するか全滅するまでセーブ不可という緊張感があったため、ダンジョン手前で野営(テントやコテージを使用)してから挑むのが常套手段だった。
武器・防具
武器・防具にも注目すべき点がある。剣や斧、杖やナイフ、槍など様々な武器が登場し、中には「使用すると魔法効果を発揮する武器・防具」も存在した。例えば雷の力を持つ「サンダーソード」はアイテム使用で「デジョン(テレポ)」の効果が出たり、白魔道士用の「ヒーリングスタッフ」は使用するとケアルラ相当の回復効果があったりした。使い捨てではない戦闘中アイテムとして、こうした装備品の活用が攻略を楽にしてくれることもある。
また属性や特効(対アンデッドにダメージ倍など)の概念も一応存在していたのだが、実はファミコン版FF1では武器の属性・特効が機能しないバグがあり、本来弱点を突けるはずの武器でもダメージが増えないという問題があった (これも裏話で後述)。
魔法
魔法システムは、FF1独特のスロット(チャージ)制になっている。当時の『ウルティマ』やテーブルトークRPGの影響を受けた方式で、MP(マジックポイント)制ではなくレベル別の使用回数制だった。
魔法には白魔法(回復・補助系)と黒魔法(攻撃・妨害系)があり、それぞれレベル1から8までの段階に分類されている。各レベルにつき4種類ずつ、計32種類の白・黒魔法が存在し、町の「白魔法屋」「黒魔法屋」で購入して習得する仕組み。
しかし1キャラクターが習得できるのは各レベルにつき3種類までという制限があり(つまり同じレベルに4つ魔法があっても1つは覚えられない)、ここでも戦略的な選択が求められた。
魔法の使用回数はレベルごとに管理される。例えばレベル1魔法は最大使用回数×回、レベル2魔法は×回…という具合で、消費すると宿屋で休むかアイテム「エーテル」(FC版には未登場)などで回復しない限り使えなくなる。低レベルの魔法ほど使用回数が多く、高レベル魔法ほど貴重な回数しか使えない。そのためダンジョン攻略では強力な魔法をどこで使うかの駆け引きが生まれた。
特にMP回復アイテムの無いファミコン版では魔法使いは息切れしやすく、序盤は黒魔術士の魔法回数が極端に少ないこともあって「すぐ無力化してしまう」と評されるほど。実際、本作ではステータス「知性」が魔法威力に影響しないバグも抱えており、黒魔道士系の攻撃魔法が伸び悩む欠点があった(知性については後述)
まとめると、FF1のゲームシステムはパーティ制RPGの基本を押さえつつ、複数キャラ運用や乗り物導入、コマンド選択型バトルの演出強化、戦略性のある魔法運用などで当時としては非常に洗練されていた。その一方で、一部バグや不親切な点(セーブ制限や空振り仕様など)もあったが、それすら含めて初代ならではの味わいとして記憶しているファンも多いことだろう。
第3章:開発の舞台裏 ― 崖っぷちから生まれた伝説

続いて、FF1がどのような経緯で生まれたのか、開発当時のスクウェア社内の事情やチームの様子、タイトル名に込められた意味など、開発秘話を紐解いていく。スクウェアが「最後の賭け」に臨んだと言われる本作の裏には、数々のドラマがある。
企画立ち上げの背景:DQの衝撃とスクウェアの窮状
1980年代半ば、スクウェア(当時は電友社のソフトウェア制作部門)は、PC向けゲームの開発からファミコン参入を模索していた。しかし当時の社内では「ファミコンで本格RPGは無理だろう」との空気があり、若きプログラマーだった坂口博信氏も最初はアクションやレースゲームの制作を手掛けていた。
実際、坂口氏率いるチームは『キングスナイト』(縦シューティングゲームを無理やりRPG風に売り出した異色作)や『ハイウェイスター』(3D表現が話題のレースゲーム、『ラッドレーサー』)などを開発するが、いずれも決定的な大ヒットには至らなかった。
そんな中、1986年に発売されたエニックスの『ドラゴンクエスト』(DQ)第1作が坂口氏に大きな衝撃を与る。
「ファミコンでも工夫次第でRPGが作れるんだ」という事実に目を開かされた坂口氏は、DQをきっかけに「自分たちもファミコンでRPGを作ろう」と決意したと言う。
ちょうど同じ頃、スクウェアはファミコン参入を本格化させ会社組織も独立(1986年に株式会社スクウェア設立)。しかしヒット作に恵まれない状況は続き、会社は傾きかけていた。
まさに崖っぷちの状況下で、坂口氏は上層部にファミコンRPG企画を何度も提案。なかなかゴーサインが出なかったものの、社内の開発チーム再編(後述)も追い風となり、ついに社運を賭けた大型プロジェクトとしてRPG開発が動き出す。
少数精鋭Aチーム誕生:4人から始まった開発
スクウェアでは1986年末頃、開発体制の見直しからチーム分割が行われた。坂口博信氏や田中弘道氏(後のFFXIプロデューサー)らリーダー格を中心に4つ程度のチームが編成され、坂口氏もそのひとつのチームを任される。
当時坂口氏のチームに配置されたのはわずか4名だった。主要メンバーは坂口博信(ディレクター)、ナーシャ・ジベリ(Nasir Gebelli、プログラマー)、石井浩一(ゲームデザイン)、渋谷員子(グラフィックデザイナー)という顔ぶれで、社内では皮肉も込め「Aチーム」と呼ばれていたとか(他のチームは15名規模だったのに対し4名しかおらず、「Aチームはもう終わりだな」と噂されたとか) 。
坂口氏自身も当時のチームについて「メンバーが少ないのは自分が厳しかったせいかもしれない」と回顧している。
そんな少数精鋭(?)のAチームだが、実情は過酷でした。彼らには「次のゲームが失敗したら解散」というプレッシャーがのしかかっていたのだ。坂口氏自身、「この次がダメなら大学に戻ろう」と腹を括っていたと言う。
だからこそ、「最後の作品にしよう」という覚悟でRPG開発に挑んだという。
この坂口氏の決意こそが、タイトル『ファイナルファンタジー』の由来である。すなわち「自分にとって最後の(Final)夢・幻想(Fantasy)」という意味を込めて命名されたのである。
実は候補名に「ファイティングファンタジー」という案もあったそうだが(戦う幻夢? やや謎な響きですが)、最終的により象徴的な“ファイナル”が選ばれた。今ではシリーズ名としておなじみのFFだが、その始まりは背水の陣から生まれたものだった。
開発の進行:大量の資料とゼロからのRPG作り
4人スタートの坂口チームは、社内で半ば隔離状態に置かれていた。社屋の倉庫を改造した小部屋に追いやられ(4人しかいないため狭い場所で充分だった)、坂口氏・渋谷氏・河津氏(※途中参加)・ナーシャらは奥の部屋で『ハイウェイスター』の仕上げ作業に追われ、石井浩一だけが手前の即席デスクで一人RPGの企画立案に取り組むという状況だったといいう。
石井氏は当時アルバイト入社から半年ほどの新人だったが、「ドラゴンクエストやゼルダの伝説が好きだった」経験を活かしつつ、試行錯誤でRPGのゲームデザインを考え始めた。
石井氏がまとめた企画の中核には、既にいくつかの斬新なアイデアが盛り込まれていた。その一つが先述したサイドビュー形式の戦闘であり、さらに「火・水・風・土のクリスタル」を軸にした世界観や、ジオラマ風に見せるワールドマップの構想もこの時点で提示されていたという。
ウィンドウUIのデザイン面でも、石井氏は「マリオの土管のイメージから太いウィンドウ枠を」「白い手袋の指差しカーソルは『謎の壁 ブロックくずし』から着想」など細部に工夫を凝らした。このように、新人プランナーが中心となってゼロからRPGを作り上げるという大胆なプロジェクトだった。
企画が具体化してくると共に、徐々に仲間も増えて行く。スクウェアにはテーブルトークRPG愛好家でもあった河津秋敏氏(のちにサガシリーズを手がける)が在籍しており、彼も開発途中から坂口チームに合流。
河津氏の参加によって、FFのゲーム内容は当時ポップだったDQに対しより硬派で幻想性の高いものへと方向付けられていったという。事実、ダンジョンに仕掛けられた謎解き要素や、時間ループを絡めたシナリオなど、どこかマニアックでダークな雰囲気が漂うのも初期FFの特徴だった。
また、開発開始当初からシナリオ面はプロに任せようという方針があり、外部のシナリオライターとして寺田憲史氏が起用されている。寺田氏は当時アニメ脚本家などで活躍しており、FF1~3の脚本を担当。世界設定やプロット原案は坂口氏が提示し、寺田氏がゲームシナリオとしてまとめていく形で物語が作られたようだ。
肝心のプログラミング面では、ナーシャ・ジベリの存在が絶大であった。ナーシャ(Nasir Gebelli)氏は米国在住のイラン系プログラマーで、Apple II時代から3D表現のゲームなどで名を馳せた天才。
スクウェアの宮本雅史社長(当時)がアメリカで偶然知り合い日本に招聘した経緯があり 、1986年夏頃にスクウェアに参加した彼は、『とびだせ大作戦』や『ハイウェイスター』ですでにその腕前を発揮していた。FF1でもマップ画面と戦闘画面を切り替えるシステムや乗り物で広大なマップをシームレスに移動する処理など、ファミコンの性能を限界まで引き出すようなコーディングを行ったと伝えられている。
さらにナーシャは隠しミニゲーム(15パズル)までも密かに実装。これは元々企画に無かった要素だが、彼の遊び心から「RPG史上初のミニゲーム」として船上パズルが生まれた。これには坂口氏も驚いたかもしれない。
開発期間は約半年間という短期決戦だった。1987年の春から制作が本格化し、同年9月頃に一応の完成を迎えたという。完成後、スタッフ達は慰労のためグアム旅行へ出かけたが、帰国すると重大なバグが見つかり慌てて対処したというエピソードも残っている(どのような不具合かは定かではないが、のちに判明した一部魔法効果が機能しないバグ等だったのかもしれない)。
発売直前にはスクウェア本社が御徒町にオフィス移転するドタバタもあり、ギリギリまでデバッグ作業が続けられた。
「ファイナルファンタジー」の名に込めた想い
企画段階から坂口博信氏の並々ならぬ意気込みがあったFF1だが、やはりタイトルに込められた意味は特別だった。先述の通り「自分にとって最後になるかもしれない作品」という覚悟がそのまま名前になっている。
面白いのは、スクウェアの他のスタッフから見ると「坂口チームは終わった」とまで揶揄されていた状況で、それを逆手に取るような自己暗示的な命名だったこと。もっとも、坂口氏自身は後年「別に会社が倒産しそうだったから“ファイナル”にしたわけじゃない。自分の中で区切りをつける意味だった」と語っており、社運云々は結果論とも言える。
事実、当時スクウェアに在籍した北瀬佳範氏(後のFFシリーズプロデューサー)は「FFというタイトルを聞いたとき、別に遺作とか最後とか深い意味は考えず“かっこいい名前だな”と思っただけ」と回想している。
つまり内輪ですらタイトルの由来はあまり共有されておらず、単に音の響きの良さで受け止められていたようだ。それでも「ファイナル=最後」という言葉のインパクトは強く、発売当時からプレイヤーの間でも「何で最後なんだろう?」と話題にはなった。そして蓋を開けてみれば、その『“最後”は新たな始まりの象徴』となっていったのである。
第4章:制作スタッフとその功績
FF1の成功を支えたのは、情熱あふれる少数の制作スタッフだった。ここでは主要メンバーにスポットを当て、当時の役割や経歴、その後のゲーム業界への影響について解説して行く。
坂口博信(ディレクター/ゲームデザイン)
坂口博信(さかぐち ひろのぶ)氏は、言わずと知れたFFシリーズ生みの親であり、本作のディレクター兼ゲームデザイナー。当時25歳前後の若者だったが、大学在学中にスクウェアにアルバイト参加し、そのまま中核スタッフとなった経歴を持つ。
坂口氏はPCゲーム時代からストーリー性のある作品を作ることに熱心で、自らプログラムやグラフィックも手掛けた経験を持っていた。(例:パソコン用ADV『WILL』ではキャラアニメやBGMまで自作したとのこと )。しかしファミコン参入後の数作品が商業的に振るわず、「次がダメならゲーム業界を去る」と決意して挑んだのがFF1だった。
坂口氏はディレクターとしてチームを牽引しつつ、シナリオ原案やゲームバランスの面にも関与。FF1の基本プロット(4人の光の戦士と4つのクリスタル、時空を超えたカオスとの戦いなど)は坂口氏の発案によるところが大きいと言われる。
また開発中、「自分たちが本当に納得できるゲームを初めて作れた」という手応えをチームで味わったそうで、完成直後にはスタッフ皆で達成感を分かち合ったと語られている。この感覚は後に坂口氏いわく「世間に認められる作品が生まれるとき特有のものだった」とのことで、実際FF1は出荷本数52万本超(日本国内)の大ヒットを記録し 、スクウェアにとっても坂口氏自身にとっても運命を変えた一作となった。
以降、坂口博信はFFシリーズのエグゼクティブプロデューサー的立場で関わり続け、FF7の開発・映画『ファイナルファンタジー』制作を経て2001年にスクウェアを退社。その後もミストウォーカーを設立し、『ブルードラゴン』『ラストストーリー』など新たなRPGを世に送り出している。
FF1はそんな坂口氏の原点であり、「思い入れのあるFFとしては特に1・4・5・7」と語るほど、氏にとっても特別なタイトルと言える。
石井浩一(ゲームデザイナー/プランナー)
石井浩一(いしい こういち)氏は、FF1~3のゲームデザインを担当したクリエイター。当時はまだ20歳そこそこの新人アルバイトだったが、坂口チームに配属されるや否や「RPGの企画を考えておけ!」と無茶振りされ、一人奮闘した逸話は前述の通り。
石井氏は4つのクリスタルやサイドビュー戦闘、世界設定の骨子を形作り、UIデザインの細部にまでアイデアを盛り込んだ。さらに、「FFの世界を表現するイラストレーターには天野喜孝さんしかいない!」と最初に提案したのも石井氏だった。当時から熱心な天野ファンで、愛読していた画集『魔天』を見せながら上司を説得したという。
石井氏の働きかけで坂口氏も天野喜孝起用に同意し、横浜の天野氏の事務所へ依頼に行く際には石井氏も同行した (このエピソードは後述の天野喜孝の項で詳しく紹介します)。
また、FFシリーズにチョコボやモーグリなどのマスコットキャラを生み出したのも石井氏で、FF2以降に登場するチョコボは彼のデザイン。後年、石井氏は『聖剣伝説』シリーズの生みの親としても活躍し、スクウェア退社後は株式会社グレッゾを率いている。
FFXIでは初代ディレクターを務め、再び坂口氏や天野氏と仕事をしている。FF1の企画立案者とも言える石井浩一氏の存在無くして、FFシリーズの独自色(クリスタル神話やファンタジックな世界観)は生まれなかったと言っても過言ではない。
河津秋敏(ゲームデザイナー/シナリオサポート)
河津秋敏氏(かわづ あきとし)は、FF1開発途中から参加したゲームデザイナー。石井氏同様若手だったが、熱心なテーブルトークRPGプレイヤーであり、その知識とセンスでFFのゲームデザインに深みを与えた。
具体的には、ステータス異常や属性概念、独特なレベルアップ仕様など、一部マニアックな要素に河津氏の影響が見られると言われている。
例えば、通常は隠しパラメータである「魔法防御」を概念化し、敵の呪文耐性を設定するなど凝った部分も見受けられる。残念ながらFC版ではその魔法命中率計算にバグがあり十分機能しなかったが、後のリメイクでは正しく実装された。
河津氏はFF2でディレクター・シナリオを担当し、斬新すぎる成長システム(経験値ではなく使用行動回数による熟練度)を導入するなど大胆な試みを行う。その後は『サガ』シリーズを立ち上げ、現在もスクウェア・エニックスにてゲーム開発に携わっている。
FF1における河津氏は裏方的な立場だったが、「ドラクエを強くライバル視しつつも心からリスペクトしていた坂口を間近で見た」と語っており 、以降の自身の作品にその精神が活きているのではないだろうか。
寺田憲史(シナリオライター)
寺田憲史(てらだ けんじ)氏は、FF1~3のシナリオライターを務めた人物。元々アニメ脚本家として名高く、『うる星やつら』や『機動戦士ガンダム』の小説版執筆などで知られていた。
スクウェアは外部のプロにシナリオを依頼する形で寺田氏に白羽の矢を立て、ファンタジックで神話的なストーリーをFFの世界にもたらした。FF1では「光の戦士と闇の四戦士の時空を超えた因果」というSF的要素を含む設定をまとめ上げ、ゲーム冒頭とエンディングの印象的なナレーションを書いたのも寺田氏である。
寺田氏は当時の裏話として、「ファイナルの意味」について後年著書で触れており、「坂口君は自分でこれを最後にすると決めていた」と証言している。またシナリオ制作過程では、ゲーム的都合からストーリーに調整が入ることもしばしばで、特にFF3開発時には容量との戦いで泣く泣く台詞を削ったとも語っている。
FF1のシナリオ面は文字数こそ少ないものの、多くを語らず世界の広がりを感じさせる名調子で、これは寺田氏の功績だろう。
天野喜孝(イメージイラスト/キャラクターデザイン)
天野喜孝(あまの よしたか)氏は、FFシリーズの象徴ともいえるパッケージイラスト・ロゴデザイン・コンセプトアートを手掛けたアーティスト。FF1当時、すでに挿絵画家・キャラクターデザイナーとして著名で、『タイムボカン』シリーズ等のアニメ制作や、ファンタジー小説の装画で名を馳せていた。スクウェア側から見ると高嶺の花のような存在だったが、前述の通り石井浩一氏の熱望と坂口氏の直談判によってFFプロジェクトへの参加が実現する。
坂口氏らが横浜の天野氏の事務所を訪れた際、緊張しながら依頼したところ「ああ、いいですよ。やりましょう」と二つ返事で引き受けてくれたという。このとき坂口氏はスポーツカー(RX-7)で石井・渋谷を乗せて行ったのだが、後部座席に押し込められた渋谷員子氏が身体を横にしないと乗れないほど狭く、皆で「天野さん引き受けてくれるかな?」とワクワクドキドキしながら向かったという微笑ましいエピソードも残っている。
天野氏がもたらした功績は計り知れない。FF1のパッケージイラスト(光の戦士を象徴する戦士とオーブの絵)やタイトルロゴの書体デザインは唯一無二のファンタジー性を醸し出し、それまでゲーム業界ではあまり見られなかった芸術的なビジュアルイメージを確立した。
さらにモンスターやキャラクターの原画も担当し、コーネリア王女(サラ姫)やガーランド、各職業のデザイン原案なども天野氏の手によるもの。
当時の開発スタッフたちは大ファンばかりで、天野氏が一度スクウェア社に来社した際には、坂口氏が「ミーハー禁止!サインねだるなよ!」とクギを刺したにも関わらず、石井浩一氏がちゃっかり画集を持ち出してサインをお願いし、それに続いて社内即席サイン会になってしまったという笑い話もある。
坂口氏は苦笑いだったそうですが、「だってあの天野さんですよ? 従えるわけないですよね(笑)」と石井氏は振り返っている。
その後も天野喜孝氏はFFのイメージイラストレーターとして現在に至るまで長年関わり続けている。FF1における天野アートの貢献は、ゲーム音楽における植松サウンドと並び、シリーズのアイデンティティ確立に大きく寄与したと言える。
植松伸夫(音楽作曲)
植松伸夫(うえまつ のぶお)氏は、FFシリーズの音楽を語る上で欠かせない作曲家。彼はFF1が開発されていた1987年前後に正式にスクウェア社員となり、本作の全BGMを手掛けた。
当時27歳だった植松氏は、開発部門で最年長というほど社内が若手だらけだったそうだ。もともと音楽業界志望で、在学中からバンド活動や作曲をしていた植松氏は、一時レコード会社社員などを経て、坂口博信氏との偶然の出会いに導かれてゲーム音楽の道へ進む。
その出会いとは、植松氏がアルバイトしていた都内のレコードレンタル店でのこと。たまたま来店した坂口氏と話すうちに「僕、音楽作曲やりたいんです」と植松氏が語り、当時パソコンゲームを作っていた坂口氏が「じゃあうちのゲーム音楽やってみる?」と誘ったのである。
こうしてファルコムの某作品風アクションゲーム『とびだせ大作戦』で初めてタッグを組み、以降坂口&植松コンビが誕生した。坂口氏曰く「当時から植松の音楽はメロディアスだった」そうで 、FF1でもその才能が遺憾なく発揮されることになる。
ファミコンの音源は同時発音数たった3音+ノイズ音という厳しい制約があった。植松氏はプログラマー(おそらく音楽ドライバー担当の成田賢など)と二人三脚で、他社ゲームの曲を研究しながら作曲を進めたと語っている。
「同じファミコン音源を使っているはずなのに、メーカーごとに音の個性が違うのが面白かった。制限があったからこそ作曲者たちは試行錯誤したのだと思う」と振り返っており、ハードの枠内で最大限の表現を引き出すための創意工夫があったことが伺える。
生み出された曲は、メロディアスで覚えやすく、それでいてゲーム体験を盛り上げる名曲揃いであった。オープニングで流れる荘厳な「ファイナルファンタジー メインテーマ」、各所で耳にする美しい「街のテーマ」や「フィールド曲」、緊張感ある戦闘曲と勝利時の「勝利ファンファーレ」、ラスボス戦の「カオス神殿」、そしてエンディングの感動的なピアノ調BGMまで、どれも後のシリーズ作品や音楽ライブで繰り返し演奏されるレパートリーとなっている。
特に「プレリュード」(Prelude)はFFシリーズを象徴するクリスタルの煌めきをイメージした名曲だが、実はFF1開発終盤になって坂口氏が「タイトル画面が寂しいから今すぐ何か作って!」と無茶振りし、植松氏が30分ほどで即興的に作ったものだという。
植松氏自身「その場しのぎで作ったら、まさか25年も流れる曲になるとは(笑)」と語っており、短時間で生まれたフレーズがシリーズの顔になるという伝説的エピソードとなっている。
FF1の音楽は当時から高く評価され、サウンドトラックはFF2とのカップリングでCDとカセットテープで発売された。ゲーム音楽が単独のアルバムとして発売されるのは珍しかった時代ですが、それだけファンの支持があったということだろう。
また、FF1発売後には思わぬ人物から賞賛を受けている。『ドラゴンクエスト』の作曲家・すぎやまこういち先生の事務所から突然電話がかかってきて「先生(すぎやま氏)が褒めていらっしゃいましたよ。それでは」と伝えられたという。ライバル会社の著名作曲家からの激励に、植松氏は「すごく嬉しかったですね」と感激したそうだ。
以降もすぎやま氏はFFシリーズが出るたびにプレイして感想を伝えてくれ、FF6のオペラシーンの曲については「何も知らないで書いただろう、相談してくれればよかったのに」と冗談交じりに言われたとか (植松氏は「さすがにドラクエの先生に作曲中相談なんてできません(笑)」と返したそうです )。
このように他社の大先輩からも一目置かれるクオリティだったFF1のBGMは、現在も「ゲーム音楽の古典」として世界中で演奏・アレンジされ、愛され続けている。
ナーシャ・ジベリ(メインプログラマー)
ナーシャ・ジベリ(Nasir Gebelli)氏は、FF1~3のプログラムを担当した伝説的プログラマー。先に少し触れたが、彼は米国でアクションゲームや3Dダンジョンゲームを開発して名を馳せた人物で、スクウェアが異例の待遇で契約しチームに迎え入れた。
日本語が堪能でなかったナーシャ氏だが、プログラミングに関しては天才的な腕前を発揮し、FF1の完成に大きく貢献した。
ナーシャ氏の実績としては、戦闘シーンとフィールドシーンの切替処理や、大量のキャラクターデータ管理など、ファミコンでは困難と言われた処理を滑らかに実現したことが挙げられる。
また、彼の遊び心から組み込まれた隠しコマンドがいくつかあります。例えばワールドマップ表示の裏技(フィールド画面でBボタンを押しながらセレクトボタン)や、前述の船上15パズルゲーム(船に乗ってA+Bボタン連打)は、公式には説明されない隠し要素だった。
特に15パズルは、完成させると100ギルがもらえるミニゲームで、後の移植版では景品額が増えたりランキング機能が付いたりしている。これを「RPG初のミニゲーム実装」として評価する向きもあり、当時としては画期的な試みだった。
ナーシャ氏はFF3開発後に母国語圏であるイランへの帰国を機にスクウェアを離れたが、その後も坂口氏とは親交が続いているという。FFシリーズのプログラム技術の基礎を築いた重要人物として、ファンの間でも伝説的な存在となっている。
渋谷員子(グラフィックデザイナー)
渋谷員子(しぶや かずこ)氏は、FF1のドット絵グラフィックを手掛けた女性デザイナー。戦闘画面に表示される可愛らしいキャラクターのドット絵や、モンスター図柄の作成などを担当した。
特にモンスターグラフィックについては天野喜孝氏の原画を基にファミコン仕様で描き起こす作業で、限られたドットと色数で迫力ある敵キャラを表現する手腕は見事であった。
例えばコーネリアを襲う騎士ガーランドや、各地のカオス四天王(リッチ・マリリス・クレイク・ティアマット)のデザインはファミコン作品とは思えない緻密さがある。
またキャラクター側も、ジョブごとに戦闘ポーズが異なり、攻撃や白黒魔法使用時のモーションも描き分けられていた。当時としては贅沢なドット表現で、渋谷氏らグラフィック班の尽力がうかがえる。
渋谷員子氏はその後もFF6まで全ての2Dドット絵を描き続け、「FFドット絵の生みの親」として知られている。現在もスクウェア・エニックスに在籍し、FFのドット絵リマスター監修などで活躍している。
FF1の時点ではクレジット上あまり目立たない存在だったが、彼女がいたからこそプレイヤーは自分のキャラに愛着を持てたと言っても過言ではない。
田中弘道(アシスタントプロデューサー/デザイナー)
田中弘道(たなか ひろみち)氏は、坂口氏の大学時代からの友人であり、スクウェア創業メンバーの一人。FF1では明確な肩書きはないものの開発途中からサポートに入り、ゲームバランス調整やテストプレイなどを担ったようだ。
実際、坂口氏と共にウルティマやウィザードリィに熱中した仲であり 、RPG制作のモチベーションを共有していた。
田中氏はFF3でディレクターを務め、シリーズ屈指の名作と名高い同作を成功させた。その後、『聖剣伝説』や『ゼノギアス』プロデューサーを経て、FF11オンラインのプロデューサーとしてFFシリーズに復帰。
オンラインRPGでFFブランドを新境地へ導いた立役者でもある。FF1時点では裏方ポジションだったが、田中氏の存在もまたスクウェア開発陣の底力の一部であったと言える。
以上のように、FF1の開発には才能豊かなメンバーが集い、それぞれが後のゲーム史に名を刻む活躍をしている。
25歳前後の若者たちが情熱でもぎ取った成功が、今日のFFシリーズの礎となったのである。

第5章:社会・業界への影響:スクウェア復活とRPG黄金時代の幕開け

FF1がゲーム業界に与えた影響は計り知れない。ここでは発売当時の反響やスクウェア社へのインパクト、そしてRPGジャンル全体への貢献について見て行こう。
スクウェアの再起:社運を賭けて掴んだ大ヒット
発売前、坂口博信氏ら開発陣は「自分たちなりに納得のいくゲームができた」という手応えを感じていた。しかし市場がどう受け止めるかは未知数。
1987年12月18日、ついにFF1がリリースされると、徐々に口コミで評判が広がり、年末商戦も手伝って販売本数を伸ばして行った。
当初の出荷はそれほど多くなく、約40,000本程度だったとも言われているが、品切れ店が続出し追加発注がかかる。最終的に国内出荷本数は52万本、スクウェアの発表によれば1994年までに累計60万本販売に達したとの記録がある。
この数字は当時のファミコンRPGとしては『ドラゴンクエストII』(約150万本)などに次ぐヒットで、「無名の新規RPGが50万本」という快挙は業界を驚かせた。
売上だけでなく内容面の評価も上々だったという。ファミコン専門誌のクロスレビューでは「映像面が素晴らしい」「音楽が美しい」とグラフィック・サウンドに賞賛が集まり、他方「レベル上げに時間がかかる」「魔法の回数制限が厳しい」といった難易度への指摘もあった。
しかし総じて「ファミコン屈指の完成度を持つRPG」との評価が定まり、今日では「ファミコンにおける最も影響力があり成功したRPGの一つ」と位置付けられている。当時まだRPGというジャンル自体が家庭用ゲーム機では新しかった中、FF1の成功はRPG市場をさらに拡大させる一因となった。
何より、このヒットでスクウェア社は一躍トップクリエイター集団の仲間入りを果たす。発売前は倒産の危機すら囁かれた同社が、FF1のヒットによって経営的にも大きく持ち直した。
1988年には早くも続編『FF2』を開発・発売し、こちらも前作を上回る売上を記録。以降も年1作ペースでFFシリーズを展開し、1990年代にはスクウェアは「RPGのスクウェア」と呼ばれるブランドイメージを確立して行く。まさにFF1はスクウェアにとっての救世主であり、同社の看板タイトルとして未来を切り開いたのである。
RPGジャンルへの貢献と他作品への影響
FF1は、同時期の他RPG(特にドラゴンクエストシリーズ)と切磋琢磨しながら、コンピュータRPGの発展に貢献した。ドラクエが示した「わかりやすく親しみやすい国産RPG」の道筋に対し、FFは「ビジュアルとサウンドに優れ、戦略性と物語性を高めたRPG」という新たな価値を提供した。
例えばパーティ制と職業選択、乗り物による探索の自由度、演出面のリッチさ(戦闘画面でのキャラ表示やエフェクト)などは、以降の多くのRPG作品が取り入れていった。
また、クリスタルや飛空艇、ジョブチェンジといったFF独自の要素はシリーズ内のみならず他社作品にも影響を与えている(クリスタル=世界の調和を司るもの、という設定は後のRPGのお約束の一つとなった)。
ゲーム音楽の分野でも、植松伸夫氏の仕事は後続に多大な影響を与えた。FF1発売翌年の1988年には、早くもすぎやまこういち氏指揮による「ファミリークラシックコンサート」にてFFの曲が交響アレンジで演奏されるなど、ゲーム音楽コンサートのレパートリー入りを果たしている。
ストーリー面でも、FF1の時間ループを題材にしたシナリオは当時として斬新だった。ゲーム終盤まで伏せられたガーランド=カオスのタイムパラドックスは、多くのプレイヤーに驚きをもって迎えられ、「ゲームでここまで凝った物語を描けるのか」と評価された。以降のFFシリーズや他RPGでも、時間ものやパラレルワールドの設定が登場することが増え、FF1はその草分け的存在と言える。
さらにFF1の成功は、スクウェアのみならず同業他社にも刺激を与えました。エニックス(現スクウェア・エニックス)は言うまでもなく、ナムコ(『テイルズオブ』シリーズ)やカプコン(『ブレスオブファイア』シリーズ)など、90年代には各社が本格RPG開発に乗り出す。
コンシューマーRPGの市場が広がり群雄割拠の黄金時代が訪れた一因に、FFシリーズの台頭があったことは間違いない。FF1がもたらした「RPGはビジュアルや音でも魅せるエンターテインメントだ」という概念は、その後のゲーム作りの潮流にも影響を与えた。
シリーズの発展と国際的成功への礎
FF1はその後のFFシリーズ発展の礎となりました。続編のFFII(1988年)、FFIII(1990年)とファミコンで3作が生まれ、いずれもヒット。1990年代に入るとスーパーファミコンでFFIV~VIが発表され、FFはドラクエと並ぶ国民的RPGシリーズに成長する。
特に1997年発売のFFVIIはPlayStationプラットフォームで世界的メガヒットを記録し、FFブランドをグローバルなものへ飛躍させた。そうした大躍進の始まりに、FF1が果たした役割は大きい。
海外展開に目を向けると、FF1は1980年代当時、日本国外のファンにも知られる存在となっていた。任天堂オブアメリカは1989~1990年にFF1を英語ローカライズし、海外版ファミコン向けに北米で発売している。
これはエニックスが『Dragon Quest』(北米名:Dragon Warrior)をローカライズ発売した成功を受けてのもので、任天堂自らパブリッシャーとなりFF1を紹介した。北米版FF1は日本版に比べ若干バランス調整が施され、任天堂の定める検閲ポリシーにより宗教的表現(例えば教会の十字架マークなど)が差し替えられるなどの変更があった。
しかしゲーム内容は概ねそのままで、多くの米国プレイヤーがファンタジーRPGの魅力に触れる機会となった。売上も北米で約70万本程度と、日本とほぼ同程度に健闘したと言われる。欧州(PAL地域)では残念ながら当時FF1の発売がなく、公式にプレイできるようになるのは2003年のPlayStation版『Final Fantasy Origins』(FF1・2合同リメイク版)が初だった。
FF1以降、シリーズ作品の多くが海外展開され、FFは世界的なRPGシリーズとしての地位を確立して行く。そして2020年代現在までにナンバリングは16作(+スピンオフ多数)を数え、2022年にはシリーズ累計販売本数が2億本を突破したと報じられた(※パッケージ出荷とDL販売の合計) 。
その偉大な歩みも、一作目が成功しなければ成し遂げられなかっただろう。坂口博信氏も「FF1がなければ自分はゲーム業界にいなかった」と公言するほどで、スタッフ・ファン双方にとってFF1は特別な起点と言える。
第6章:裏話・トリビア:知られざるエピソード集
最後に、FF1にまつわる細かな裏話や逸話の数々をご紹介して行く。バグや没要素、ユニークな仕掛けや当時のちょっとした事件まで、読むとさらにFF1通になれるネタ集。
「知性」ステータスの謎
FF1には各キャラの能力値として「力」「素早さ」「体力」「知性」「幸運」などがあるが、このうち「知性」(ちせい)はまったく意味をなさない珍現象があった。
本来は魔法威力や魔法防御に影響するパラメータとして設定されたはずだが、ファミコン版ではバグで機能していなかったのである。
そのため知性が高い黒魔道士でも低い赤魔道士でも、同じ魔法を唱えればダメージが変わらないという事態に…。マニュアルにも知性の説明はなく、当時のゲーム雑誌でも「魔法効果に関係するらしい」と曖昧に書かれていた。
リメイク版(WSC版以降)では修正され、知性が高いほど黒魔法の威力が上がるように改善されている。
機能しない魔法と武器特効
上記の知性バグ以外にも、FF1に上記の知性バグ以外にも、FF1には一部魔法や属性効果が無効という不具合があった。
代表的なのが黒魔法「デスペル」と白魔法「ストライ」そして強化魔法「セーバー」。これらは本来それぞれ「敵の強化効果解除」「味方への雷防御付与」「自分の攻撃力アップ」といった効果を持つはずだが、実際には何も起こらない。
プログラム上で効果処理が抜け落ちていたためで、プレイヤーからするとMP(正確には使用回数)を無駄にするハズレ魔法だった。
また武器に設定されていた「◯◯系にダメージ倍」などの特効属性も全く機能せず、せっかくゾンビに効く聖なる武器を持ってもダメージは普通…という具合だった。
これらも後のリメイクで軒並み修正され、ようやく本来の威力を発揮するようになる。
隠れミニゲーム
既に触れた船の15パズルは、当時プレイした人なら有名な裏技だった。船入手後、船上でAボタンを押しながらBボタンを素早く55回連打すると画面が切り替わり、数字パネルをスライドさせて順番に並べる15パズルゲームが始まる。
制限時間内にクリアすると100ギルがもらえ、何度でも挑戦可能。ファミコン版ではお小遣い程度の額だが、リメイク版では賞金が桁違いに増えたり、タイム短縮にやり込み要素を持たせたりと発展していった。
「RPGにミニゲーム」という発想は当時新鮮で、以降FFシリーズではチョコボレースやカードゲームなど様々なミニゲームがお約束になっていく。その原点がこの15パズルである。
冒険のヒントはほうきが教える?
マップ表示の隠しコマンド(B+セレクト)は取扱説明書にも載っていない裏技だったが、実はゲーム内でそれとなく示唆されている。
序盤に訪れる魔女マトーヤの洞窟にいるほうき(箒)のキャラクターに話しかけると、意味深な呪文めいた言葉を喋る。実はこれ、文字を逆から読むとBボタンを押しながらセレクト(Select)となっており、隠しコマンドを教えてくれていたのである。このユーモア溢れるヒントの出し方もFFらしい遊び心である。
初回出荷版だけの折り鶴伝説
FF1の初回出荷分(いわゆるROMカセット版の初版)には、製品パッケージの中に一枚の「おしらせ」ペーパーが同梱されていあ。内容はゲーム上の注意事項だったようですが、なんとその束の中に1枚だけ、坂口博信氏が折った紙の折り鶴が紛れていたという逸話がある。
坂口氏がユーモアで忍ばせたものなのか、お守り代わりだったのか定かではありませんが、「もしかしたら自分の買った箱に入っていたかも?」と想像するとロマンがある。現在この折り鶴を手にしたという報告は聞きないが、もし保管している人がいればとても貴重なコレクターズアイテムになるだろう。
MSX2移植版の存在
実はFF1はファミコンだけでなく、MSX2という当時の日本製パソコン向けにも移植されている。発売は1989年12月で、開発・販売はスクウェアではなくマイクロキャビンという会社が担当した。
MSX2版は媒体がロムカセットではなくフロッピーディスクになったため、容量はファミコン版の約3倍に増強された。そのおかげでグラフィックや音楽がやや強化され(戦闘背景の追加やFM音源対応など)、一見パワーアップ版のようにも思える。
しかし致命的な弱点があった。それはディスクアクセスによるロード時間。ファミコンはROMゆえロードなしだったが、MSX2版は何をするにもカリカリと読み込みが発生し、特にエンカウント→戦闘突入までの待ち時間が長いことで評判が悪かった。
結局MSX2版FF1は商業的に振るわず、日本国内のPCゲーム市場が縮小していったこともあり、FFシリーズは以降コンシューマ専業となる。現在ではこのMSX2版は幻の移植作として一部で語られるのみだが、ファミコン版との微妙な違い(例:BGMのアレンジや一部アイテム名称変更など)を比較してみるのもマニアには興味深いポイントである。
その他小ネタいろいろ
FF1には他にも挙げればキリがないほど小ネタがあります。例えば「ビッグアイ」という一つ目モンスターを倒すと500以上という破格の経験値が手に入りレベル上げに重宝するとか、アイテム「テント」は実は戦闘中にも使用でき、使うと即座に全滅扱いになる(開発用デバッグ機能の名残?)とか、一部の魔法名は容量不足でカタカナ4文字制限となり「デジョン」が「デジョ」「ケアルラ」が「ケアル2」表記になっている等々。宗教的理由で海外版では「HOLY(ホーリー)」魔法が「FADE」に改名されたり、街の教会が「Clinic(くりにっく)という無宗教風施設に差し替えられたりしたのもローカライズ時代ならではのネタである。
こうしたディテールに注目してみると、当時のゲーム開発事情や文化の違いが垣間見えて面白い。
第7章:BGMの魅力:8bit音源に刻まれた永遠のメロディ
前述した通り、FF1の音楽は植松伸夫氏の手による珠玉の名曲揃い。ファミコンの3和音+ノイズという制限の中、植松氏は数々の印象的なメロディを作曲し、本作を彩った。その魅力を改めて紐解いてみよう。
限られた音色で紡がれた豊かな音楽
ファミコンの音源仕様は矩形波2音、三角波1音、ノイズ1音、DPCM1音というもので、同時に使える旋律は実質3つまでだった。
この制約下、植松氏は旋律・和音・リズムの取捨選択を迫られます。例えば「メインテーマ」では、三角波でうねるようなベースラインを奏でつつ、2本の矩形波で分厚い主旋律と内声を表現している。
限界までポリフォニックに聞こえる工夫で、広大な世界を旅する高揚感を演出した。また「戦闘シーン」の曲では、矩形波の鋭い音色を活かし緊迫したリフを刻み、三角波の重低音ドラムで鼓動を表現するなど、シンプルな音ながら迫力十分。
注目すべきは、当時の他社タイトルと比べてもFF1の音楽は格段に音が良い点。植松氏自身も「同じPSG音源を使っているのにメーカーによって個性が違う」と語っているが、FF1では音色エンベロープの工夫やノイズチャンネルの的確なドラム使用など、技術面でも洗練されていた。
他社の有名作曲家(古代祐三氏など)の作品を聴いて刺激を受け、「負けない音を作ろう」と研究したというエピソードもある。制約があるからこそ研ぎ澄まされた作曲・編曲が行われ、それが逆に8bitサウンドならではの魅力を生み出している。
名曲ギャラリー:プレリュードからファンファーレまで
ここで、FF1を代表するいくつかの楽曲について触れてみよう。
- プレリュード
- タイトル画面などで流れる透明感あるアルペジオ曲。前述の通り30分で作られたとは思えない完成度で、ゆったり上下する分散和音がクリスタルの輝きを連想させる。
- 以後、全てのナンバリングタイトルで何らかの形で使われており、今やFFの代名詞的な一曲と言える。
- メインテーマ(メインタイトル)
- オープニングデモ(ブリッジを渡った後のスタッフロール)やエンディングで流れる壮大なテーマ。冒頭のファンファーレ風モチーフから美しいメロディへ展開し、冒険心を掻き立てる。
- FFシリーズ序盤~中盤のフィールド曲としても使われ、FF4以降はエンディングテーマに編曲版がよく登場する。
- マトーヤの洞窟
- 序盤に訪れる魔女マトーヤの洞窟で流れるコミカルな曲。軽やかなリズムに木琴のような音色が特徴で、植松音楽の引き出しの広さを感じさせる。後年コンサートでも演奏され人気の高い一曲です。
- 戦闘シーン
- 通常戦闘の曲。短いループながらイントロの緊張感あるフレーズと、展開部の疾走感が秀逸。
- FFシリーズのバトル曲は本作から毎回ファンの注目を集める要素となったが、その原点がこの曲です。勝利後にはお馴染み「勝利のファンファーレ」が流れ、経験値獲得の喜びを盛り上げる。
- このファンファーレも以降のシリーズで不変のモチーフとして踏襲されている。
- カオス神殿
- ラストダンジョンおよびラストボス戦で使われる曲。荘厳かつ不気味な雰囲気を湛え、三角波ベースが刻む不協和音が不安感を煽る。
- カオス4体連戦~ラスボス・カオス戦まで続く緊張の局面に彩りを添え、当時の子供たちにトラウマ級の印象を残した。
- エンディング
- ラストバトル後、エピローグからスタッフロールにかけて流れる組曲的な曲。序盤は静かなピアノ調で始まり、やがて歴代フィールド曲の旋律(メインテーマ)が壮大に再現され、最後はプレリュードに戻って物語を閉じる。
- 8bit音源とは思えない多彩な表現で、エンディングの感動を演出した。
これら以外にも、町や城のテーマ、ダンジョン各種、飛空艇入手時のちょっとしたジングルなど、全曲挙げたいほど魅力的な楽曲ばかり。FF1のBGMは後のアレンジアルバムやオーケストラコンサートでも取り上げられ、ゲーム音楽の金字塔として評価されている。
植松伸夫氏は2020年代に入った現在も精力的に音楽活動を続けており、FF1から数えて35年以上にわたってファンを楽しませてくれている。
植松氏は「制限の中で作ったファミコン音楽があったからこそ、作曲者は工夫を凝らした」と述懐しつつ、技術が進歩した今も心に残るメロディの大切さを説いている。FF1の音楽はまさにその信条を体現するような、シンプルだが心に響くゲーム音楽だった。
第8章:その後のエピソード:リメイク・復刻と受け継がれる伝説
FF1は発売後も様々な形でリメイクや移植が行われ、新しい世代のファンにもプレイされ続けている。その過程で追加要素や変更点も生まれていますので、最後に復刻版の歩みと特徴を簡単に振り返ってみよう。
- 1994年:ファミコンカセット復刻版
- FF1とFF2を一本にまとめた『ファイナルファンタジーI・II』が、スクウェアから限定生産で発売された。中身はファミコン版の完全そのままだが、両面イラスト仕様のスペシャルパッケージで、当時入手困難だった2作を遊べるとあってファンに喜ばれた。
- 1989年:MSX2版
- 先述の通りマイクロキャビンからMSX2移植版が発売 。グラフィックが一部描き直され戦闘背景が追加されたが、ロードの長さなどから評価は芳しくなかった。
- 2000年:ワンダースワンカラー版
- 2002年:PlayStation版
- FF1とFF2をカップリング収録した『ファイナルファンタジー オリジンズ』がPS向けに発売 。基本的にはWS版準拠の内容だが、CGムービーの追加、サウンドのアレンジ録音(PSG音源曲の忠実な強化版) 、美術ギャラリー、おまけダンジョンなどが盛り込まれた。
- また、ゲームバランス面では「イージーモード」が選択可能となり、経験値やお金が多めにもらえる・魔法使用回数が増える等の初心者向け調整も行われている。
- 2004年:ゲームボーイアドバンス版
- 任天堂の携帯機GBA向けに、再びFF1・2同時収録のリメイク版を発売。PS版をベースにしつつ、FF1には新ダンジョン「ソウルオブカオス」が4つ追加された。各ダンジョンには過去シリーズのボスが登場するファンサービス的内容で、やり込み要素となっている。
- 難易度は全体的に下がり、特に魔法がMP制に変更され(使用回数システムは廃止)たため、遊びやすくなった。またセーブもフィールド上どこでも可能になり、現代風の快適設計になっている。
- 2007年:PlayStation Portable版(20th Anniversary)
- 2010年代:スマートフォン版・レトロ配信
- iMode携帯アプリやスマホ(iOS/Android)にもFF1は配信され、いつでも遊べるようになった。内容は概ねPSP版準拠。
- またWiiや3DS向けのバーチャルコンソールでFC版がそのまま配信されたこともあり、オリジナル版を手軽に楽しむ機会も提供された。
- 2021年:ピクセルリマスター版
- 最新のリマスター企画として、FF1~6を当時の雰囲気そのままに刷新する「Pixel Remaster」シリーズが始動 。FF1も2021年7月にPC・スマホ向けに配信され、2023年にはNintendo Switch/PS4向けにも発売されました。
- 特徴はドット絵の美麗化(キャラ描き直し+滑らかなスクロール等の実現)とBGMの生演奏アレンジです。UIも現代風に洗練され、ミニマップ表示やオートバトル、モンスター図鑑など便利機能が追加されている。
- 難易度は原作準拠だが、経験値倍増などのオプションは無く、比較的オリジナルのバランスに忠実。
- ピクセルリマスター版は「フォントが見づらい」といった議論も起こったが、その後アップデートでドット風フォントが選択可能になるなど改善された。
- 「昔ながらの2D FFを今プレイするならこれ」という決定版的位置付けになっている。
このようにFF1は数多くのハードで繰り返しリメイク・移植され、その都度新しいプレイヤーを獲得してきた。
中には「親子二代でFF1を遊んだ」というファンもいるそうで、植松伸夫氏も「お父さんが子どもの頃遊んだタイトルを息子さんがリメイク版で遊ぶと聞くと嬉しいですね」とコメントしている。
1987年のオリジナルから実に世代を超えて楽しめる作品となったFF1。その普遍的な面白さと魅力が、時を経ても色褪せない証と言えるだろう。
最後に:光はまだ、ここから生まれ続ける
「もしこのゲームが売れなければ、私たちはこれで終わりだ」――そんな覚悟から始まったFF1。だが結果として、それは『終わりではなく始まり』だった。数々の続編・派生作品・リメイクを経て、今なおシリーズは輝きを増し続けている。
そしてその原点たるこの作品は、決して過去の遺物ではない。今日でも、私たちはそのシステム、物語、そして開発者の挑戦から学び、感動を受け取ることができる。プレイヤーとして、クリエイターとして、物語紡ぎとしても。
旅の幕は閉じたかもしれないが、クリスタルの輝きは今も世界に灯り続けている。四人の戦士たちを動かしたあなたの決意、そして冒険心は、きっと忘れられない。
今、この文章を閉じる前に、あなた自身の『光の戦士』としての名前を思い出してほしい。そして、もう一度コントローラを手に取り、あの町の門をくぐろう。世界があなたを待っている。
――「光は、まだここから生まれ続ける」