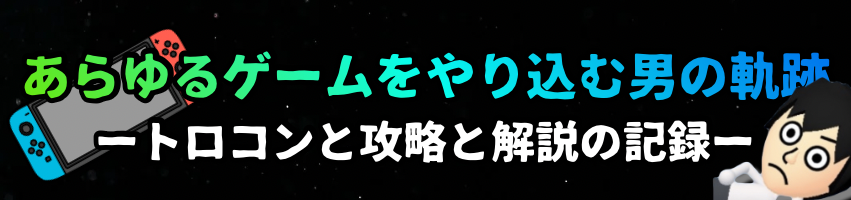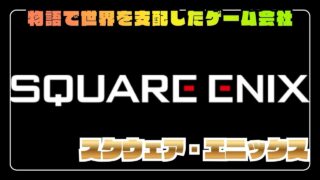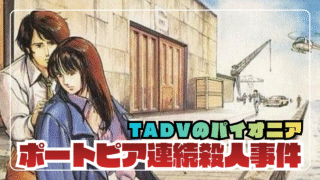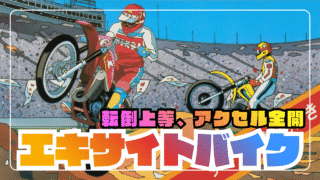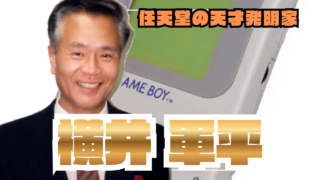ゲームボーイが発売されたあの頃、僕たちのポケットには“夢”と“単三電池”と、なぜか“役満”が入っていた。
――もちろん麻雀牌じゃなくて、ゲームボーイ版『役満』のことだ。
白黒の液晶画面。豆粒みたいな牌。リンクケーブルという謎の紐。今思えば制約だらけの環境だったのに、それでもこの一本は「どこでも雀荘」を実現してしまった。
当時の少年たちは、休み時間になるとランドセルの下でこっそりツモり、通信ケーブルを挿しては「立直(リーチ)!」と無言の熱戦を繰り広げていたのだ。(小学生がそんなことするかっ!!!笑)
携帯機で麻雀?しかも役満狙い?
そんな無茶を当たり前のように実装してくれた開発者たちの情熱には、今になってじわじわ感動すら覚える。
本記事では、ゲームボーイ版『役満』のシステム、魅力、そして当時ならではの裏側を、ちょっとした笑いも交えながら徹底的に振り返っていく。
『ポケットの中の雀荘』がどんな風に誕生し、どんなふうに私たちを夢中にさせたのか――その真相を紐解いていこう。(さっきからポケットの中の雀荘ってなんやねん)
GB版『役満』とは?

- 発売日:1989年4月21日
- 開発:インテリジェントシステムズ
(Intelligent Systems) - 発売:任天堂(Nintendo)
- 価格:2,600円
- プラットフォーム:ゲームボーイ/Nintendo Switch
- ジャンル:テーブルゲーム/麻雀
- プレイ人数:1人用+2人対戦(通信ケーブルによる)
はじめに:なぜ「役満」か?
まずタイトルから。「役満(やくまん)」とは麻雀(日本式麻雀)における最高得点級の役、要するに「ビッグレイズ」「マックスボーナス」な役どころである。本作もその名前を冠しているのだ。
本作は任天堂より発売され、開発はインテリジェントシステムズが担当。発売日は1989年4月21日、日本国内版。GBが同じ日に発売されたローンチタイトル群の一つでもある。
麻雀ゲームというと、テレビに繋いだ据え置き機で4人打ち・多人数が定番だが、本作は携帯ゲーム機で麻雀を遊ぶという新しい環境の中で、しかも2人打ち(1人用CPU対戦&2人対戦)というスタイルを採っていた。
いわば「どこでも麻雀、誰とも麻雀(ただし2人まで)」という宣言めいたものがある。
この背景には、GBというハードおよびその通信ケーブル機構が密接に関わっており、「通信対戦できる麻雀」という当時としてはかなり意欲的な試みがなされていた。
「ポケットに入れたラス牌をツモるぜ!」といったノリである。(意味がわかりません)
ではまず、システム面を丁寧に見て行こう。
システム解説:ゲームの中身を紐解く

プレイモード/対戦相手
本作のモード構成としては大きく次の2つ。
- 1人用(CPU雀士5人から対戦相手を選択)
- 2人用(2台のGB+同じソフト+通信ケーブルで対戦)
CPU雀士の個性付けもなされており、ただ「牌を切るだけ」ではなく、相手によって手筋・鳴き頻度・リーチの挙動が変わる構成になっている。
例えば「役満仙人」という超インチキキャラクターが登場し、名前の通り『役満を狙う』という非常にハイリスク・ハイリターンなCPU。
しかもかなりの頻度で揃えてくるという、、、。
ルール設定(カスタムオプション)
本作では対局前に細かくルール設定が可能。
これが初心者向けではなく、かなり麻雀ルールに詳しいユーザー向けに「ちょっと変則のアリ・ナシも選べる」仕様になっており、当時としては実にマニアック。
- 喰いタン・後付けあり(クイタン・アトヅケ)かどうか
- フリテン・リーチありかどうか
- ノーテン親流(親がテンパイしていないと流れる)かどうか
- 南入(東南戦)ありかどうか
- ツモ・ピンフ(いわゆるピンフ・ツモ和了)を認めるかどうか
- BGMあり/なし
これだけ選択肢があるというのは、「携帯麻雀ゲームでもある程度本格的に遊べる」ことを示しており、当時のハード性能や画面の制約を超えて「麻雀らしさ」を追求していたと言える。
「ポケットサイズでエキスパート仕様」みたいなやつである。
ゲーム進行と操作
操作系統としては、GBの十字キー+A・Bボタン+スタート・セレクトボタンという従来スタイルを踏襲しつつ、麻雀牌の操作に最適化されている。
例えば、牌を選択して捨てる、ポン・チー・カン・ロン・ツモというコマンド選択、など。
画面はモノクロ小画面ながら、必要な情報(手牌、河、捨て牌、点数表示など)はきちんと収められており、「携帯で麻雀やってる」という実感があった。
特に「2人対戦」時には通信ケーブルを用いた別々の画面で同時プレイが可能という点が、当時としては斬新だった。
ちなみにこの通信機構がGBの将来タイトルである ポケットモンスター赤・緑 の交換・対戦機構の先駆けになったとも言われている。
点数・勝利条件・仕様の特徴
本作の麻雀は2人打ち仕様であるため、一般的な4人打ちのルールと若干異なる点や簡略化された点がある。主な仕様を以下に列挙して行く。
- 初期持ち点30000点スタート。
- 箱テン(ハコ割れ)による飛び(トビ)は無し、0点未満もマイナス点として扱われる仕様。
- 役満の複合(たとえば複数の役満役を同時に成立させる)を認めるが、得点計算は「シングル役満」で打ち止め。つまり複合しても役満1つ分の扱い。
- 「喰い平和」による20符1飜、五対子(七対子)50符1飜など、少々変則的な符・翻体系が採られている。
- オーラス親あがり止め無し。喰い替えあり。振聴(フリテン)立直・後付けなど細かい設定がオン・オフ可能。
- CPUキャラクター毎に鳴きの傾向・立直傾向・手作りのスタイルが分かれており、相手によって戦略が変わる。
このように、ただ「牌を揃えてロン!」というだけではなく、「どのルールをオン・オフにするか」「敵の性格を見て手を作るか降りるか」を考えさせられる構造になっている。
「役満仙人が速攻で役満を狙って来る…いやマジで!?降りるしかねえ!」という緊迫感も当時のプレイヤーは感じていたのではなかろうか。
UI/画面構成・制約
GBという携帯機での開発のため、当然画面・メモリ・操作系・音響などの制約が存在した。
- モノクロ表示(カラーではない)である為、視認性を高めるために牌の模様・数字/字牌の判別を工夫してある。ユーザーからは「画面が小さいから少し見づらい」という声もあったという。
- 通信対戦対応という点で、2台間の同期や牌の流れ・捨て牌の反映遅延など最適化が必要だった。
- 時間制限は無く、じっくり考えて打てる仕様。
- 操作は「牌を選ぶ→捨てる・鳴く・リーチ」などのコマンド式。直感主義ではなく、少し考えて打つ麻雀らしい手応え。
こうした制約と工夫によって、GBという限られた環境でも「麻雀を遊べる」だけでなく「麻雀らしさを感じられる」ものに仕上がっていたと言える。
開発秘話・背景:意外と深い話

開発元とハードの関係
本作の開発を担当したインテリジェントシステムズは、任天堂との深い関係を持つ開発会社。
また、ゲームボーイ自体は横井軍平氏や岡田敏氏らが主導した携帯機プロジェクトで、通信機能を備えていた。
実は、リンクケーブルという機構をGBに正式に備えさせる一因として、1983年発売のコンピュータマージャン役満(任天堂電子ゲーム)が、2台接続の麻雀対戦機構を備えていたという流れがある。
つまり、この「麻雀×通信ケーブル」というテーマには任天堂内でも古典からの流れがあったのだ。 「麻雀牌を手から手へ、ケーブル越しに渡す時代が来るとは…」と感銘を受けた人もいたことだろう。
また、本作がGBローンチタイトルの一つであったこともポイント。ゲーム機が「どこでも遊べる携帯機」になる時、そこで誰かと繋がって遊べるという機能を実現したかったという意図も読み取れる。
実際、「本作はGBのリンクケーブル機構を活かしたタイトル」だと位置づけられている。
よって、開発側としては「携帯機で麻雀ができる!しかも友だちとケーブルで対戦できる!」という新しさを打ち出したかった説がある。
“役満”というブランドとシリーズ化
「役満」は、実は任天堂が1964年から展開する麻雀牌ブランド名としても使用されており、麻雀ゲームソフトとしての展開も行われている。
本作は「役満」シリーズの第1作目として位置づけられており、その後にも 役満 天国(ファミリーコンピュータ)、役満アドバンス(ゲームボーイアドバンス)と続いて行く。
つまり、「ポケットに麻雀を」「麻雀=役満ブランド」を携えての展開だったのだ。
ローンチとしての意義と挑戦
GBの発売初期において、ゲームボーイ本体の普及と同時にソフトが注目される必要があった。
麻雀ゲームというのは万人受けというよりは麻雀好き向けという側面が強いジャンルだが、GBという新ハードの魅力を携帯+対戦で示すという意味では、本作はかなり意欲的な選択だった。
通信ケーブルを使って2人対戦ができるという本機能を早期に活かしたタイトルのひとつであり、その意味でハードの機能紹介という役割も持っていたと思われる。
加えて、画面も操作もかなりシンプルに整えられており、携帯機ならではの手軽さを追求している。実際、レビューなどでは「いつでもどこでも麻雀できるぞ!」という趣旨で紹介されている。
実は俺がめちゃくちゃ幼い頃、親父が買ったソフトが家にあった、、、、、。
もちろん、画面の小ささやモノクロ表示、2人打ちという仕様は完全な麻雀体験ではなく、あくまで携帯機向けに最適化されたものではあるが、その割り切り・挑戦は開発時点で評価されうるものである。
開発中の“ちょっとした逸話”(想像含む)

公式に語られている細かい開発秘話は多くは残っていないが、いくつか読み取れるポイントがある。
- CPU対戦相手の個性付け
- 5人の対戦相手(「キマジメ太郎」「ヤミノ半蔵」「リーヅモ姫子」「泣きのジョー」「役満仙人」)がそれぞれ異なる打ち筋を持ち、「ただ強いだけ」ではなくキャラクター性も表現されている。このあたり、開発側が麻雀を知ってる人に向けて面白く作ろうという意思を持っていたと言える。
- この記事を書く前に筆者は本作を5時間ほど遊んだのだが(笑)、ヤクマンセンニンだけは許さん。
- パッケージ・表現上のミス
- 本作の初期バージョンでは、パッケージイラストに役満仙人が多牌(15枚目の牌をツモっている)してしまっているというミスがあったとのこと。後に修正されたとか?
- つまり、「えっ、その仙人、手札多くない!?」というギャグみたいなミスもあったわけで、発売当時に気付いた人は「役満仙人、多牌で役満どころじゃない!」と突っ込んだかもしれない。
- 対戦機能の同期・通信負荷
- リンクケーブルを使った対戦仕様は、GBとしては初期段階であり、通信安定や同期処理などのプログラム的な難しさがあったと類推できる。
- 特に麻雀という「山から牌を引く」「捨て牌を相手が見る」など情報共有が発生するゲームでは、遅延や誤差が目立ちやすいからである。開発側としては「携帯+通信」でどう快適に遊ばせるかが課題だったと思われる。
- モノクロ・小画面への対応
- 牌の字柄や捨て牌の表示、河の見やすさなど、ハード的制約(画面解像度・色数)に合わせたUI設計が求められたはず。
- レビュー記事で「画面が小さい、牌識別が少々難しい」という声もあったことが示している。
- 変則ルールの充実
- 冒頭に書いたように、ルール設定を細かくすることで麻雀好き向けにも満足できる作り込みをしている。
- これには開発側が「ただ遊べる」だけでなく「本格的に遊べる」仕様を目指した意図が感じられ、GBという新ハードで“ミニ卓オンザゴー”を実現しようとした意欲が見える。
売り上げ・評価・その後

本作は国内で128万本を売り上げたと言われている。
麻雀ゲームというジャンルで携帯機向けに出された初期作品としては相当な数字と言える。いや、むしろ「携帯機で遊べる麻雀が当時いかに革新的だったか」が分かる。
また、ローンチタイトルとしても意味があり、「対戦できる携帯ゲーム機」というGBの特徴を象徴する一本だった、という位置づけもできる。
その後、「役満」シリーズは継続され、ファミコン/GBA/DS/Wii/WiiU/3DSなど様々な機種で展開されており、本作がその原点にあたるという意味でも重要。
ちなみに、現在では 役満 鳳凰(Wii U/3DS)が最後のシリーズ作品になっている。
最後に

ゲームボーイ版『役満』は、白黒の小さな画面と限られたボタン操作の中で、麻雀という奥深いゲーム性を驚くほどしっかり再現していた。
もしあなたが当時を知っているなら、きっとあの独特の緊張感を思い出したはずだし、初めて知った人なら、携帯ゲーム史のはじまりにこんな挑戦的なタイトルがあったことに驚くはずだ。
どれだけ技術が進んでも、あの頃の「ポケットから取り出す雀荘」のワクワクや、シンプルだけど頭に残るBGMは、妙に忘れられないしつこさがある。(しつこいって言っちゃったよ)
これを機に、久しぶりにあの一本を手に取ってみるのも悪くない。
役満を狙う楽しさは、時代が変わっても、きっと変わらないはずだ。