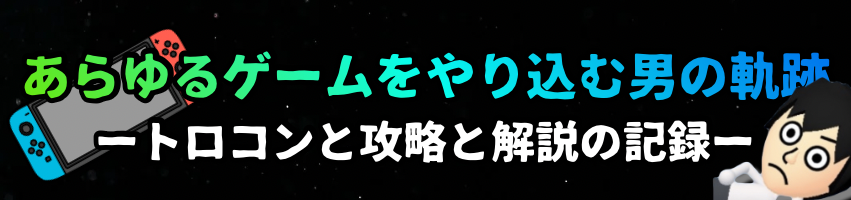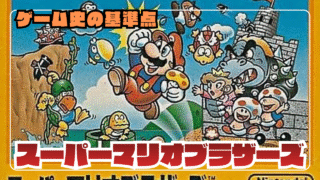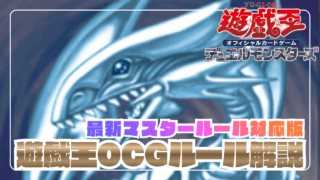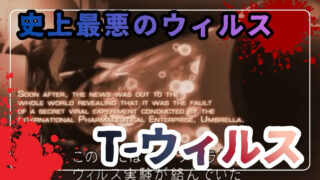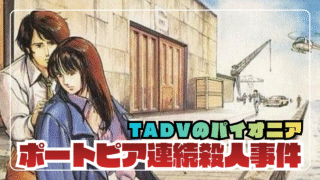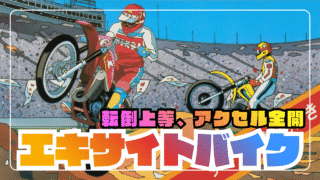RPG──ロールプレイングゲーム。
このジャンルほど、「人によって思い浮かべる世界が違う」ゲームはない。
ある人はドット絵のフィールドを駆け回った少年時代を思い出し、ある人は自由度の高いオープンワールドで何十時間も寄り道した日々を語ることだろう。そして今まさに、オンラインで仲間と冒険しているプレイヤーもいるはずだ。
しかし、この冒険の原体験とも言えるRPGは、実は紙と鉛筆とダイスから始まった。
1970年代のテーブルトークRPGに端を発し、家庭用ゲーム機やパソコンへ移り変わり、やがてJRPG・CRPGといった地域性豊かなスタイルが生まれ、現在ではオープンワールドやオンラインRPG、さらにはモバイルゲームへと進化を遂げている。
RPGは単なるゲームジャンルではない。
「物語を体験すること」
「キャラクターを育てること」
「世界に自分の選択が刻まれること」
こうした『ゲームの本質的な楽しさ』の多くが、RPGから広まった。
本記事では、そんなRPGの長い歴史をたどりながら、
- どのようにしてこのジャンルは生まれたのか
- なぜここまで人々を魅了し続けるのか
- 現代のRPGはどんな方向へ進もうとしているのか
というテーマを、わかりやすく深掘りしていく。
あなたの好きなRPGも、きっとこの物語のどこかに繋がって行く。さあ、一緒にRPGという冒険の歴史を旅していこう。
序章:なぜ “RPG” という言葉が重要なのか
ゲームジャンルとしての「RPG(Role Playing Game・ロールプレイングゲーム)」という呼び名には、ただ「ゲームを遊ぶ」だけでなく「役割を演じる」「物語を作る・物語に参加する」という体験が含まれている。
プレイヤーがキャラクターになり、その世界で「もし自分だったら…」と考えながら選択を重ね、成長し、冒険して行く。「演じる」体験こそが、RPGというジャンルの核である。
本稿では、テーブルトークRPG(TTRPG)から始まり、家庭用コンピュータ、コンソール向けRPG、そして現代のオンライン、オープンワールド、モバイルRPGへと至る流れを俯瞰しつつ、「なぜこのジャンルが私たちを惹きつけるのか」「どんな構成要素によってRPGは成立するのか」「これからどこへ向かうのか」を探る。
第1章:起源とテーブルトークRPGの誕生

『RPG』という言葉のルーツは、1970年代に登場したテーブルトーク型(机上型・紙+鉛筆+ダイス)のロールプレイングゲームにある。
代表格である Dungeons & Dragons(D&D、1974年)では、プレイヤーが「ファイター」「ウィザード」「ヒーラー」などのキャラクターを演じ、ゲームマスター(GM)が世界を語り、冒険を導くという構造が確立した。
この形式の特徴は、「キャラクター」「物語(シナリオ)」「プレイヤーの選択・ロールプレイ」という三本柱があること。
1970年代中盤には、ファンタジー以外にもSFジャンルのテーブルトークRPGが出現した。例えば Starfaring(1976年)など。
この「演じる」という概念が、後のコンピュータ/家庭用ゲーム機へのRPGジャンル拡張の大きな原動力となります。
テーブル型RPGがとんなものなのかは、ザックリと以下の通り。
- ボードゲームみたいにプレイヤー全員で机(テーブル)を囲む。
- 1人が「ゲームマスター(GM)」になり、世界観・状況・敵・NPC(村人とか)を担当。
- 他の人は「プレイヤーキャラクター(PC)」を1人ずつ担当して、勇者・盗賊・魔法使いなどの「役」を演じる。
- 会話メインで進んで行って、「こう行動したい!」→「じゃあダイス振って判定しよう」 みたいに サイコロ で結果を決める。
って感じ。(説明むずい)
第2章:コンピュータ・家庭用ゲーム機RPGの黎明期(70〜80年代)

テーブルトークRPGを起源としながら、1970年代〜80年代にかけてコンピュータゲーム・家庭用ゲーム機において「電子的なRPG(Video RPG)」が誕生し、徐々に一般化して行った。
例えば、大学のメインフレームで動く初期のRPG的プログラムや、ASCII・テキストベースのものが存在した。
また、日本国内でも、1984年の『ハイドライド』などが「アクションRPG」「オープンワールド的探索」を含む先駆作として注目された。
この時期の特徴を整理すると、以下のような点がある。
- ダンジョン探索・迷路・モンスターとの戦闘という構造
- 経験値(EXP)を獲得し、レベルアップして強くなる育成要素
- アイテム管理・装備・ステータスといった成長メカニズム
- 当初は技術的な制約ゆえストーリーが限定的・固定キャラが少ないケースも多かった
例えば、米国では PC 用RPGとして 『ウルティマ(Ultima I: The First Age of Darkness)』 や 『ウィザードリィ(Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord)』 が1980年代初頭にリリースされ、ヨーロッパ・北米のRPG文化の基盤となった。
一方、日本では、家庭用ゲーム機へ向けた独自の変化が起こる。例えば、固定主人公・物語重視・マンガ・アニメの表現技術を取り入れた「日本的RPG(JRPG)」の萌芽が見られ始めた。
1985年には『ドラゴンクエスト』が発売され、日本で爆発的なヒットを飛ばす。以降、RPGは屈指の人気を誇るジャンルとなる。
第3章:黄金期(90年代)とジャンルの多様化

1990年代に入ると、RPGジャンルは黄金期といえる拡張を見せる。市場が拡大し、家庭用機・PC機・アーケード機など多様なプラットフォームでRPGが花開いた。
ここでは主に「欧米PC系RPG(CRPG)」「日本家庭用機系RPG(JRPG)」という2つの潮流を対照しながら、その特徴を見てみよう。
欧米のCRPG(Computer RPG)
欧米では、プレイヤーが自由度の高いキャラクターを作成し、パーティーを編成して探索・会話・選択肢・ダンジョン攻略などを行うスタイルのRPGが深まった。
例として 『バルダーズ・ゲート(Baldur’s Gate)』(1998年)などは「D&Dルールを忠実に再現し、深い物語と自由な行動を実現した」作品として高く評価されている。
この時期には モッド(MOD)文化 も発展し、ゲームを拡張・改変して楽しむプレイヤー・コミュニティが活発になったのも欧米CRPGの特徴である。
日本のJRPG
一方、日本では「あらかじめ設定された主人公」「ドラマチックなストーリー」「カットシーンや演出重視」「固定キャラの仲間集め」といった傾向をもつRPGが台頭した。例えば『ファンターシースター(Phantasy Star)』(1987年)は、SF×ファンタジーという設定を持ち、女性主人公を採用し、日本国内外で注目された。
また、洋RPGとは異なる日本独特のキャラ萌えや物語演出という文化的バックグラウンドが、JRPGの形成に大きく寄与した。
更に、この時期にはサブジャンル化も進んだ。例えば「タクティカルRPG(戦略・マス目・ユニット・戦闘重視)」「アクションRPG(リアルタイム戦闘)」「オープンワールドRPG(自由探索重視)」などが登場し、RPGというジャンル自体の幅が広がった。
ハードウェアの進化(グラフィック性能、CD-ROM、演出、音声)とともに、プレイヤーの期待も高まり、「ただ育てて戦う」から「物語を体験・選択し成長する」という体験にシフトして行く。
第4章:2000年代〜現代:オープンワールド・オンライン・インディー化

2000年代以降、RPGジャンルはさらに大きな転換を迎えている。技術・市場・プレイヤー行動の変化を受け、「RPGらしさ」の定義そのものが拡張することになる。
オープンワールド・自由度の高い設計
例えば、プレイヤーが広大なフィールドを自由に探索し、サイドクエストやNPCとの交流、選択肢による物語分岐などを体験できるようなオープンワールド型RPGが主流となって行く。
舞台・システムともにスケールが大きくなった。
オンラインRPG・MMO化
また、インターネットの普及により、複数のプレイヤーが同じ仮想世界で冒険する MMO(Massively Multiplayer Online)RPGも定着した。
これは従来の「プレイヤー vs モンスター/世界」という構造から、「プレイヤー同士の協力・対戦・社交」が加わる変化を意味する。
モバイル・ソーシャルRPG
さらにスマホ・タブレット・ソーシャルゲームの登場により、「短時間プレイ」「断片的な冒険」「ガチャ・育成・キャラ収集」というRPG要素がモバイル市場で爆発的に広がった。
これによりRPG体験の裾野が大きく広がりましたが、同時に「ジャンルの希釈」という議論も起きている。
インディーゲームとジャンルの再定義
近年では、インディー開発者による小粒ながら独創的なRPG作品も増加している。技術の民主化(Unity・Unreal・ストリーミング)により、従来の大手メーカーの枠組みにとらわれない新しいRPG体験が模索されている。
このように、RPGジャンルは機械性能・ネットワーク・料金モデル・プレイヤー行動などを取り込みながら、形を変えつつも「演じる・選択する・成長する」というコアに立ち返る進化を続けている。
第5章:RPGジャンルの主要構成要素とゲーム体験の鍵
ここからは、「RPGとは何か」を整理するために、体験を支える主要な構成要素を掘り下げて行く。
キャラクター育成
RPGにおいて「育成=成長」は欠かせない。
プレイヤーが自分のキャラクター(あるいはパーティー)を操作し、経験値を得てレベルアップしたり、スキルツリーを開放したり、装備を強化したりするプロセス。
これにより、始めは弱いけど探索して戦って成長する、という快感が得られる。
また、多くのRPGでは「装備」「ステータス」「スキル」「アビリティ」などの成長メタ構造を備えており、自己改善と達成感が設計されている。
ストーリーテリング・世界観・キャラクター
「演じる」という意味で重要なのが、物語と世界観です。プレイヤー・キャラクターが「誰かになって」「何かを成し遂げる」という物語体験があるからこそ、RPGは単なるゲームプレイ以上の没入感を与える。
固定主人公でストーリーが強く提示されるタイプ(日本のJRPG型)もあれば、プレイヤー作成キャラ・自由度重視(欧米CRPG型)もある。前者は感情移入や演出力に、後者は自由度や没入感に強みがある。
世界観も重要です。ファンタジー(剣と魔法)、SF(星間旅行)、ホラー、現代ファンタジーなど設定が変わることでRPGの体験も大きく変化する。
選択と分岐・プレイヤーの「役割」感
RPGは「ただ進む・倒す」だけでなく、選択・分岐・プレイヤー自身の意思が反映されることが魅力。
どのクエストを受けるか、どのキャラクターを育てるか、世界にどう関わるか。これが「自分が役割を演じている」という感覚を生み出す。
最近の作品では、分岐エンディング・マルチルート・プレイヤーの行動による世界変化などが強化され、結果を受け止めたり、世界を変えるという感覚がより深くなっている。
探索・クエスト構造・インタラクティブな世界
RPGでは「旅」「冒険」「探索」がキーワードです。広いマップ、隠されたダンジョン、サイドクエスト、NPCとの交流、収集要素など。これらにより「世界を探る」「未知を発見する」喜びが得られる。
また、プレイヤーが世界の中で能動的に選び、動き、反応を得られる構造(インタラクティブ性)も重要である。
戦闘システム(ターン制・リアルタイム・ハイブリッド)
RPGには多様な戦闘システムがある。
古典的には『ドラゴンクエスト』のようなターン制(ターンバトル)を採用していた作品が多く、最近ではリアルタイム戦闘+戦略要素(『ファイナルファンタジー』のようなATB)、あるいはそのハイブリッド型も増えている。
戦闘をただ「数を倒す」だけでなく、戦術を考える、仲間との連携を考える、状態異常や属性を活かすといった要素があると、戦いそのものがゲーム体験の核になる。
第6章:地域別・文化的影響:日本 vs 欧米 vs アジア
RPGが世界中で発展してきた中で、地域ごとに文化的特徴や強み・弱みが存在する。
日本における「JRPG」の特色
日本では、マンガ・アニメ文化の影響を強く受けたキャラクターデザイン、語りの演出、音楽・シナリオの重視が特徴である。
研究でも「固定ストーリーライン」「経験値・レベルという育成メカニズム」「日本的キャラクターデザイン」が日本のCRPGとは異なる進化をたどったと指摘されている。
例えば、仲間キャラがストーリー中で台詞を交わし、感情ドラマとして展開する構造は典型的であり、このような「物語として楽しむRPG」文化が強く根付いている。
欧米におけるPC・CRPG文化
欧米では、テーブルトークRPG由来の自由度・パーティカスタマイズ・モッド文化・PC中心という流れがあります。プレイヤー自身がキャラクターを作り、世界を自由に探るというスタイルが根付いて行った。
例えば、『バルダーズ・ゲート』のような作品が象徴的である。
また、モッドやコミュニティによってゲームが拡張・改変されるという文化も欧米RPGの魅力の一つ。
アジア・モバイル市場の影響
近年、アジア諸国(中国、韓国、東南アジアなど)ではモバイルRPG市場が急速に拡大している。
これにより「短時間・断片プレイ」「ガチャ・キャラ収集」「ソーシャル要素」がRPGデザインに取り込まれるようになった。
地域による市場の特性・文化・料金モデルの違いが、RPGジャンルそのものの多様化を促している。
文化とゲームデザインの関係性
例えば、日本の妖怪・神話・マンガ文化、欧米のファンタジー(トールキン的世界観)やSF文学、アジアのスマホ文化といった背景がゲームデザイン・世界観・ユーザーの期待に影響を与えていふ。
RPGはただゲームのジャンルというだけでなく、文化の受容と変化を映す鏡でもあるのある。
第7章:RPGの未来展望と課題
RPGというジャンルは既に長い歴史を持ち、かつ今も進化を続けている。ここでは「これからのRPGはどうなるか」「何が課題か」を考えてみよう。
技術的進化と新たな可能性
- 人工知能(AI)・生成コンテンツ(Procedural Generation)
- プレイヤーの選択・行動に応じて世界や物語が変化する「動的RPG」の可能性。
- クラウド・ストリーミング・VR・メタバース
- 没入感がさらに高まり、仮想世界で「演じる」という体験が深化。
- ユーザー生成コンテンツ(UGC)・モッド・コミュニティ主導開発
- RPG体験がプレイヤーとクリエイターの境界を超えていく可能性がある。
これらを背景に、RPGは昔ながらの構造を維持しつつも、新しい体験装置として再定義されつつある。
ジャンルとしての課題
- マンネリ化/似通った構造:RPGの“育成+探索+戦闘”という根幹構造が何度も使い回されることで、新鮮味低下の懸念がある。
- マイクロトランザクション・ガチャモデル:特にモバイルRPGでは、「課金前提」「コレクション収集」が重視されるあまり、ゲーム体験そのものの質が問われている。
- サービス型ゲーム化による“終わりなき運営”
- RPGが「ソフトを買って終わる」から「サービスを遊び続ける」形へ移行し、プレイヤーの心理的負担や開発コスト・運営コストが増えている。
- ジャンル定義の曖昧化:アクション+RPG+シミュレーション+モバイルなど、ジャンル横断化が進み「RPGって何?」という問いが再び浮上している。
最後に:なぜRPGは私たちを魅了し続けるのか
RPGは、キャラクターになりきって世界を旅し、成長し、選択し、物語を紡ぐという「演じる・選ぶ・成長する」という体験を提供してくれる。
テーブルトークRPGというアナログ由来から始まり、コンピュータ・家庭用ゲーム機・オンライン・モバイル・インディーへと広がってきたこのジャンルは、技術・文化・市場の変化を受けながらも、その根底にある「もし自分だったら?」という問いを常に抱えている。
今後、どんな技術が、どんな物語が、どんな探索が私たちをさらに深いRPG体験へと導くのか、、、
読者の皆さん、それぞれにとっての「RPGとは何か?」を、この機会に少し立ち止まって考えてみて欲しい。